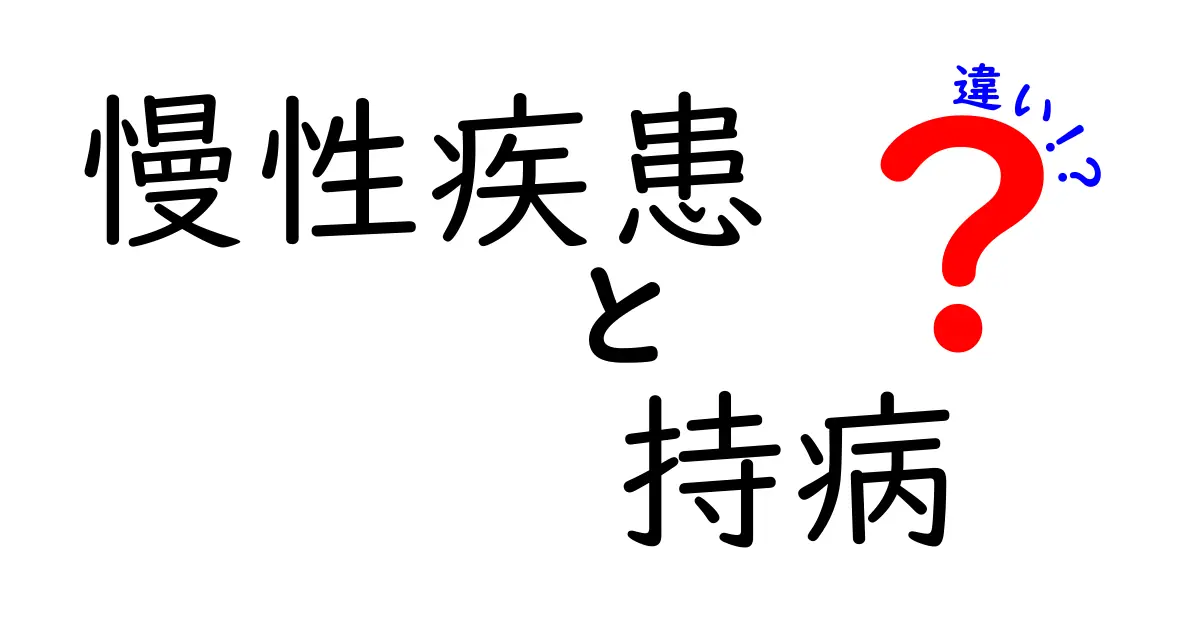

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
慢性疾患と持病の意味の違いとは?
私たちが病気について話すとき、「慢性疾患」と「持病」という言葉をよく耳にしますよね。
でも、実はこの二つは似ているようで少し意味が違うんです。慢性疾患とは、長期間にわたって症状が続く病気のことを言います。たとえば糖尿病や高血圧、ぜんそくなどがそれにあたります。
一方、「持病」は日常会話でよく使われる言葉で、自分がずっとかかえている病気や体の不調のことを指します。持病は慢性疾患のことを指す場合もありますが、厳密には「本人が自覚している継続的な病気」のニュアンスが強いです。
つまり、慢性疾患は医学的な用語で、持病はもっと広く、本人の視点や感覚を含んだ言葉だと言えます。
慢性疾患と持病の違いをわかりやすくまとめた表
なぜこの違いを知ることが大切なの?
慢性疾患や持病を正しく理解することは、自分や家族の健康管理に役立ちます。
医療機関では慢性疾患という言葉が使われますが、日常生活の中では持病という言葉の方がよく使われます。
例えば、持病がある人は特定の薬をずっと使っている場合があります。医師や看護師に伝える時にこれらの言葉の意味を正しく理解していると、正しい治療や対応をスムーズに受けることができるのです。
また、自分の健康状態に合わせて生活習慣を見直す際も、慢性疾患の特徴を知っておくと対策が立てやすくなります。
慢性疾患は長く付き合う病気ですが、生活の質を落とさずに過ごすことも可能です。これらの違いを理解して、正しい情報を持つことが健康な毎日につながります。
まとめ
このように「慢性疾患」と「持病」は似ていますが、医療用語か本人視点の言葉かという違いがあります。
慢性疾患は医学的に長期の病気を指し、持病は本人がかかえている病気や不調のこと。
それぞれの意味を理解して、健康についての話をする時に正しく使い分けると良いでしょう。
「持病」という言葉は、実は本人が自分の体の状態をどう感じているかに大きく影響されます。例えば同じ慢性疾患でも、症状が軽くてあまり気にならない場合、本人は「持病」とはあまり呼ばないかもしれません。逆に症状が日常生活に大きく影響していると感じている時は「これは私の持病だ」と強く認識します。このように、持病は医学的な診断だけではなく、本人の自覚の度合いで呼び方が変わる不思議な言葉なんです。
前の記事: « 心不全と運動不足の違いとは?特徴・原因・対策をわかりやすく解説!





















