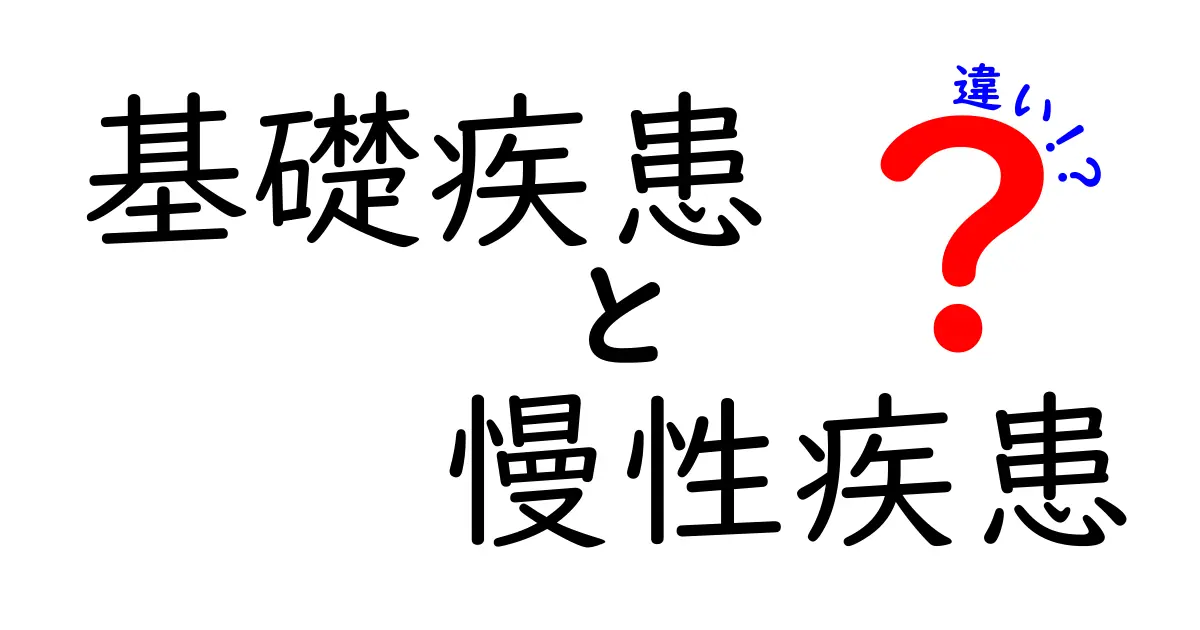

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基礎疾患と慢性疾患の違いを知ろう
皆さんは「基礎疾患」と「慢性疾患」という言葉を聞いたことがありますか?
特に最近はニュースや医療でよく耳にする言葉ですが、実は似ているようで意味が少し違います。健康や病気について正しく理解することは、日々の生活にもとても大切です。
まず結論からいうと、基礎疾患はある病気の背景にある持っている病気のことで、
慢性疾患は長く続く病気のことです。
この2つの言葉は混同されやすいので、まずはそれぞれの意味をしっかり押さえましょう。
基礎疾患とは?
基礎疾患とは、もともと持っている病気のことを指します。
例えば、糖尿病や高血圧、心臓病、肺の病気などがそうです。
これらの病気があると、ほかの病気にかかったときに症状が重くなったり回復が遅れたりすることがあります。
例えば新型コロナウイルス感染症の場合、基礎疾患がある人は重症化しやすいと言われています。
大切なのは、基礎疾患は病気がどんな状態か、またどのように影響するかを考えるときの「背景」となる病気だということです。
基礎疾患は必ずしも長く続くとは限らず、慢性か急性かは関係ありません。
慢性疾患とは?
一方、慢性疾患とは長期間、繰り返し症状が続く病気のことを指します。
たとえば、糖尿病や高血圧、慢性の気管支炎や関節リウマチなどです。
病気が長い期間続く特徴があります。
慢性疾患はなかなか治らず、長く付き合っていく必要がある病気と考えられています。
慢性疾患の管理には生活習慣の改善や薬の服用が重要になります。
慢性疾患は基礎疾患の一種と考えることもでき、長期間の病気の状態を指します。
基礎疾患と慢性疾患の違いを表でまとめると?
| ポイント | 基礎疾患 | 慢性疾患 |
|---|---|---|
| 意味 | もともと持っている病気のこと(背景となる病気) | 長期間続く病気のこと |
| 期間 | 短期・長期どちらもありうる | 基本的に長期間続くもの |
| 例 | 糖尿病、高血圧、心臓病など | 糖尿病、高血圧、慢性気管支炎など |
| 役割 | 他の病気の重症化などに影響する背景 | 長く症状が続く病気そのもの |
まとめ
・基礎疾患は、ある病気の背景として存在し、それがあることで他の病気が重症化しやすくなることがある
・慢性疾患は、長期間続く病気のことで、生活習慣の改善や薬で管理が必要
・慢性疾患が基礎疾患の一種になることもある
この違いを知ることで、自分や家族の健康管理に役立ちます。
病気の種類や期間を理解し、適切な予防や治療を心がけましょう!
「基礎疾患」という言葉は、もともと持っている病気という意味ですが、実は単に病気の種類だけでなく、その病気がほかの病気の重症化にどれだけ影響を与えるかも含まれます。たとえば、同じ糖尿病でもコントロールが良い人と悪い人では体への影響が変わります。だから「基礎疾患」と聞いたときは、その病気の状態や管理状況も考えることが大切なんですよ。
前の記事: « 消込と相殺の違いとは?初心者でもわかる会計・経理の基本解説





















