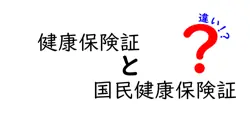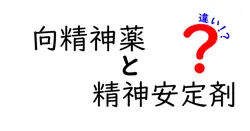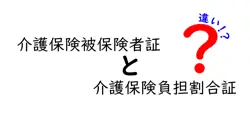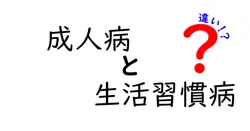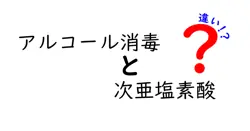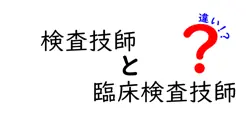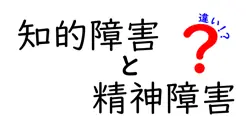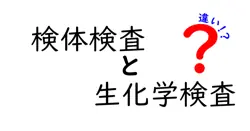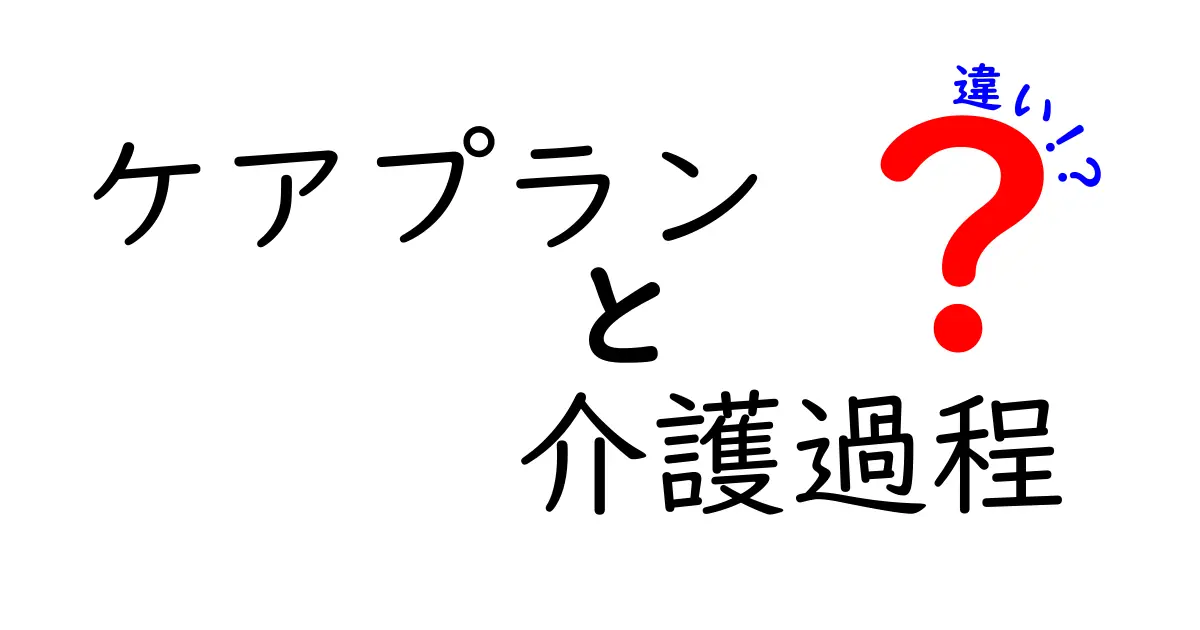
ケアプランと介護過程の違いって何?基本から知ろう
介護に関わる仕事やサービスを考えるとき、よく聞く言葉が「ケアプラン」と「介護過程」です。どちらも大切な役割を持っていますが、意味や使い方が違うため、混同しやすいものです。
簡単に言うと、ケアプランは利用者のために作成する具体的な計画書、
介護過程はその計画を立てる際の考え方や手順を表します。
この違いを理解することで、介護サービスの質を高めたり、利用者に合った支援ができるようになります。
以降では、それぞれの意味や役割、具体的な内容、違いを丁寧に解説していきます。
ケアプランとは?利用者に合わせた介護サービスの設計図
ケアプランとは、正式には「介護サービス計画」と呼ばれるものです。
利用者がどのような介護や支援を受けるべきか、具体的にまとめた書類のことを指します。
主にケアマネージャー(介護支援専門員)が中心となって作成し、利用者本人や家族、介護スタッフと相談しながら決めていきます。
ケアプランには以下のような内容が含まれます。
- 利用者の目標や希望
- 必要な介護サービスの種類や頻度
- サービス提供の体制やスケジュール
- 予算や費用の見込み
この計画に沿って、利用者へサービスが提供されるため、介護の方向性や内容を具体的に示す設計図と言えます。
介護過程とは?ケアを組み立てるための考え方の流れ
介護過程は、ケアプランを作成する前に使われる考え方や手順のことです。
どのようにして利用者の状態を確認し、必要な支援を考え、計画を立てるかというプロセスのことを指します。
介護過程は大きく4つの段階があります。
- アセスメント(利用者の状況や希望を評価)
- 診断(支援が必要な課題を整理)
- 計画(ケアプランの作成)
- 評価(計画の効果を確認し改善)
この流れを踏むことで、科学的かつ体系的に介護サービスを提供することが可能になります。
介護過程は、利用者一人ひとりに適したケアプランを作るための大切な土台と言えるでしょう。
ケアプランと介護過程の違いを表で比較しよう
まとめ:ケアプランと介護過程、どちらも大切な介護の基礎
ケアプランは利用者が受ける介護サービスの具体的で分かりやすい計画書で、
介護過程はその計画を作成するための評価から改善までの手順や考え方です。
両者をしっかり理解して使い分ければ、より質の高い介護サービスにつながります。
介護に関わる人はもちろん、家族の方もケアプランと介護過程の違いを知っておくと、
利用者に合った支援を考える手助けになるでしょう。
ぜひ今回の内容を参考にして、介護現場の理解を深めてください。
ケアプランという言葉はよく聞きますが、実はそれを作るために欠かせないのが「介護過程」です。
介護過程は、ただの手順ではなく、利用者の状態や希望をしっかり見極め、計画がちゃんと機能しているかを評価・改善するとても大切な考え方なんです。
つまり、ケアプランは結果で、介護過程はその結果に至るまでの道のり。この両方があって初めて良い介護サービスができるんです。
日々の介護で利用者の変化に気づきやすくするためにも、介護過程の理解は現場のキモなんですよね。
前の記事: « 感染と感染症の違いは?中学生にもわかるわかりやすい解説
次の記事: 臨床試験と臨床開発の違いとは?初心者にもわかりやすく徹底解説! »