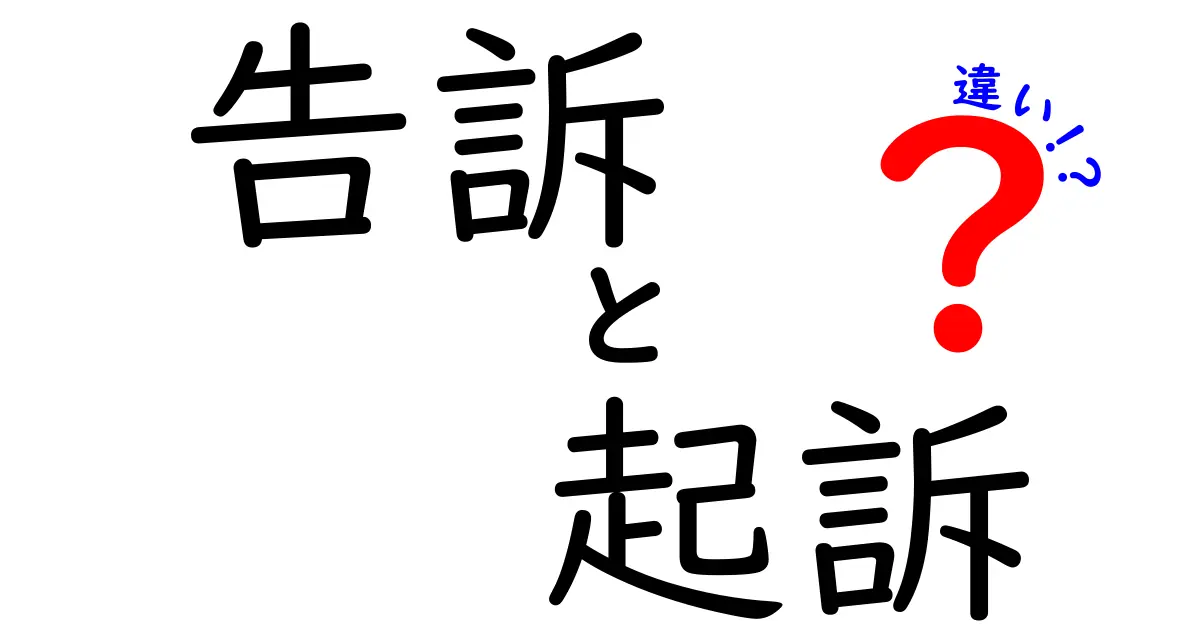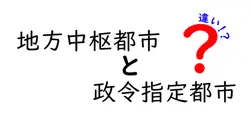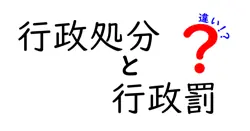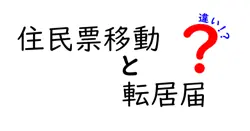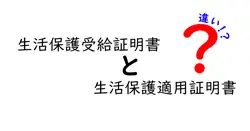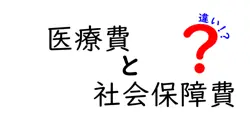告訴と起訴の基本的な意味を知ろう
<まずは告訴と起訴という言葉の意味を簡単に説明します。告訴とは、犯罪の被害者やその代理人が警察や検察に対して『この人を処罰してください』と申告することです。つまり、被害者側からの申し入れで犯罪を認めてほしいという意思表示です。これに対して起訴とは、検察官が裁判所に『この人を裁判にかけます』と正式に申し立てることを指します。
告訴は民間人がする行為、起訴は国家の検察官が行うものであり、その役割や目的は大きく異なります。
そのため、告訴されたから必ず起訴されるわけではありません。起訴されるには、検察官が証拠や状況を判断し、裁判にかける価値があると判断しなければならないからです。
<告訴の特徴と流れ
<告訴は被害者が主体となって行います。例えば、盗難や暴行などの事件で被害にあった場合、まずは警察に被害届けを出します。さらに加害者を処罰してほしい場合、その意志をはっきり伝えるために告訴します。
告訴のポイントは以下の通りです。
- 原則として被害者本人またはその代理人しか行えない
- 告訴がないと処罰されない罪(親告罪)がある
- 告訴できる期間は犯罪発覚から6か月以内が一般的
- 告訴は警察や検察に行い、受理されると捜査が本格化する可能性が高い
告訴があると警察が捜査をすすめ、証拠を集めます。
<起訴の意味と流れ
<起訴は国家の検察官が行う手続きで、裁判所で正当に審理を行うための重要な段階です。起訴されると被告人は裁判を受けることになります。
検察官は、警察の捜査結果などをもとに証拠を検討します。証拠が十分で社会的に処罰の必要があると判断した場合に起訴します。逆に証拠が不十分な場合や情状酌量が必要な場合は不起訴にすることもあります。
起訴には以下の特徴があります。
- 検察官が裁判所に対して刑事事件の審理を申し立てる
- 起訴されるかどうかは告訴とは別に決められる
- 起訴されると裁判が始まり、被告人の有罪・無罪が判断される
- 不起訴の場合は被告人は処罰されない
<告訴と起訴の違いのまとめ
<ding="5" cellspacing="0">< < < | 項目 | < 告訴 | < 起訴 | <
< < | 主体 | < 被害者や代理人 | < 検察官 | <
< < | 目的 | < 加害者を処罰してほしい意思表示 | < 裁判にかけるための正式な申し立て | <
< < | 手続きの場所 | < 警察や検察 | < 裁判所 | <
< < | 効果 | < 捜査が開始または強化される | < 裁判が開始される | <
< < | 必要条件 | < 被害者の意思が必要(親告罪の場合) | < 証拠や社会的判断により決まる | <
< <able><告訴と起訴を正しく理解してトラブルを防ごう
<このように告訴と起訴は法律上まったく異なる意味と役割を持っています。被害者はまず告訴という形で警察や検察に訴え、その後起訴されるかどうかは専門家である検察官の判断に委ねられます。
もし身近な事件で告訴や起訴に関わる可能性がある場合は、用語の意味をしっかり押さえておくことが重要です。法律相談や専門機関への相談も活用し、正しく理解しましょう。
告訴=被害者が訴え、起訴=国家が裁判へ進める申し立てと覚えておくとわかりやすいでしょう。
ピックアップ解説「親告罪」という言葉をご存知ですか?これは「告訴がなければ処罰できない罪」のことです。例えば名誉毀損や軽犯罪が該当します。つまり被害者本人が『告訴しない』と判断すれば、たとえ犯罪があっても処罰されないこともあります。告訴がどれほど重大な役割を果たしているかが分かる興味深いポイントですね。法律の世界はこうした細かいルールがいっぱいで、見た目以上に複雑です。中学生でも少し興味を持っておくと将来役に立ちますよ!
政治の人気記事

200viws

199viws

157viws

144viws

139viws

125viws

107viws

99viws

92viws

88viws

82viws

82viws

81viws
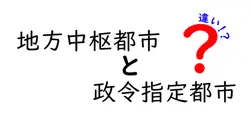
77viws

76viws
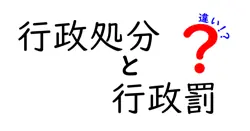
74viws
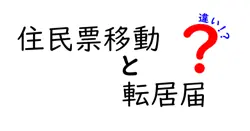
72viws
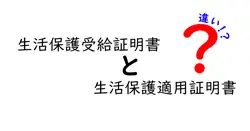
70viws

66viws
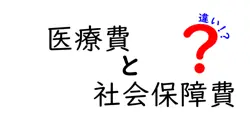
66viws
新着記事
政治の関連記事