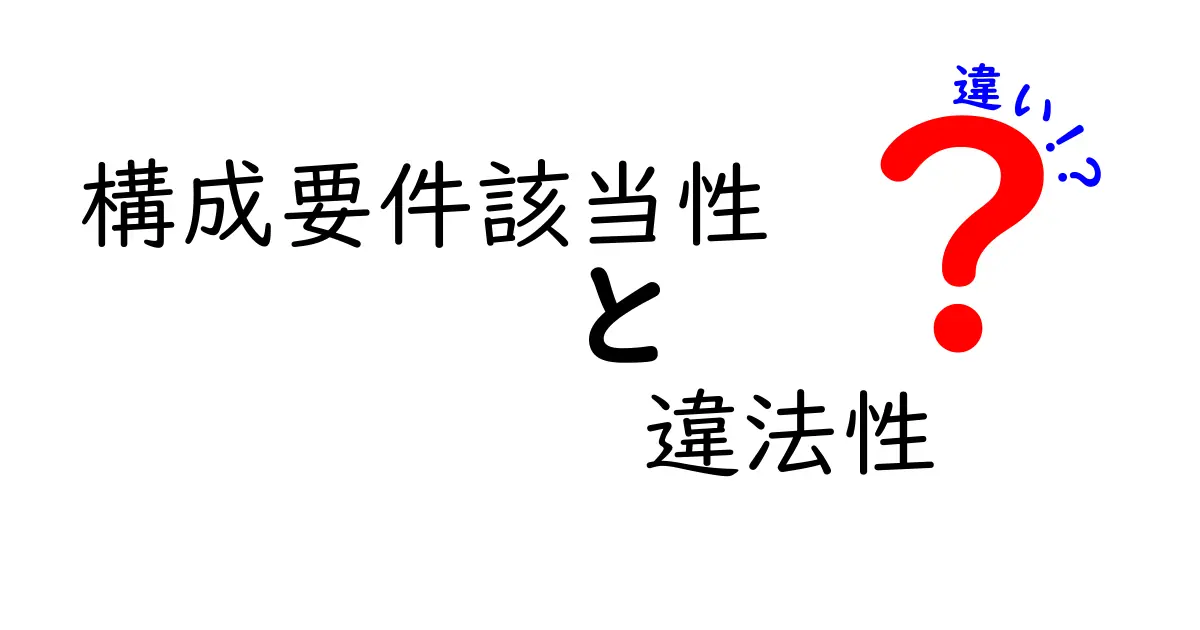
構成要件該当性とは何か?
「構成要件該当性(こうせいようけんがいとうせい)」は、刑事事件で使われる大事な言葉です。
簡単にいうと、ある行為が法律で禁じられている犯罪の条件に当てはまるかどうかを確かめることです。
例えば、もし誰かが物を盗んだとすると、その行為が「窃盗」という犯罪の条件に合っているか調べます。
つまり、「行為が法律の犯罪の形(構成要件)にピッタリ合っているかどうか」を見るのが構成要件該当性なのです。
ここで大事なのは、まだそれが違法かどうかは判断しないこと。犯罪の形に合っているという条件だけを調べます。
この部分が犯罪成立の第一歩となるのです。
違法性とは何か?
次に「違法性(いほうせい)」ですが、これは行為が法律に反しているかどうかの問題です。
構成要件に該当したとしても、その行為が法律上認められている理由があれば違法ではありません。
例えば、正当防衛があります。
誰かが自分や他人の身を守るために攻撃した場合、その行為は一見すると暴行や傷害かもしれませんが、「正当防衛」という理由で違法とはされません。
これが違法性の否定と呼ばれる部分です。
つまり、違法性は構成要件に該当した行為が法律に照らして禁止されるか、許されるかを判断する段階なのです。
違法な行為なら処罰されますし、違法性が否定されれば処罰されません。
構成要件該当性と違法性の違いまとめ
ここまでの説明をまとめてみましょう。 このように、構成要件該当性は犯罪の形式的な条件のチェック、違法性はその行為が許されるかどうかの判断をするという違いがあります。 今回は「構成要件該当性」と「違法性」の違いについて、中学生にもわかるように解説しました。 「構成要件該当性」という言葉は、法律の中でもちょっと難しく感じますよね。これは、犯罪として処罰されるための条件がぴったり当てはまるかを確かめるもので、まさに“法律のチェックリスト”のようなものなんです。面白いのは、同じ行為でも条件に当てはまらなければ犯罪にならないこともある点です。例えば、単にものを持ち上げただけなら盗んだことにはなりません。でもそれが“盗む”という意図や状況と合えば、構成要件に該当してしまう。つまり、行為だけでなく背景や意図も法律が見ている部分なんですよ。 前の記事:
« 「懲戒処分」と「訓告」の違いとは?違いをわかりやすく解説! 次の記事:
執行猶予と禁固刑の違いを徹底解説!中学生でもわかる刑罰の基本 »ポイント 構成要件該当性 違法性 意味 犯罪の法律上の条件に合っているかどうか 法律に違反して禁止されているかどうか 判断の順番 最初に行う 構成要件が該当してから判断 結果 行為が犯罪の形に合う その行為が処罰されるかが決まる 例 物を盗んだ=窃盗の条件に合う 正当防衛なら違法ではない
刑事事件の理解には、この二つの概念をしっかり把握することがとても大切です。まとめ
構成要件該当性は、行為が犯罪の条件に当てはまるかを判断することです。
違法性は、そうした行為が法律的に許されるかどうかを判断します。
両方を理解することで、刑法の仕組みや法律の考え方がよりわかりやすくなります。
法律の話は難しく感じやすいですが、身近な例から考えてみると理解が深まりますよ。
の人気記事
新着記事
の関連記事



















