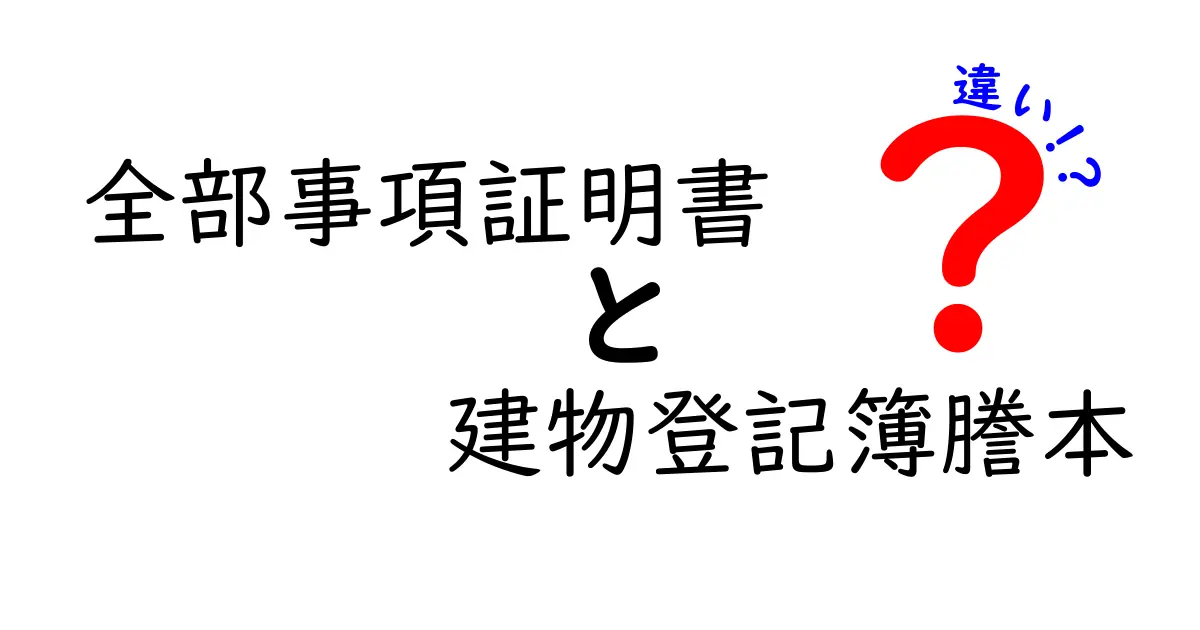

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
全部事項証明書と建物登記簿謄本、何が違うの?
不動産を買ったり売ったりする時によく耳にする「全部事項証明書」と「建物登記簿謄本」という言葉。
でも、「これって同じもの?違うの?」「どうやって使い分けるの?」と思う人も多いですよね。
簡単に言うと、両方とも登記情報を証明する書類ですが、呼び方や発行の仕方に違いがあります。
ここでは、中学生でもわかるように、その違いと特徴を分かりやすく解説します。
■ 登記簿謄本とは?
登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、不動産登記簿の内容をそのままコピーしたもののことです。
以前は登記簿に記載された情報の全部または一部を正式な写しとして発行していて、
「謄本」という言葉は「登記内容の全文写し」を意味します。
建物や土地の所在地、面積、所有者の名前、権利関係などが詳しく書かれている書類です。
過去の登記も含めて情報が記載されています。
■ 全部事項証明書とは?
全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)は、登記簿謄本の内容を電子化した書類として発行されるものです。
不動産登記制度がデジタル化されたことで、現在は「登記簿謄本」という言い方よりもこちらの呼び方が正式になっています。
この証明書は登記簿に記載されたすべての情報を証明するもので、最新の正確な登記情報を提供します。
つまり、全部事項証明書は登記簿謄本の電子的に更新された新しい名前の書類と考えて良いでしょう。
どんな違いがあるの?一覧でチェック!
| ポイント | 登記簿謄本 | 全部事項証明書 |
|---|---|---|
| 名称の違い | 法務局で昔から使われていた書面上の写し | 現在の正式名称で電子化された証明書 |
| 発行方法 | 紙の登記簿から写しを取って発行 | 電子情報から印刷して発行 |
| 情報の新しさ | 紙ベースで更新に時間がかかることも | 最新の情報をすぐに入手可能 |
| 呼ばれ方 | 一般に「謄本」と呼ぶ | 「全部事項証明書」が正式名称 |
なぜ、呼び方が変わったの?
2004年(平成16年)から不動産登記情報の電子化が進み、昔の紙の登記簿謄本は電子データによる証明書に切り替わりました。
これにより、 issuance(発行)が速くなり、データの正確性・利便性も向上。
その結果、新しい名前として「全部事項証明書」が使われています。
ただし、昔から「謄本」という言葉になじんでいる人も多いため、両方の呼び方が混在して使われているのです。
まとめ:不動産取引で大切なのはどっち?
実際の利用では、「全部事項証明書」と「建物登記簿謄本」はほぼ同じものを指し、不動産の権利関係や所有者を確認するのに同等の証明書です。
法務局やオンラインで取得する場合は「全部事項証明書」の名称が使われ、情報も新しくて正確。
不動産売買や相続などの際に提示を求められたら、どちらの名称でも基本的には問題ありません。
慣れている方は昔ながらに「謄本」と呼んだり、書類の名称差に戸惑うこともありますが、今は電子化された全部事項証明書が主流と覚えておきましょう。
「全部事項証明書」という言葉を聞くと少し難しく感じますよね。でも実はこれは登記簿謄本の電子版で、紙の書類ではなく、パソコンで管理された最新の情報なのです。登記情報が電子化される前は、すべて手作業で書面を確認していたので時間がかかったんです。今では、クリックひとつで正確で速い証明書が手に入る便利な時代になりました。これは不動産に関わる人にとってはとても大きな進化と言えますね!
前の記事: « 検案書と死亡届の違いとは?分かりやすく解説します!





















