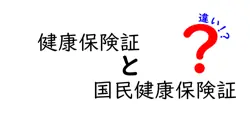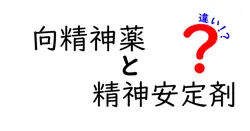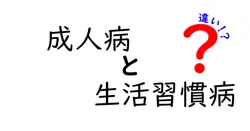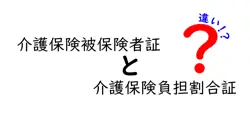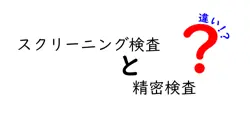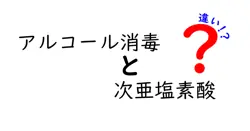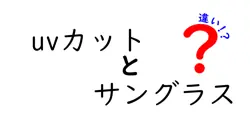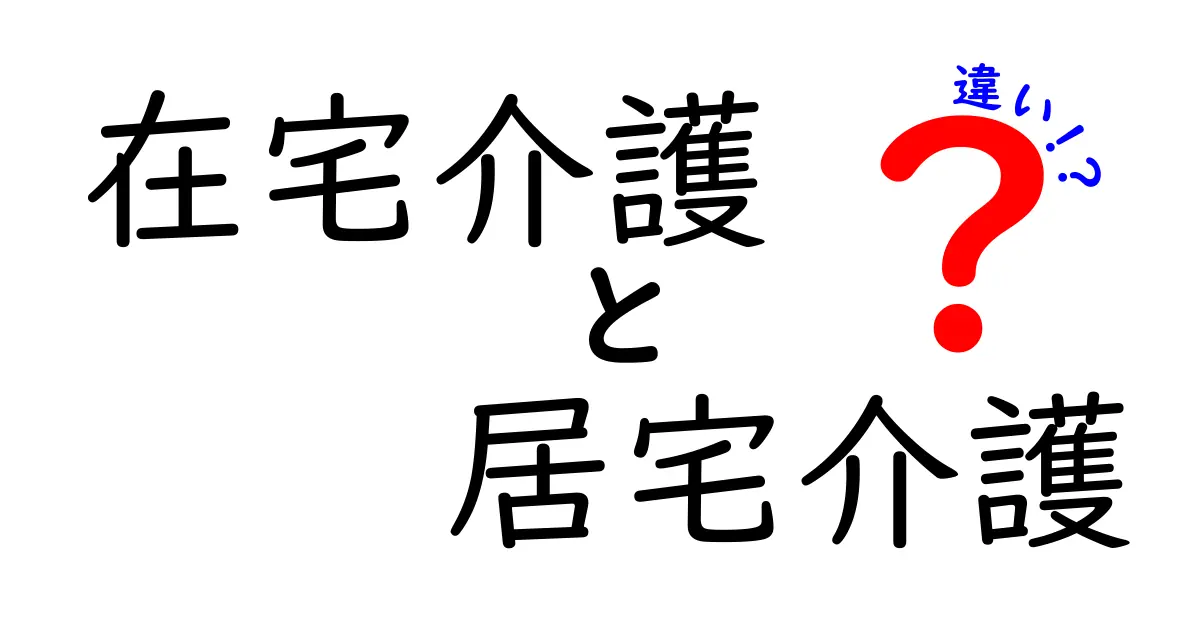
在宅介護と居宅介護の基本的な違いとは?
在宅介護と居宅介護は、似た言葉に見えますが、実は意味や使われ方に違いがあります。
まず、在宅介護とは、自宅で家族や介護者が直接介護を行うことを指します。高齢者や障がいのある方が自宅で安心して生活できるように助けることが目的です。家族や訪問介護サービスがサポートをする場合も多いです。
一方、居宅介護は、介護保険制度の中で定められたサービスの一つで、訪問介護や訪問看護、デイサービスなど、自宅に「介護の専門スタッフ」が訪問して提供するサービス全般を指します。つまり、居宅介護は法的な仕組みの中で実施されるサービスの名称です。
このように、在宅介護は介護の場所や状況を示す言葉で、居宅介護は介護保険に基づく制度上のサービスの通称という点に大きな違いがあります。
具体的なサービス内容と対象者の違い
在宅介護では家族や親しい人が中心となって日常生活の支援を行います。具体的には食事の介助、入浴の手伝い、トイレの介助、服薬管理などです。これらは無償または少額の費用で手助けが行われがちですが、介護者の負担は大きいことが多いです。
一方、居宅介護のサービスは市区町村や介護保険制度を通じて専門の介護スタッフが提供します。訪問介護員や看護師などが定期的に訪問し、専門的に身体介助や生活支援を行います。また、介護保険を使うため、費用の一部が公費負担となり家族の負担が軽減されやすいです。
対象者も少し違います。在宅介護は家族の事情や本人の希望に応じて自由に行えますが、居宅介護は要介護認定を受けた方が介護計画に沿って利用するサービスです。
表でわかる在宅介護と居宅介護の違いまとめ
| 比較項目 | 在宅介護 | 居宅介護 |
|---|---|---|
| 意味 | 自宅で家族などが行う介護全般 | 介護保険制度を利用した自宅での専門サービス |
| 提供者 | 家族や親しい人 | 介護専門スタッフ(訪問介護員、看護師など) |
| 費用 | 無償や家族負担が多い | 介護保険適用で公費負担あり |
| 対象者 | 自由に行える | 要介護認定者 |
| サービス例 | 食事介助、入浴補助、話し相手 | 身体介助、生活支援、医療的ケア |
まとめ:目的に合わせて適切な介護サービスを選ぼう
在宅介護は家族の温かさや自由度が大きなメリットです。しかし、身体的・精神的負担が大きくなる場合もあります。
一方、居宅介護は専門スタッフによるケアで安心感があり、公的な支援も充実していますが、利用には要介護認定が必要です。
介護が必要な方やその家族は、それぞれの特徴を理解し、本人の生活環境や希望、介護負担のバランスを考えて適切なサービスを選ぶことが大切です。
介護は決して一人で抱え込まず、専門の相談員やケアマネージャーに相談しながらより良い在宅生活を続けていきましょう。
居宅介護と聞くと「専門スタッフが来てくれる安心なサービス」と思いがちですが、実は利用するには本人が要介護認定を受けていることが大前提です。つまり、居宅介護は単なる訪問ケアではなく、国が正式に認めた介護計画に基づくサービスなのです。この制度のおかげで、家族の負担が軽減されるだけでなく、ケアの質も保障されている点が現代の大きな強みと言えるでしょう。
前の記事: « 「医師会」と「医師協同組合」の違いとは?わかりやすく解説します!
次の記事: かかりつけ医と病院の違いとは?わかりやすく解説! »