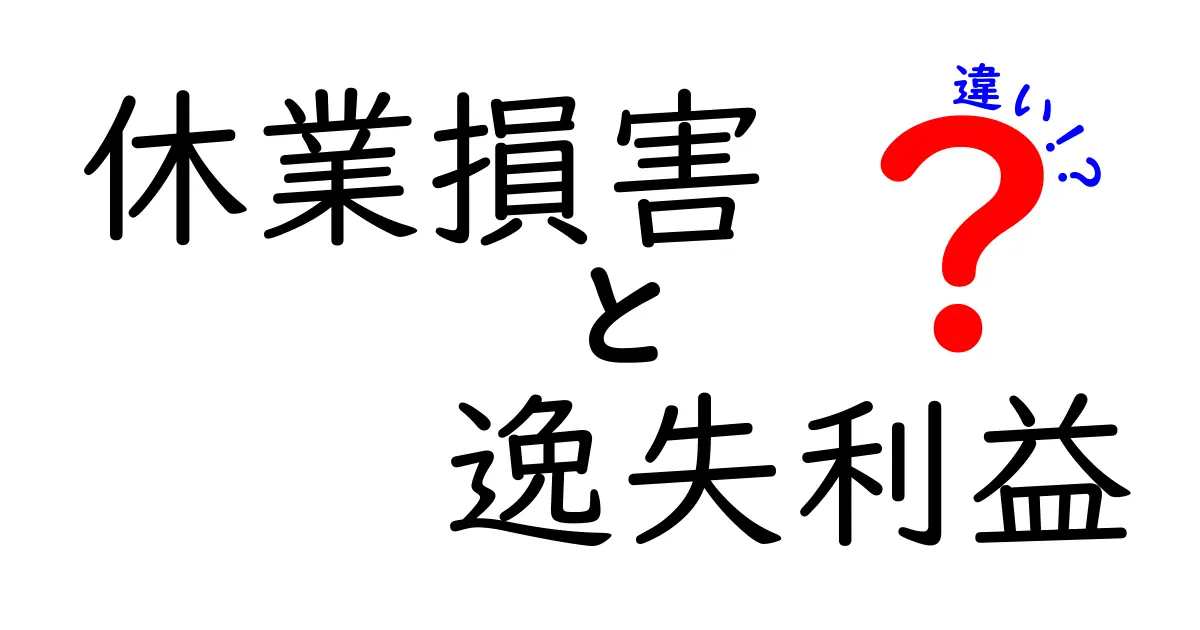

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
休業損害と逸失利益の基本的な違いとは?
交通事故や仕事中のけがなどで収入が減った場合、損害賠償として請求できる損害の種類に休業損害と逸失利益があります。
この二つは似ていますが、実は違う意味を持っています。
まず、休業損害とは、事故やけがのせいで働けなかった期間の収入減少分を指します。会社員やアルバイトのように、実際に働いた日数が減った場合に請求できます。
それに対し、逸失利益は、けがなどが原因で将来にわたって収入が減ってしまう可能性がある場合、つまり長期的・将来的な収入減少を見越した賠償金です。
このように休業損害は“現実に働けなかった期間の損害”で、
逸失利益は“将来にわたる収入減少の見込み”をカバーしています。
この点が最も大きな違いです。
しっかり理解することで損害賠償請求時に適切な補償を受けることが可能になります。
休業損害の具体例と計算方法について
休業損害は、たとえば突然の事故で数日間入院したり、けがの治療で会社を休んだりした場合に発生します。
例えば、通常1日1万円稼いでいる人が3日間仕事を休んだ場合、休業損害は単純に3万円になります。
実際の計算では、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの収入証明書類をもとに、1日あたりの収入を割り出します。自営業者の場合は、特に収入の変動や事業損害の有無などを細かく調査して計算します。
また、通勤時間や残業代が損害に含まれることもあります。
注意点としては、休業したことが証明できないと認められない可能性があるため、診断書や職場の証明書を用意する必要があります。
逸失利益の意味と計算のポイント
逸失利益は将来的に稼ぐはずだった利益が失われる損害のことです。例えば交通事故で重い後遺障害が残り、仕事に復帰できなくなったり、能力が低下して収入が減ることが考えられます。
計算は少し複雑で、元々の平均年収や労働能力の喪失割合、就労期間(ケースによっては定年まで)を考慮し、そこに生活費等を除いた利益額を計算し、その総和を現在価値に割り引いて求めます。
表でまとめると以下のようになります。項目 意味 基礎収入額 事故前の平均的な年収など 労働能力喪失率 事故による能力低下の程度(%) 労働予定期間 減収と見込まれる期間(例:定年までの年数) 生活費控除 生活に必要な費用を差し引く 割引率 将来の損害を現在価値に換算
これらを元に専門家が計算します。
注意点は、逸失利益の計算は証明責任が厳しく、必要な資料や医学的証明書の提出が不可欠です。
休業損害と逸失利益を混同しやすい理由と判例の例
休業損害と逸失利益は共に収入減に関する損害で、法律用語としても似ているため混同されやすいです。
例えば短期間で治るけがは休業損害として扱い、長期的かつ恒久的障害がある場合は逸失利益の対象となります。
過去の判例でも判断基準が微妙に異なり、医師の診断書や専門鑑定書で労働能力の喪失度合いが示されることで逸失利益認定に繋がります。
双方の損害は別々に請求できる場合もあるため、正しく理解し、専門家と相談しながら準備することが大切です。
また、賠償額の合計が二重に同じ損害をカバーしないよう調整される場合もあります。
「逸失利益」ってちょっと難しい言葉ですよね。実はこれは“これから先に稼げなくなるお金”のことなんです。でも、どうやってその将来的な金額を計算するかってすごく大変なんですよね。医療の診断や仕事にどのくらい影響が出るか、退職までの期間、生活費のことまで考える必要があって、保険会社や裁判所で専門家がじっくり検討するんです。つまり、逸失利益は“未来の損害”をしっかりと見積もるための、とても大事な損害賠償の一部なんですね。





















