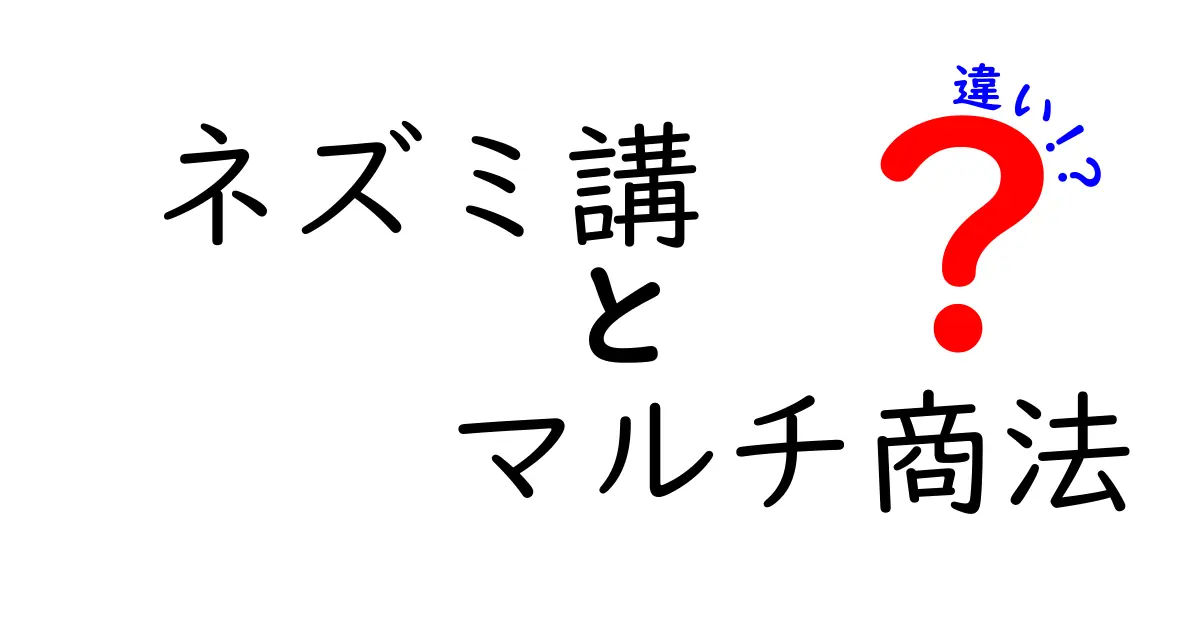

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ネズミ講とマルチ商法の基本の違いとは?
まずはネズミ講とマルチ商法の違いを理解しましょう。どちらも似た言葉で、よく混同されがちですが、実は法律的にもビジネスの形態としても違いがあります。
ネズミ講は主に新しい会員を勧誘し、その会員からお金を集めることで利益を上げる仕組みです。商品やサービスの販売がなく、単に人を集めることで成り立っているため、法律で禁止されています。
一方、マルチ商法は商品の販売を主としたビジネスです。新しい会員を勧誘することで報酬が得られますが、あくまでも商品やサービスの取引が中心である点が特徴です。ただし、悪質なマルチ商法は違法となることがありますので注意が必要です。
ネズミ講とマルチ商法の仕組みと法律の違い
ネズミ講は「無限連鎖講防止法」により、日本では禁止されています。
この法律は、商品の販売を伴わずに参加者からお金を集めるビジネスモデルを禁じるものです。参加者は新しい人を勧誘することで報酬を得ますが、それが限界を迎えると社会問題に発展しやすいためです。
マルチ商法は「特定商取引法」によって規制されています。商品やサービスの販売が中心で合法的なビジネスですが、消費者が適切な説明を受けなかったり、過大な勧誘を受けたりした場合は違法となる場合があります。つまり、マルチ商法は合法である場合も多いですが、ネズミ講は完全に違法です。
ネズミ講とマルチ商法の被害例と見分け方
被害に遭わないために大事なのが、両者の特徴を見分けることです。
- ネズミ講の特徴:商品がない、勧誘が強引、参加費が必要、報酬が新規会員の勧誘による点
- マルチ商法の特徴:実際に商品やサービスが販売されている、新規会員の勧誘もあるが主は商品販売、契約内容や商品の説明がある
以下の表でも違いを比較してみましょう。
| ネズミ講 | マルチ商法 | |
|---|---|---|
| ビジネスの中心 | 新規会員の勧誘のみ | 商品の販売と会員勧誘 |
| 法律の扱い | 違法(無限連鎖講防止法違反) | 条件を満たせば合法だが要注意 |
| 商品・サービス | なし | あり |
| 報酬の仕組み | 新規会員の参加費から支払い | 商品の販売と紹介による報酬 |
この違いを理解すると見分ける目が養え、被害を防ぎやすくなります。
ネズミ講や悪質マルチ商法に遭わないためにできること
被害に合わないためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 商品の有無や価値をよく確認すること
- 契約内容や報酬の仕組みを詳細に理解すること
- 強引な勧誘や短期間で大きな利益を謳う話には注意すること
- 疑わしい場合は専門機関に相談すること
特に「新しい人を誘うことが中心のビジネスはネズミ講の可能性が高い」と覚えておくのが大切です。
また、マルチ商法でも正当な事業なのか、違法性があるのかは専門家の判断を仰ぐことも重要です。
ネズミ講について少し掘り下げてみると、その名前の由来はネズミのように次々と仲間(参加者)が増えていく様子から来ています。でもその仕組みは実はとても危険。表面的には仲間を増やすだけで儲かるように見えて、実際には新しい人が増えないと成り立たないため、いずれ破綻してしまうんです。なので昔から世界中で禁止されてきました。ちょっと面白いのは、日本だけでなく世界中で似たような問題が頻繁に起きているということ。歴史と社会の中でこうしたビジネス形態がどう扱われてきたかを知ると、もっと注意深くなるきっかけになるかもしれませんね。
次の記事: 英語で「詐欺師」とは?違いをわかりやすく徹底解説! »





















