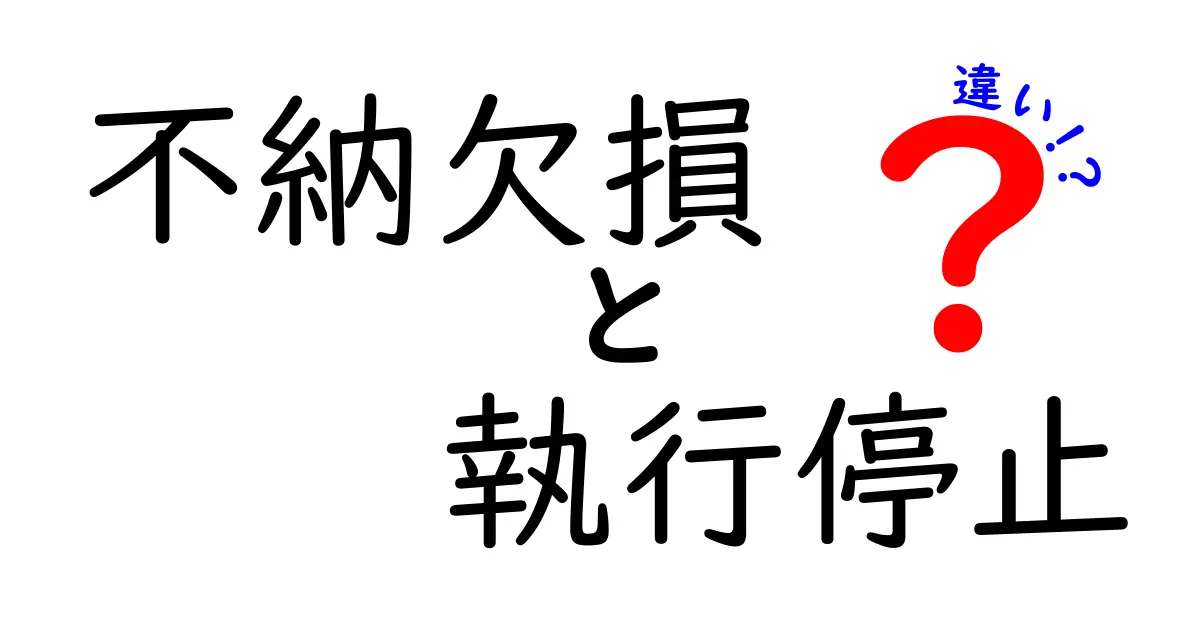

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
不納欠損とは何か?その意味と特徴をわかりやすく解説
税金の徴収に関する言葉で「不納欠損(ふのうけっそん)」という言葉があります。
不納欠損は、簡単に言うと「税金を徴収できない状態」のことを指します。たとえば、納税者が破産してしまった場合や、税金を払ってもらう相手が行方不明で所在がわからない場合などが該当します。
税務署や国が税金を徴収しようとしても、どうしてもお金を回収できないため、このように「欠損(損失)」として扱うわけです。
この不納欠損が認められることで、その分の税金は徴収しない、つまり回収不可能と判断されます。
そして、不納欠損は法律に基づき、きちんと適用される条件や期間が定められているため、むやみに使われる言葉ではありません。
こんな感じで、不納欠損とは税金が回収不可能と認められた状況のことだと覚えておきましょう。
執行停止とは何か?役割と不納欠損との違いを説明
「執行停止(しっこうていし)」も税金の徴収や行政の手続きでよく出てくる言葉です。
執行停止とは、税金などの強制徴収を一時的に止めることです。これは、法律に基づいて実施され、たとえば納税者が健康上の理由で体調が悪い場合や、災害で財産が一時的に差し押さえできない状況などがあげられます。
不納欠損が「もはや回収できない」という判断で徴収を終了するのに対し、執行停止は一時的に収める行為を止めるだけなので、状況が改善すればまた徴収が再開される可能性があります。
さらに執行停止は必ずしも「税金を払わなくてよくなる」わけではなく、ただ「今は徴収をやめましょう」という状態を示します。
この点で、不納欠損と執行停止は意味も扱いも大きく違うことを理解しておきましょう。
不納欠損と執行停止の違いを一覧でまとめてみた
ここまで説明した不納欠損と執行停止の違いをわかりやすく整理してみます。
| 項目 | 不納欠損 | 執行停止 |
|---|---|---|
| 意味 | 税金などを回収できず徴収終了 | 強制徴収を一時的に止める |
| 適用条件 | 破産、所在不明など回収が不可能な場合 | 災害、健康理由など一時的な事情がある場合 |
| 徴収の状態 | 徴収不能として終わる | 一時停止、再開の可能性あり |
| 納税者の負担 | 免除に近いと考えられる | 支払い義務は残る |
このように、不納欠損は徴収の終わり、執行停止は徴収の一時停止です。
税金や行政の現場でこれらの言葉が出てきたら、どの状態を指しているのかをよく考えましょう。
わかりにくい専門用語も、意味をしっかり理解するととても役立ちますよ。
「不納欠損」という言葉には興味深い背景があります。税金がどうしても回収できなくなると、不納欠損として処理されるのですが、これは国の財政にも影響します。特に大きな災害や経済危機が起きたとき、不納欠損が増えると国の税収が減り、公共サービスにも影響が出かねません。だから、ただの徴収不能ではなく、国にとっては重大な財政問題として考えられるんですよね。普段はなかなか意識しませんが、この言葉の裏には国の経済が絡んでいるんです。





















