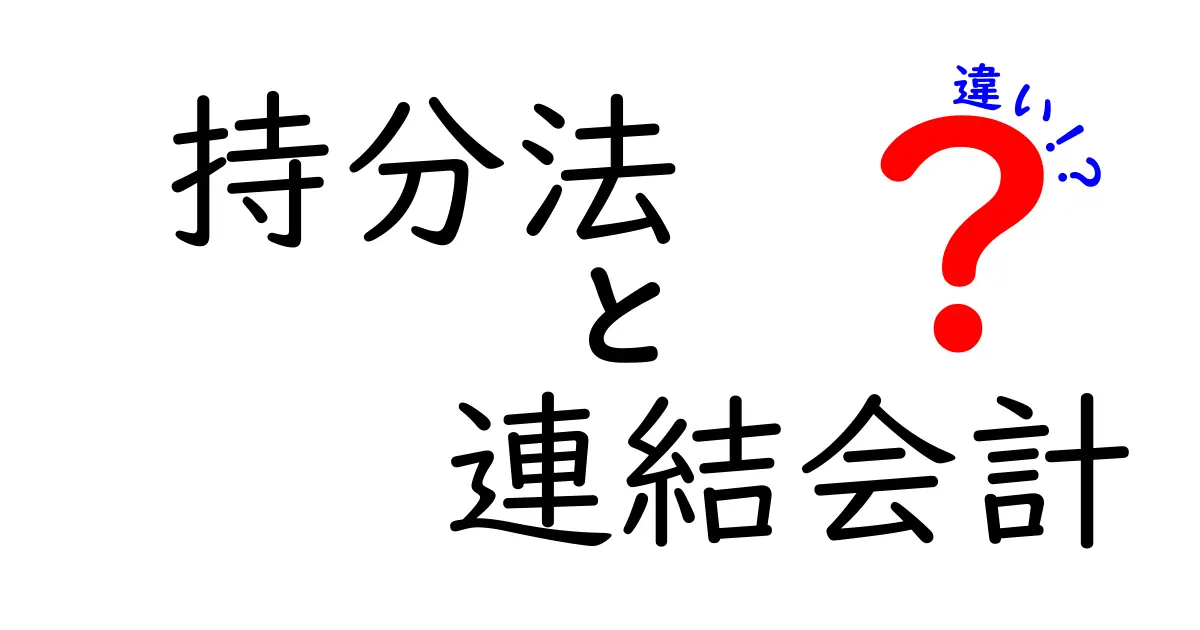

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
持分法と連結会計とは何か?基本の理解から始めよう
企業の財務報告を理解するうえで大切な会計手法として「持分法」と「連結会計」があります。
持分法は、投資先企業に対して実質的な影響力を持つ場合に用いられる方法です。通常、持分比率が20%以上50%未満の投資に使われます。
一方、連結会計は、親会社が子会社を支配している場合に両者の財務諸表をひとつにまとめて報告する手法です。支配とは、通常50%以上の株式を持つことで成立します。
これらは企業グループの財務状況を正確に表現するために重要なのです。
持分法と連結会計の違いを詳しく比較表で確認しよう
では、具体的にどのように違うのか、表で比べてみましょう。
| ポイント | 持分法 | 連結会計 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 持分割合20%~50%未満の関連会社 | 持分割合50%以上の子会社 |
| 報告の仕方 | 投資額を基に持分比率で収益や損失を反映 | 親会社と子会社の財務諸表を完全に合算 |
| 支配力の有無 | 実質的な影響力あり | 支配(コントロール)あり |
| 財務諸表の見え方 | 投資先の純資産増減が反映 | 細かい資産負債も合わせて報告 |
| 株式保有割合の基準 | 20%~50% | 50%以上 |
このように持分法は影響力のある関連会社を扱い、連結会計は支配している子会社を対象にする点が最も大きな違いです。
なぜ持分法と連結会計を使い分けるの?その理由と意義を理解しよう
持分法と連結会計は、企業の持つ影響力の度合いに応じて使い分けられます。
もし企業が完全に支配しているなら、親会社と子会社の財務諸表を合算してグループ全体の状況を明確にする必要があります。これが連結会計です。
しかし、50%未満の持分であっても企業に影響力がある場合は、投資先の利益や損失を持分比率に応じて反映する持分法が適切です。
つまり、どの程度コントロール可能か、企業の実態を正しく表すために、この二つが用いられているのです。
適切な会計方法の選択は投資家や取引先にとっても重要で、企業の実力を正確に知ることにつながります。
持分法の面白いポイントは、“影響力”の捉え方です。持分20%以上で影響力があるとされるのは、企業が株式割合だけでなく、取締役の派遣や重要な意思決定への参加など、多面的に関係を持つからです。例えば、20%ちょっとの持株でも取締役を送り込んでいるなら、実質的な経営参加が認められ持分法の対象になります。このように数字だけではなく実際の影響度で会計処理が変わるのは、ビジネスの多様性を上手く反映している面白さですね。





















