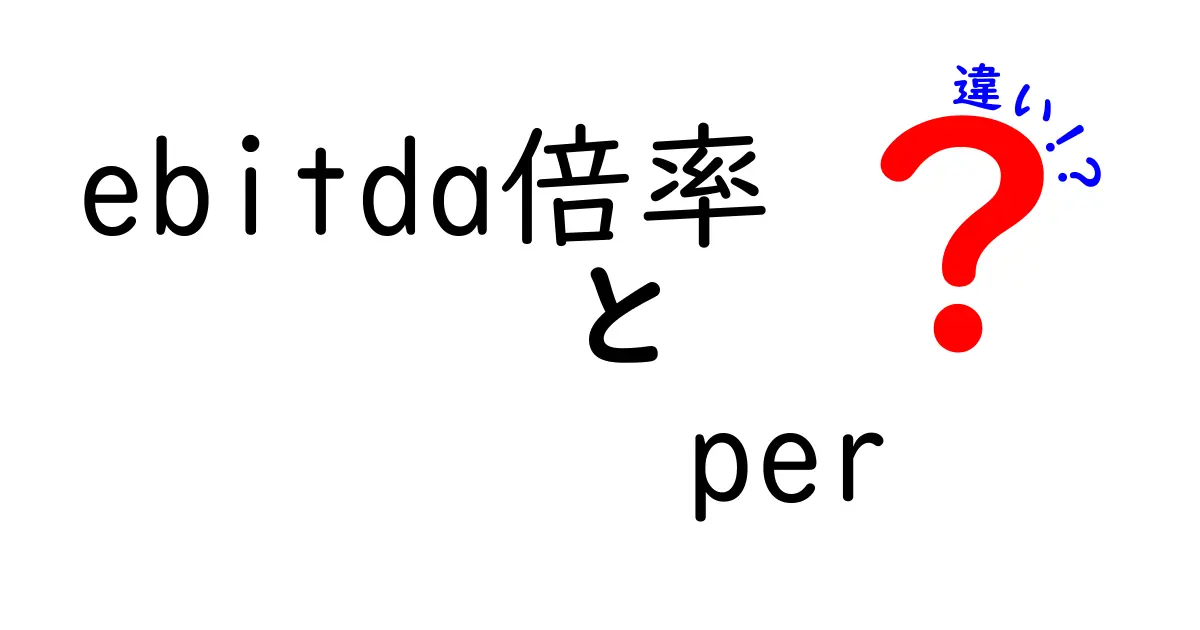

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
EBITDA倍率とPERの違いを理解する基礎
ビジネスの世界では、企業の価値を測る指標としてさまざまな計算方法が使われます。その中でも EBITDA倍率(EV/EBITDA)と PER(株価収益率)は、投資家やアナリストがよく参照する代表的な指標です。まずはこの二つの基本的な定義をしっかり押さえましょう。EBITDA倍率とは企業価値をその企業の稼ぐ力で割った指標で、一般には EV/EBITDA と呼ばれます。ここで EV は株式時価総額に負債を足し、現金を引いた値です。つまり“企業全体の価値”を“本業の稼ぐ力”で割るイメージです。計算を誤ると、似た名前の指標でも数字が全く違う結果になることがあるため、最初のうちは用語の意味と分母の意味をきちんと理解することが重要です。
PERとは株価を1株あたりの利益で割る指標です。具体的には株価 ÷ 1株当たりの純利益(EPS)で表されます。この指標は株式市場が現在の利益水準をどの程度評価しているかを示す直感的な数値ですが、税金の影響、会計方針、企業の資本構成などの影響を強く受けます。したがってPERだけを見て“この株は割安だ/割高だ”と判断してはいけない場合が多く、業界の平均値や企業の成長見通しと比較することが重要です。さらに、PERは一株あたりの純利益が安定していないと過度に変動することがある点にも注意が必要です。
二つの指標の最大の違いは“対象とするもの”と“分母の意味”です。EBITDA倍率は企業の本業がどれだけキャッシュを生み出せるか(利払い・税金・減価償却前の利益)を重視します。一方PERは株主が現在の価格を正味でどれだけの利益に対して払っているかを測る指標です。EBITDA倍率は資本構成の違いの影響をある程度吸収しやすく、設備投資の影響を織り込みながら比較しやすい特徴があります。これに対してPERは税制や減価償却、特殊要因の影響を受けやすく、同業他社と比較する際には同じ会計方針かつ同程度の成長性を持つ企業同士での比較が適しています。投資をする際には、これらの違いを理解したうえで複数の指標を組み合わせて判断することが基本です。
実務上の注意点として、EBITDA倍率は“非現金項目の排除”を前提としているため、減価償却や償却費用の多い業界では実態のキャッシュフローと乖離しやすい点を忘れてはいけません。またEVの計算には負債や現金の把握が不可欠であり、グループ内の子会社構成や資本市場の状況によって数値が変動します。PERは一株あたりの利益(EPS)の水準を基準にするため、会計上の利益をどう算定するかによっても数値が変わります。非繰延性の特別利益や税効果の違いもPERに影響を与えます。いずれにせよ“単一指標だけで投資判断を下さない”ことが最も重要な原則です。
使い分けのポイントとして、資本集約型の産業や、企業構造が複雑な場合にはEV/EBITDAを使って企業本来の稼ぐ力を比較するのが効果的です。一方で市場の評価や成長期待を直感的に知りたいときにはPERを参照します。ただし、実務では両者だけでなく、PBRやROE、FCFマージンなど他の指標と組み合わせて総合的に判断します。
比較する際には「同じ会計基準・同じ産業・同じ成長局面か」を前提にすることが重要です。
結局のところ、指標は道具であり、正しく使い分けるほど洞察が深まります。
計算のコツと現実的な使い分けの例
ここでは基本的な計算の要点と、現場での使い分けの簡単な例を紹介します。
1) EBITDAの計算: 営業利益に減価償却費を戻す。
2) EVの計算: 時価総額に負債を足し、現金を差し引く。
3) EBITDA倍率: EV ÷ EBITDA。
4) PERの計算: 株価 ÷ EPS。
実務例として、ある企業AのEVが2000、EBITDAが200、株価が100、EPSが10とします。EV/EBITDA = 2000 ÷ 200 = 10倍、PER = 100 ÷ 10 = 10倍となり、二つの指標が同じ水準に見えることがあります。しかし、同業他社の資本構成や会計方針が異なると、数値は大きく乖離することもあるため、必ず複数の指標で総合判断してください。
友達Aと放課後の図書室で、PERとEBITDA倍率の話をしてみたんだ。Aは“株価が高いのはいいことか悪いのか”と戸惑っていた。私はこう答えた。PERは株価が“今の利益に対して高いのか安いのか”を示す指標で、成長期待が大きい企業ほど低く出ることがある。しかし将来の成長を過大評価している場合もある。対してEBITDA倍率は“本業の稼ぐ力”を基準に企業全体の価値を評価する指標だ。負債や税金の影響を受けにくい一方、減価償却など非現金項目を除くため設備投資の負担を考慮しづらい。要は、PERは市場の心理、EV/EBITDAは現実の資産・負債の組み合わせを映す鏡だ。





















