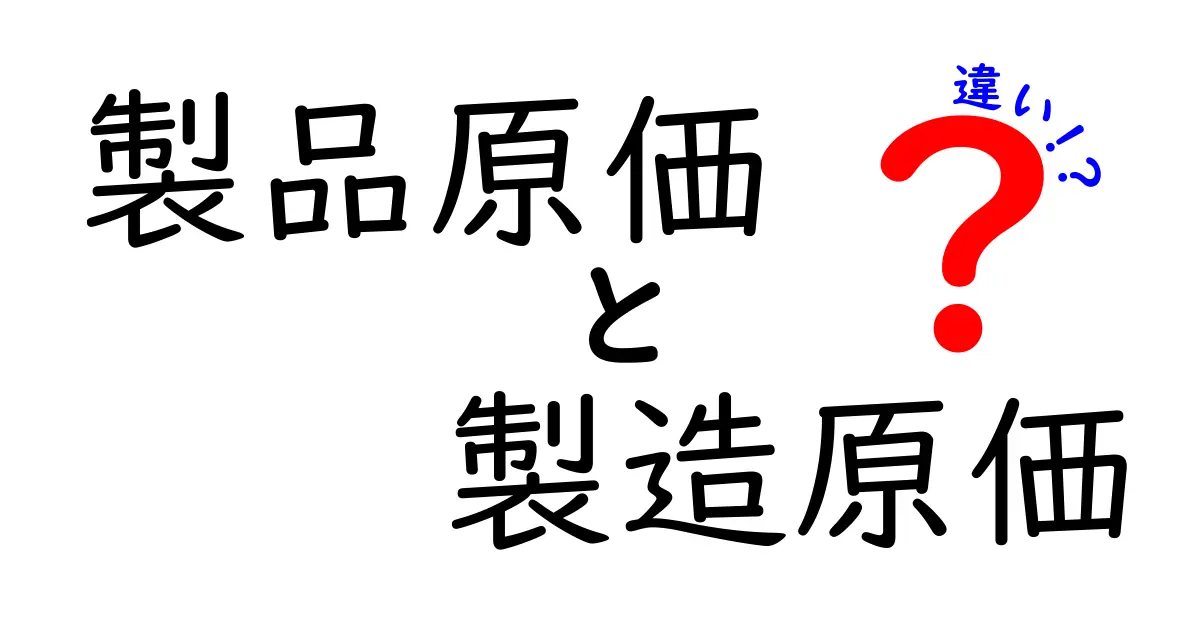

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
製品原価と製造原価とは?基本の意味を理解しよう
私たちが商品や製品を作るとき、かかるお金のことを「原価」と呼びます。
その中でも、「製品原価」と「製造原価」という言葉があります。この二つは似ていますが、意味がちょっと違います。
まずは、それぞれの基本的な意味を理解しましょう。
製品原価とは、ある商品が完成し販売できる状態になるまでにかかった全てのコストのことを指します。つまり、材料費や人件費、機械の使う費用などをすべて含んだ金額です。
一方で、製造原価は、製品を作るために直接使ったお金だけに注目します。これは主に材料費、直接労務費(働いた人の給料)、製造間接費(工場の光熱費など)が含まれます。
製造原価は「実際に物を作るための費用」に特化しているのです。
製品原価と製造原価の具体的な違い
では、この二つは具体的にどのように違うのでしょうか?
製品原価は、販売費や一般管理費など製品の販売や会社の運営にかかる費用も含むことがあります。つまり、製品が顧客の手に渡るまでにかかる全ての費用を合わせたイメージです。
これに対して、製造原価は工場で実際に製品を作る段階までの費用だけを指し、販売費や運営費は含みません。
以下の表で、それぞれに含まれる主な費用をまとめました。
| 費用の種類 | 製品原価 | 製造原価 |
|---|---|---|
| 材料費 | ○(原料も包装資材も含む) | ○(製造に直接必要な原料) |
| 直接労務費 | ○ | ○ |
| 製造間接費 | ○(工場の光熱費など) | ○ |
| 販売費 | ○(広告費・配送料など) | × |
| 一般管理費 | ○(管理部門の費用など) | × |
このように製造原価は製造に関する部分のコストだけを示し、製品原価はそこからさらに広がって販売や管理などのコストも含みます。
なぜ違いを知ることが重要?現場や会社での活用法
この違いを理解することは、会社の経営や働く人にとってとても重要です。
例えば、製造原価を正確に知ることで「一つの商品を作るためにどれだけの費用がかかっているか」がわかります。
これによって、効率の良い生産方法を見つけたり、無駄な費用を削減したりできます。
さらに、製品原価も知ることで、商品をいくらで売れば利益が出るかの判断がしやすくなります。販売費や管理費も含めて総合的にコストを管理するからです。
つまり、製造原価は生産の効率を考え、製品原価は会社全体の利益計画のために必要な数字というわけです。
経営者や工場の担当者が使い分けることで、会社全体の経営がよりよくなっていきます。
「製造原価」の中には、工場で直接使う材料費や働いた人の給料のほかに「製造間接費」というものがあります。これは、機械のメンテナンス費や工場の光熱費など、直接は見えにくいけれど必要な費用です。こうした間接費をちゃんと配分することで、一つの製品にかかった正確なコストがわかります。まるで商品の影に隠れたお金たちが、工場を支えているみたいですね。だから製造原価はただの数字じゃなくて、現場のリアルな努力や支えを映す鏡と言えます。
前の記事: « 卸価格と原価の違いとは?ビジネス初心者でもわかる解説
次の記事: 知らないと損する!生産高と製造原価の違いをわかりやすく解説 »





















