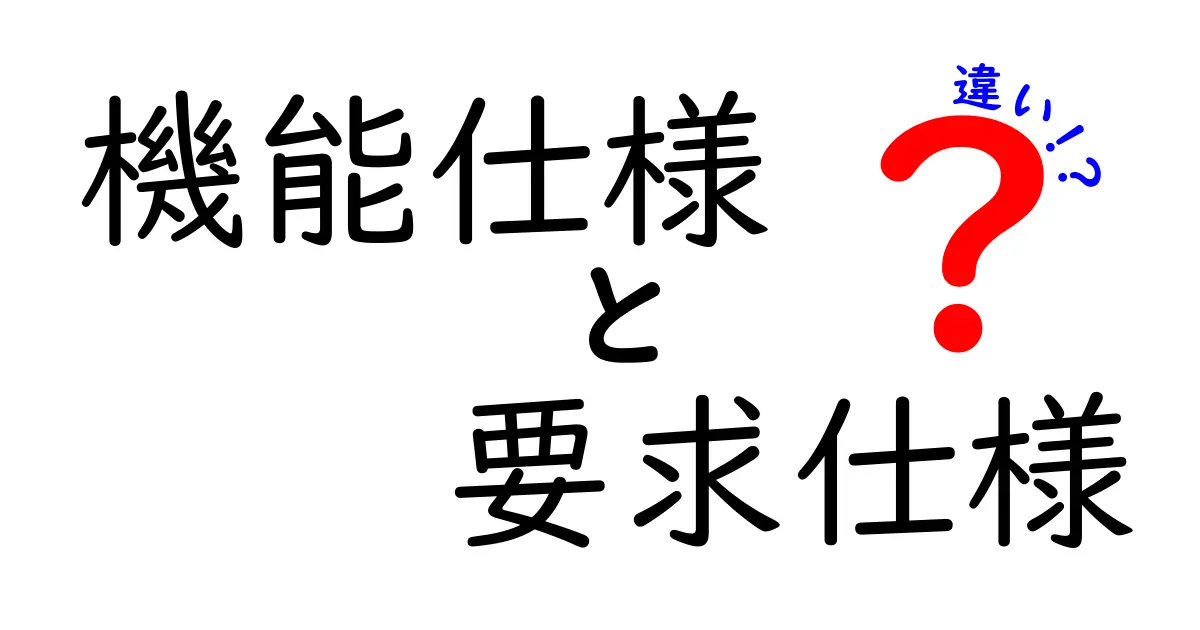

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
機能仕様と要求仕様の基本を押さえる
機能仕様はシステムが実際に何を成し遂げるかを具体的に定義します。例として会員登録機能を挙げると、登録ボタンを押した時に新規アカウントが作成され、ユーザーの名前とメールアドレスがデータベースへ保存されるといった「成果物の機能」を指します。
ここで重要なのは 機能仕様は利用者の視点と機能の成果物に焦点を当て、実装手段や技術的制約は含まないことです。
一方、求める仕様の土台となるのが要求仕様です。要求仕様は「誰が」「どういう条件で」「どの程度の品質で」機能を提供するべきかを示します。たとえば処理の正確さ、応答時間、信頼性、セキュリティといった非機能要件もここに含まれ、利用条件や制約、前提条件が具体的に記述されます。この二つは別々の文書として管理されますが、現場では相互に矛盾しないよう整合させることが大切です。
会員登録の例をさらに発展させると、機能仕様は「会員登録が完了したら success の画面を表示し、メール認証を要求する」という成果を示します。
要求仕様は「同時アクセスが最大500件まで耐える」「登録処理は2秒以内に完了する」「個人情報は批准された暗号化で保存する」「GDPRや国内法に適合する」といった条件を示します。
このように機能仕様と要求仕様は役割が異なりますが、現場では一つの要件が別の文書の一部と見なされることが多く、混同すると開発が止まる原因になります。明確な区分と継続的な整合性チェックが成功の鍵です。
友人と雑談をしていたときの話です。私は機能仕様と要求仕様の違いが頭の中でごちゃごちゃしていたので、友人にわかりやすく説明してもらいました。友人はこう言いました。機能仕様は作るもの自体の性質を決める地図のようなもの、要求仕様はその地図を現実の道路状況に合わせて動かすルール集だと。つまり機能仕様が何を作るかを示すのに対して、要求仕様はその作業がどの条件で正しく行われるべきかを定めるのです。私たちはこの二つを混同しないよう、まず機能仕様で目的を固め、次に要求仕様で品質や制約を明示します。話を整理すると、開発が進むにつれてどちらが変更されても全体の整合性を崩さないよう、段階的に見直す習慣が重要だと分かりました。これからは会員登録の例を思い出しつつ、機能と要件の境界を意識して設計していきたいです。これが雑談の中で私が得た大事な気づきです。





















