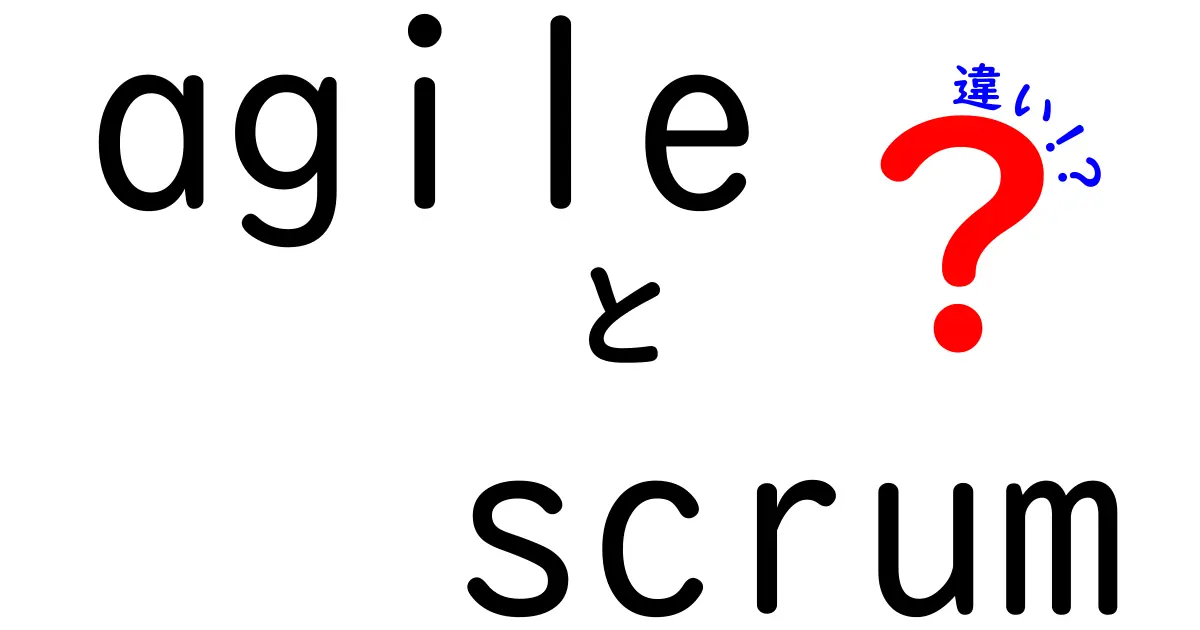

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
agileとscrumの基本概念と違いを整理する
アジャイルという言葉は元々の意味が「柔軟に対応する」という考え方を指します。
つまり、変化を前提に計画を立て、短い周期で成果を出していくという開発の考え方全体を指すフレームワークの集合体です。
一方、スクラムはそのアジャイルの中の実践的な方法のひとつで、具体的な役割やイベント、成果物の作成方法を「形」に落とした枠組みです。
この違いを端的に言えば、アジャイルは“思想や原則”で、スクラムは“具体的なやり方”です。
この違いを理解することは、現場での導入や切り替え際にとても重要です。
アジャイルは組織全体の文化や価値観を変えることを促しますが、スクラムはその考え方を現実のプロジェクトに落とすための“実務の設計図”として機能します。
では、なぜこの区別が現場で大切なのでしょうか。
第一に、名前だけ取り入れてしまうと、開発サイクルの長さやミーティングの頻度、役割の責任範囲が適切に設計されず、混乱が生まれやすくなります。
第二に、アジャイルの価値観を理解せずにスクラムの儀式だけを真似すると、実際には顧客価値の創出が遅れてしまいます。
第三に、組織が「変化を許容する風土」を作れていないと、スクラムのイベントはただの会議になってしまいます。
このような失敗を避けるには、まず“何を重視するのか”を明確にし、次に“どの程度の頻度で何を成果として出すのか”を設計することが大切です。
具体的には、短期間での検証と学習を繰り返すサイクルを作り、成果物を透明に可視化することがポイントとなります。
この章の要点は、アジャイルの思想とスクラムの実践を別々のレイヤーとして理解することです。
アジャイルの核心は「変化を歓迎し、顧客価値を最優先にする」こと。
そしてスクラムの核は「短いスプリントで成果を連続的に積み上げ、透明性を高める」ことです。
この二つを組み合わせることで、現場は変化に強いプロジェクト運営を実現します。
ただし、実務では組織規模やプロジェクトの性質、チームの成熟度によって最適解は異なります。
そのため、導入時には小さな実験を重ね、失敗を学習として活かす姿勢が大切です。
この表を見れば、両者の位置づけは明確に異なることが分かります。
アジャイルは道具箱全体の考え方、スクラムはその中の実際の使い方です。
最終的には“何を作るか”と“どのように作るか”の両方を整えることが重要で、両者を組み合わせることで顧客のニーズに迅速に応える力が高まります。
次章では、現場での使い分け方と導入時の注意点を具体的な事例とともに紹介します。
現場での使い分け方と実務のコツ
実務で agile と scrum を使い分けるとき、よくある誤解は「どちらか一方をすべて取り入れればいい」という考えです。しかし、実務では「状況に応じて選択と組み合わせを最適化する」ことが成功の鍵になります。
まず前提として、組織の成熟度を測る指標を設定します。例えば、顧客価値を測る指標、開発の透明性を示す指標、変更対応の速度を測る指標などを明文化します。
次に、スクラムを導入する場合は、役割やイベントを最適化します。プロダクトオーナーがビジョンと優先順位を強く握り、スクラムマスターが障害を取り除き、開発チームが自律的に機能する仕組みを作ります。
アジャイルの思想を現場に落とすには、“短いサイクルで価値を出す”という基本を徹底することが肝心です。スプリントの長さは1~4週間程度が目安となり、初期は短く設定して適応を促します。
また、日常のミーティングは目的を明確にし、無駄な会議を減らす工夫をしましょう。例えば、デイリースクラムでの質問を「何を達成したか」「次に何をするか」「障害は何か」この3点に絞ると、情報の流れがスムーズになります。
チームの心理的安全性を高めることも重要です。誰もが意見を言いやすい雰囲気を作り、失敗を責めずに学習の機会として扱う文化を育てましょう。
最後に、外部のフレームワークに頼りすぎず、組織の現実に合わせた“カスタム版スクラム”を作る柔軟性を持つことが成功のコツです。
この章のまとめは、現場の状況に応じてアジャイルとスクラムの要素を組み合わせ、明確な成果と透明性を両立させることです。
適切なバランスを保つことで、変化の激しい時代にも強い開発体制を築けます。
友達と雑談している雰囲気で話すと、スクラムは“作業を固めるための設計図”みたいなもの、アジャイルは“設計図そのものを作り変える心構え”みたいな感じだね。例えば、君が部活の大会に向けて練習計画を立てるとき、スクラムは「誰が何をいつまでにやるか」を具体的に決める表、アジャイルは「大会を成功させるためにどうチーム全体の動きを柔軟に変えるか」という全体の考え方だと思う。つまり、スクラムは道具箱の中の道具の一つ、アジャイルは道具箱そのもの。現場で使うときは、道具を増やすのではなく、どう組み合わせて最適化するかを考えるのがいいよ。ポイントは、変化を恐れず、失敗を学習の機会として活かす姿勢を忘れないこと。





















