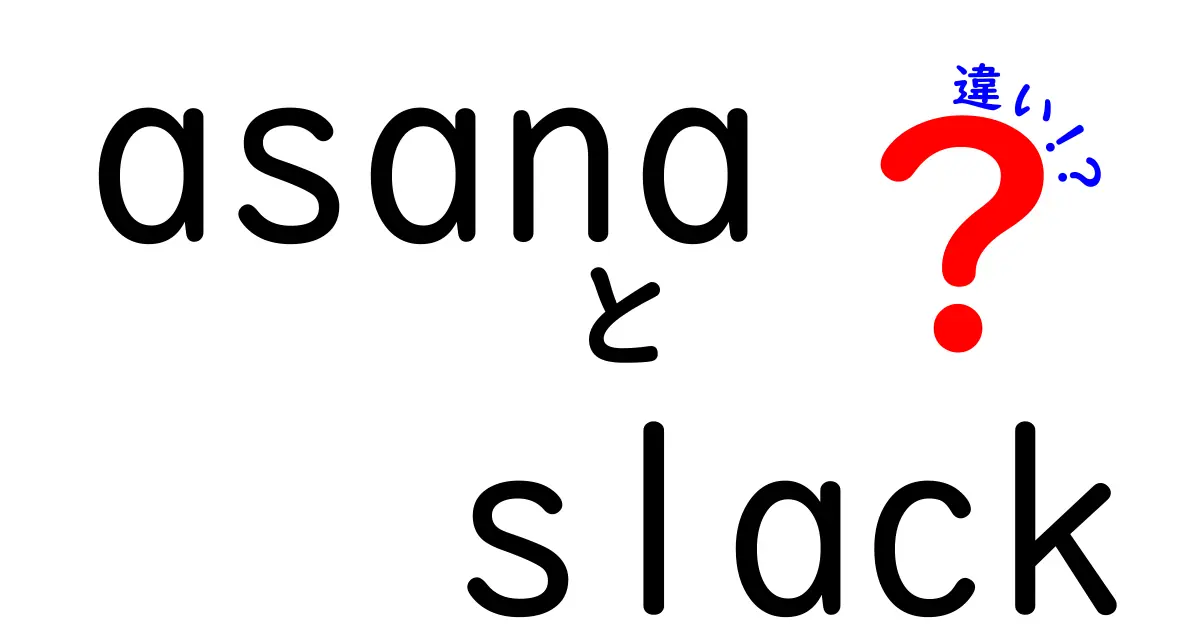

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
asanaとSlackの違いを正しく理解するための基本ガイド
最初に大事なこととして、asanaとSlackは同じようにチームの作業を助けるツールですが、役割が違います。asanaはタスクやプロジェクトを整理するための道具で、個々の作業を誰が担当して、いつまでに終わらせるかを明確にします。Slackは主にコミュニケーションを円滑にするための道具で、話題を整理したり、情報を素早く共有したりする場を提供します。もちろん連携機能もあり、Slackのチャンネルで話題になっているタスクをAsanaと連携して表示したり、反対にAsanaの作業更新をSlackに通知したりできます。つまり、asanaとSlackは同じ目的の大きなグループに属しますが、実際の“使い道”は分業されているという点が大きな違いです。
この違いを押さえずに使い始めると、毎日のルーティンでの作業が混乱しやすくなります。例えば、会議後に出た決定をすぐに誰がどう進めるかを把握できず、タスクの見落としが発生することがあります。そのため、初期設定では「何をasanaで管理して、何をSlackで共有するか」を明確なルールとして決めておくことが大切です。
以下では、機能の根本的な違い、実務での使い分けのコツ、そして両ツールを連携させる具体的な場面について、優しく解説します。
機能の根本的な違いと使い方のコツ
ここでもう少し細かく、どんな場面でどちらを使うべきかを見ていきます。asanaはタスクの状態管理、期限、担当者、依存関係、テンプレート化、進捗の可視化などを中心に設計されています。タスクを階層的に整理して、複数のサブタスクに分解し、ガントチャート的な見方で全体像を把握することができます。また、プロジェクトごとにカスタムフィールドを設定して、重要度や進捗を数値で追跡することも可能です。これにより、個々の作業がどこで詰まりやすいか、どのタスクが遅れているかをすぐに把握できます。Slackは一方で、日常的なコミュニケーション、意思決定のプロセス、情報共有を速く行うために設計されています。スレッド機能を使って話題ごとに会話を整理し、ファイルの共有、通知の設定、ボットによる自動化などを活用して、日常のやりとりをスムーズに保つ役割を果たします。
もう一点のポイントは連携です。AsanaとSlackはお互いを補完する形で使うと、作業の抜け漏れを減らせます。例えば、Slackで新しいタスクの発生を知らせ、Asanaでそのタスクを割り当て・期限設定・進捗更新を管理する、という流れです。反対に、Asanaで大きなマイルストーンが近づいたときにSlackで通知を受け取り、チーム全体の合意形成を速める、という使い方も有効です。ここまでの理解を基に、次の章で実務での使い分けのポイントを整理します。
- 使い分けの基本原理: まずは「何を管理するのか」を明確化し、Asanaはタスク・プロジェクト、Slackは会話・通知の中心とする。
- 通知の設定: Asanaの更新通知は進捗把握に、Slackの通知は緊急度の高い話題の共有に向く。
- 連携の活用法: 両方を連携させ、情報の流れを2系統で管理することで抜け漏れを防ぐ。
このような基本を押さえれば、日々の業務での混乱を減らし、効率よく進められます。実際の運用例としては、週次ミーティングで決まったタスクをAsanaに作成し、Slackでの質問を即時に受け付ける、などが挙げられます。これらを繰り返すうちに、チーム全体の生産性が少しずつ高まっていくのを実感できるでしょう。 最終的には、個人の作業習慣と組織のワークフローに合わせた最適化が鍵です。
ね、さっきの話題、通知の話だけど、私は日々の業務でこの仕組みを実体験として感じています。Asanaの更新通知は『誰が何をいつまでにするのか』を思い出させてくれるので、締切直前に慌てることが減りました。一方Slackの通知は会話の流れを止めずに質問を投げられるので、進捗に関する疑問がすぐ解決します。私の観察としては、通知を同じくらいの頻度で受け取り、適切なタイミングでフィードバックを返すと、タスクの遅延と会議の長さを両方とも小さくできるという感触があります。結局のところ、通知は情報の“速度と質”を決める要なので、設定を適度にカスタマイズすることが大事です。





















