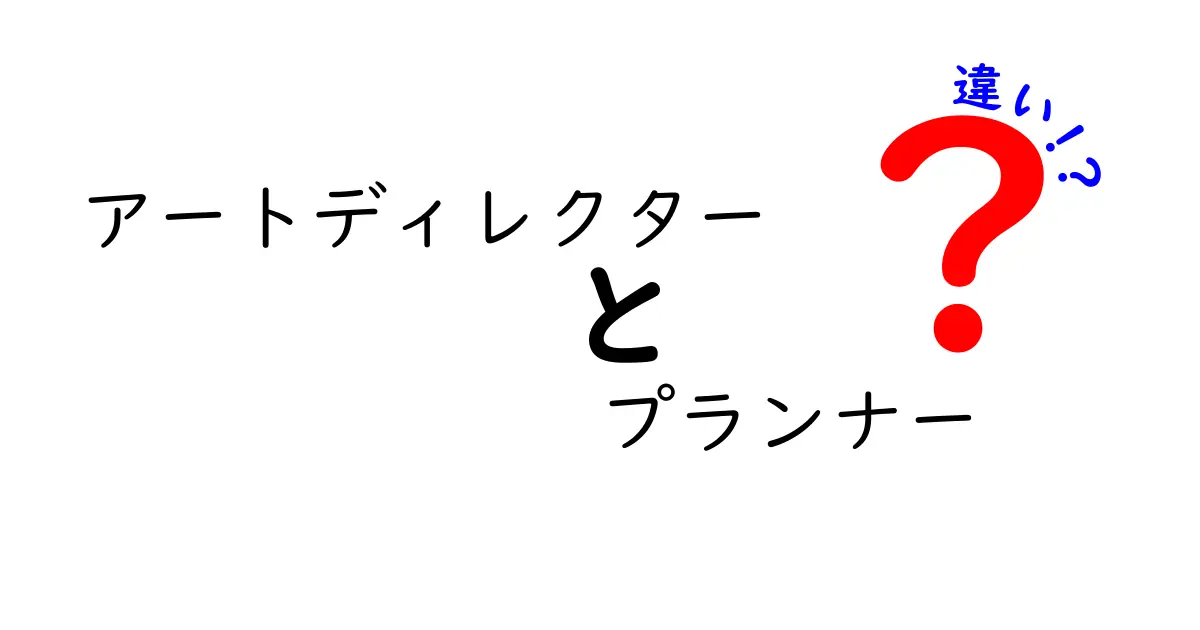

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アートディレクターとプランナーの基本的な違いを一言で理解する
アートディレクターは、作品全体の視覚的な方向性を決める「創造の船長」です。色の組み合わせ、フォント選び、写真のトーン、レイアウトのルールなど、見た目の統一感を作る責任があります。クライアントの要望を受け取り、それを具体的なビジュアル案へと翻訳し、デザイナーやフォトグラファーと協力して、ブランドの個性を壊さずに伝えることが求められます。対してプランナーは、「戦略と計画」を描く人です。市場やターゲットの分析、ユーザーの行動の予測、どのチャネルでどう伝えるか、納期や予算の管理など、成果を出すための現実的な土台づくりを担当します。ここでのキーポイントは、創造と戦略の二つの世界を橋渡しすること、そして誰が最終的な出力の責任者かという視点です。現場では、アートディレクターが最終的なデザインの美しさと一貫性を判断します。一方でプランナーは、施策の仮説を検証する指標を設定し、次の改善案を導く責任を持っています。こうした二人の役割が互いに尊重され、明確なコミュニケーションが取れて初めて、クオリティの高い成果が生まれるのです。
この先のセクションで、実際の作業フローや具体例を見ていきましょう。
アートディレクターとプランナーの役割の違いと日常の作業フロー
日常の作業フローは、まず「ブリーフを理解する」段階から始まります。アートディレクターは、ブランドのトーンやデザインの方向性を掘り下げ、ビジュアルの仮説を立てます。
そしてデザイン部隊と連携して、ムードボード、カラーガイド、タイポグラフィのルールを作成します。ここでの成果物は主にビジュアルの試案やデザイン仕様であり、完成形の美しさを追求します。反対にプランナーは、市場データの収集と分析を行い、ターゲットのニーズを明確にします。
ユーザーの行動フローを描き、どのコンテンツが最も効果的か、どのタッチポイントでエンゲージメントを高めるべきかを設計します。納期と予算のバランスを取りながら、施策全体のロードマップを作成します。
この二つは別々の仕事はもちろん、実際には密接に関係しています。アートディレクターが作るビジュアルが前提となり、プランナーがそのビジュアルをどう見せるか、どのストーリーで伝えるかを決定します。日常の会議では、要望の優先順位をつけ、段階的な成果物のスケジュールを組み、関係者全員に共通理解を持たせることが肝心です。
特に注意したいのは、「変更の許容範囲」と「ブランドの一貫性」です。変化を恐れず、しかし一貫性のある表現を保つことが長期的な信頼感につながります。最後に、チームの中でのコミュニケーションがスムーズであれば、デザインと戦略がいつも最適に結びつき、クライアントの期待に応える品質が確保されます。
具体的な作業の比較と事例
以下の表は、主な作業項目をアートディレクターとプランナーで比較したものです。現場では、両者が連携してチームを動かします。デザインの方向性を決めるのがアートディレクター、施策の検証と改善を進めるのがプランナーです。
実際のケースでは、例えば新商品キャンペーンを考える場合、プランナーが市場データとターゲット像を作成し、アートディレクターがそれを魅力的なビジュアルストーリーに落とします。デザインが完成したら、プランナーはA/Bテストの設計を行い、反応データを分析します。ここで「どの要素が効果的だったか」を判断するのはプランナーですが、効果が低い場合にはアートディレクターと共に別案を作成します。最終的には、両者の意見を統合して、ブランドの一貫性を保ちながら、創造的な表現と実用的な施策を両立させることが求められます。
実務での連携のコツ
現場での連携を円滑にするためには、まず「言葉のすり合わせ」を徹底します。似た意味の言葉でも解釈が違うと、会議の時間を浪費します。次に、成果物のアップデートの頻度を決め、脚色しすぎない正確な情報共有を徹底します。
また、デザインと戦略の両方の観点からフィードバックを受け入れ、変更がブランドの一貫性を崩さない範囲で迅速に適用する力が大切です。最後に、学習を継続する姿勢を忘れず、デザインの原理とマーケティングの基本を日常的に学ぶ習慣を持つと、二人の協働はさらに強固になります。
まとめのポイント: アートディレクターは見た目の品質を担い、プランナーは使われ方の品質を担う。両者が互いに尊重し、明確な役割分担とコミュニケーションを通じて、価値ある成果物を生み出す。現場での連携のコツを実践していくことが、現代のクリエイティブ組織の成長につながります。
ねえ、アートディレクターとプランナーの違いって、実は日常の現場でこっそり形になっていくんだ。例えば広告の企画会議で、デザイナーがいい絵を描くのはアートディレクターの仕事で、絵の良さをどう市場に伝えるかを決めるのがプランナー。僕が現場で感じるのは、二人は別々の言語を話しているけれど、共通のゴールである“人に伝わる価値を作る”ところで必ず交わる、ということ。創造と分析を同時に回す力こそが、現代のクリエイティブの要だと思う。





















