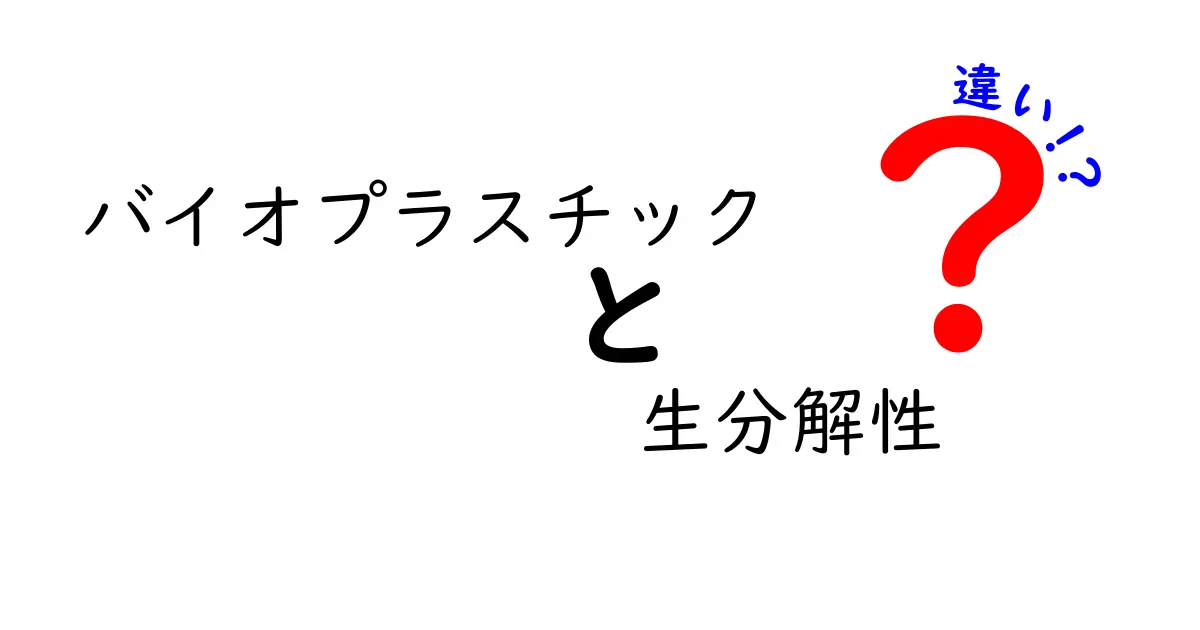

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
バイオプラスチックとは何かと生分解性の違いを正しく理解する
バイオプラスチックとは、植物由来の原料を使って作られるプラスチックの総称です。一般的には、トウモロコシのデンプン、サトウキビ、あるいは植物由来の糖を原料とするポリマーを指します。ここで大切なのは、生分解性などの性質と、バイオベースの根拠は別物であること。つまり、bio-based かつ biodegradable なものもあれば、bio-based であっても「分解されにくい」もの、または fossil-based であっても「分解する」ものがある。市販されている代表的な例としては、植物デンプンを使った糊化系の素材、リグロス樹脂を使った材料、または微生物の働きで分解されやすいポリ乳酸(PLA)などが挙げられます。
このように、バイオプラスチックには特性の組み合わせが複数あり、作られ方や実際の扱い方で差が生まれます。
以下のポイントを押さえると、混乱せずに理解できます。
1) 生分解性は条件依存性である。工業用の堆肥設備や海水、土壌中、さらには温度・湿度・微生物の種類によって分解の進み方は大きく変わります。
2) Biobased = 自然由来であることと、Biodegradable = 実際に分解することは別物。「植物由来だからすぐに自然に分解する」と考えると誤解のもとです。
3) 表示を読む力が大切です。パッケージには「生分解性」「堆肥化適合」「海洋環境生分解性」などの表現が並ぶことがあり、それぞれ分解条件が異なります。
4) 分別とリサイクルの正しい理解。生分解性素材を普通のプラスチックごみといっしょに燃やしてしまうと、リサイクルの質が下がったり、設備を傷めたりすることがあります。
生分解性の実際と注意点
生分解性の基本は「微生物が有機物を分解して無機物・水・エネルギーを得る過程」と同義です。しかし材料ごとに必要な条件が異なり、海中や家庭の土壌、産業用の堆肥施設での分解速度は大きく違います。
この違いを理解しておくと、エコの選択を誤らなくなります。例えば、PLAは工業用堆肥条件下で分解しますが、通常の家庭のゴミ処理や海洋環境では長期間残ることがあります。
また、生分解性という表示がある素材でも、土の中で完全に消えるまでの時間は数ヶ月から数年、条件によってはほとんど分解されないこともあります。
このような事情を考慮して、製品の使い道や廃棄方法を選ぶことが大切です。
以下は覚えておくべき要点です。
・ 素材ごとに分解条件が異なる(工業堆肥・家庭堆肥・海洋など、条件が変わると分解速度が変わります)。
・ ラベルの表現を鵜呑みにしない(「生分解性」「堆肥化適合」などの表現だけで分解を判断しない)。
・ ゴミの分別は丁寧に(混ぜてしまうとリサイクルや適切な処理が難しくなることがあります)。
まとめとして、エコ素材を選ぶ際には「どの条件で分解されるのか」「実際の廃棄方法はどうなのか」を確認する習慣をつけましょう。
今日は友達とカフェでエコ談義。彼女が『生分解性って自然に全部壊れるわけじゃないよね』と言い、僕は『そう、それぞれの条件が大事。あくまで特定の条件下での話なんだ』と答えた。結局、身近な消費者としては、パッケージの表示を読み、適切な廃棄方法を選ぶことが地球を守る第一歩になる。





















