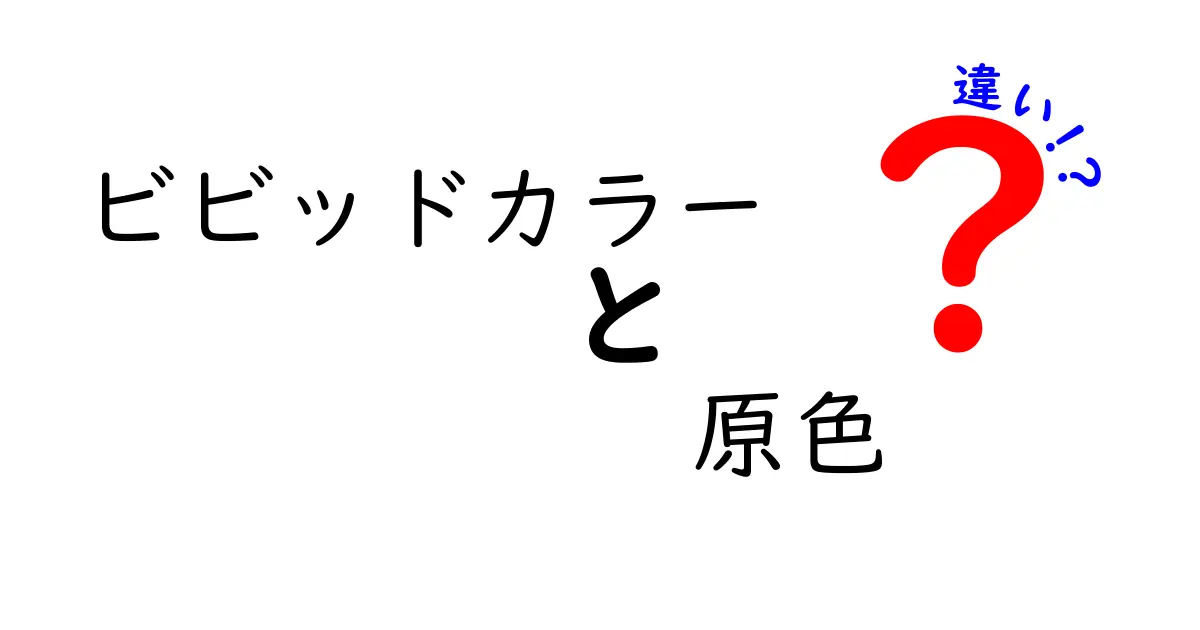

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ビビッドカラーと原色の違いを理解してデザイン力を上げよう
このページではビビッドカラーと原色の違いを、デザインや日常の色選びに役立つ形でわかりやすく解説します。まず大切なのは、色そのものの性質と人が見る印象が別物だという点です。ビビッドカラーは視覚的に強い刺激を与える色で、ポスターや広告、SNSのアイキャッチなど、注目を集めたい場面で活躍します。これに対して原色は色の“基盤”になる色の集合であり、三原色や五原色といった基本的な色の組み合わせを指すことが多いです。
デジタルの世界では光の三原色であるRGBが、筆や絵の具の世界では減法混色の色体系であるCMYが、それぞれ色の作られ方の出発点となります。これらの違いを知ることで、作品全体の雰囲気づくりがぐっと安定します。
例えば、写真の被写体を際立たせたいときにはビビッドカラーを使い、背景は原色の中の一色をポイントとして選ぶとまとまりが生まれやすくなります。こうして適切な場面に適切な色を配置する力を身につけることが、デザイン力の第一歩です。
また色の組み合わせを学ぶと、見慣れた風景や日常のファッション、インテリアなどにも新鮮さを加えられます。原色を理解しておくと、どの色を混ぜるとどう見えるかを予想でき、失敗を減らすことができます。
この章では原色の基本を押さえたうえで、ビビッドカラーの特徴と使い方、そして実際の場面でどう組み合わせるのがよいかを、段階的に紹介します。
原色とは?基本的な定義と三原色・五原色の違い
原色とは、色作りの出発点となる最も基本的な色のことを指します。歴史的には赤・青・黄の三原色が伝統的な原色として教えられてきました。三原色は、絵具や印刷の世界で新しい色を作り出すための“元になる色”であり、混ぜると他の色が生まれます。三原色は、絵を描くときやプリントの設計で特に重要です。現代の色モデルには光の色を扱うRGBと、物質の色を扱うCMYの二つの考え方があります。RGBでは赤・緑・青を組み合わせると白に近づくのが特徴で、光の世界の色の作り方です。一方CMYはシアン・マゼンタ・イエローを主に混ぜ合わせる考え方で、物体の表面に反射する光を減らして色を作る仕組みです。
さらに五原色という考え方もあり、赤・黄・青以外に緑や紫などを加える分類です。五原色は学習現場で色の混ぜ方を体感する教材として使われることがあります。
原色を知ることは、他の色を作る“出発点”を押さえることにもつながります。原色を基準にして、混色の結果としてどんな色が生まれるかを予想できると、デザインの初期設計がスムーズになります。
このセクションでは原色の基本を整理しつつ、三原色と五原色の違いを具体例とともに分かりやすく説明します。
ビビッドカラーの特徴と使い方
ビビッドカラーとは、基本的に彩度が高く、明度が高いものや高い印象を与える色のことを指します。デザインの現場では、見出しやボタン、重要なポイントを強調するときに効果的に使われます。ビビッドカラーの良さは、視線を引く力と情感の強さにありますが、使い方を間違えると情報の読みづらさや目の疲れにつながることもあるため、注意が必要です。
使い方のコツとしては、背景の色を落ち着かせる強い色の対比を作ること、そして一つの画面にビビッドカラーを多く配置しすぎず、主役と脇役をはっきり分けることが挙げられます。日常の例では、ニュースサイトのヘッドライン、ファッションのアクセント、商品パッケージの訴求点などでビビッドカラーを適切に使うと、伝えたい情報が伝わりやすくなります。
また光の影響にも気をつけましょう。室内の照明の色温度が暖色系だとビビッドカラーの印象がわずかに変わる場合があります。こうした点を踏まえ、光と背景との関係を考慮した色選びを心掛けると、デザイン全体の cohesiveness が高まります。結局、ビビッドカラーは強い印象を作る道具です。原色の性質をしっかり理解したうえで、適切な場面に配置することが重要です。
実際のカラーサンプルと比較
ここでは代表的な色の組み合わせを例に取り、原色とビビッドカラーの実際の見え方の違いを想像してみましょう。原色の赤は強いエネルギーを持ち、彩度の高いビビッドな赤はさらに鮮やかで刺激的です。青系の原色は落ち着きと信頼感を与えやすく、緑系は自然や健康、安らぎの印象を強くします。黄は元気さと注意喚起の強い色で、警告や重要情報の際に有効に働きます。これらの色を組み合わせるときは、強すぎる対比を避け、文字の読みやすさを最優先に考えましょう。
実際のデザインでは、まず背景色を落ち着かせ、次に焦点となる要素をビビッドカラーで強調するのが基本的な流れです。ポスターやウェブのヒーロー画像、パンフレットの見出しなど、目的に合わせて色の重心を調整するのがコツです。最後に、実務では印刷とデジタルの両方で色がどのように再現されるかを確認することが不可欠です。色見本とデータを比較しながら、最適な組み合わせを見つけ出す作業がデザイナーの腕の見せどころになります。
原色の話題を友だちと雑談している感じで話してみるね。原色って“これが基本の色だよ”っていう出発点なんだけど、実際には使い道がぜんぜん違うんだよね。僕が好きなのはこの感覚。原色を知っておくと、何色と何色を混ぜたらどう見えるかを直感的に予想できるようになる。たとえば赤と黄を混ぜるとオレンジ、青と黄を混ぜると緑……っていう基本の公式を覚えておくと、デザインの会議で“この色どうかな?”と提案しても、すぐに色のイメージを伝えられる。そうすると、会議がスムーズに進むんだ。もちろん実際には印刷の色味や光の影響もあるから、色見本を見ながら微調整するのが楽しい作業。原色を軸にして、ビビッドカラーをどう使うかを考えると、作品の印象がぐっと鮮やかになるんだよ。





















