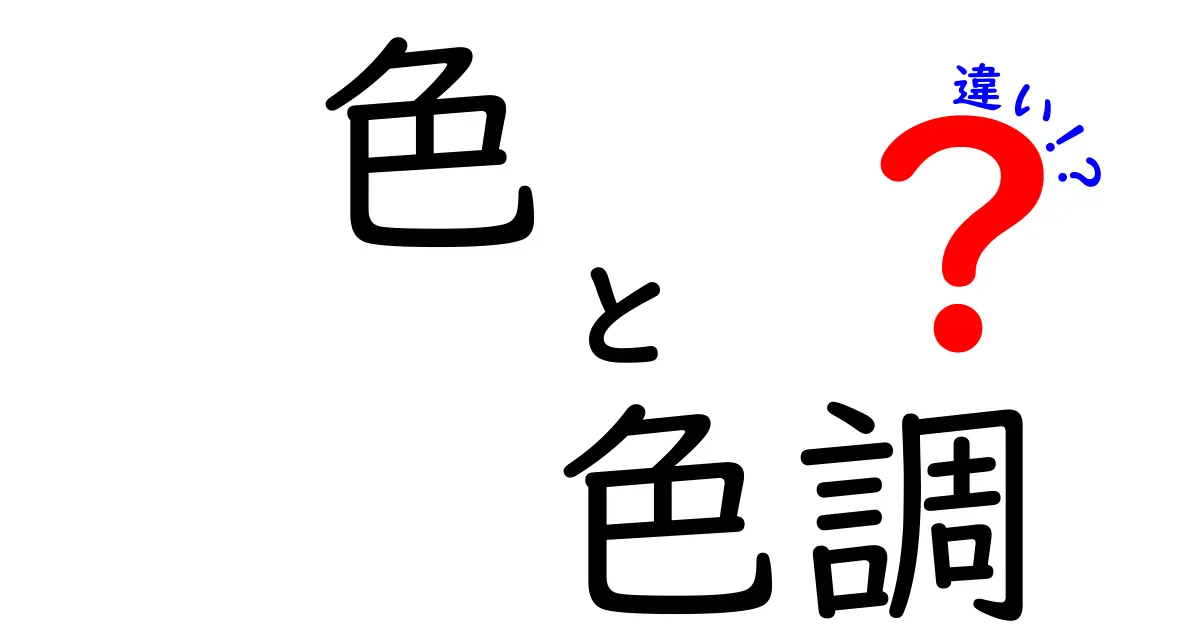

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
色と色調の違いを知るための基礎
人の目には同じ「色」を見ても、感じ方は人それぞれですが、色そのものと色の感じ方を分けて考えると、場面ごとの工夫がしやすくなります。まずは基本の違いを整理しましょう。
色とは光の波長と物体表面の性質によって決まる性質です。肉眼では波長が約380〜750ナノメートルの範囲で私たちに見える色として感じ取られます。日常の会話では“赤”や“青”といった名称がつくのは、脳がその波長の組み合わせを分かりやすく覚えているからです。媒体が違えば色の再現にも差が出ます。例えば印刷とスマホ画面では同じ赤を見ても微妙に違って見えることがあります。これは、紙の白さ・周囲の色・光源の色温度などが影響しているためです。こうした要素を踏まえて、デザインや写真を学ぶときには、色を選ぶだけでなく“どの媒体でどう見えるか”を想定することが大切です。
色の基本概念
色の基本は大きく三つの要素に分けて考えると分かりやすいです。第一は色相、つまり色そのものの名前です。赤・青・緑などが色相です。第二は明度、色の明るさを表します。白に近づくほど明るく、黒に近づくほど暗くなります。第三は彩度、色の鮮やかさ、どれだけ“強い色に見えるか”を表します。これらの組み合わせによって、同じ赤でもくすんだ赤、鮮やかな赤、オレンジ寄りの赤など、いろんな印象が作れます。日常生活でこれらを意識すると、服のコーディネート、部屋の雰囲気、写真の仕上がりが安定してきます。例えば同じ赤でも、太陽光の下ではより温かく見え、LEDの青白い光の下では冷たく見えることがあります。色相環の基本を覚えるだけで、配色の幅が広がります。
色の基本を理解しておくと、授業の発表用スライドも、友達へのプレゼント選びも、なんとなくの印象ではなく根拠を持って選べるようになります。
色調の基本概念
色調は、色そのものの名前に加えて、画面や印刷で見える“雰囲気”を表す言葉です。主な三要素は明度、彩度、色味です。明度は明るさ、彩度は鮮やかさ、色味は黄色み・緑み・青みといった色の傾向です。色調を調整することで、同じ色でも季節感や感情を演出できます。季節の写真では、暖色系の色調を使えば温かさを、寒色系の色調を使えば落ち着きを出せます。肌色の表現でも、色調を工夫することで健康的に見せたり、落ち着いた印象を作ったりできます。デザインの現場では、ベースの色を選んだ後、全体の統一感を作るために色調をそろえる技術がとても大切です。
色調の理解は、あなたの作品に“個性と伝わりやすさ”を同時に付ける道具になります。
友達と放課後に色の話をしました。彼は『色調って結局どう違うの?』と聞き、私は『色は“その色そのもの”を指す名詞、色調はその色の感じ方や雰囲気を指す名詞だよ』と答えました。僕たちはスマホの写真を見せ合い、同じ赤い背景でも写真アプリの設定で雰囲気がガラリと変わることを経験的に確認しました。明るさを上げると元気に見え、彩度を落とすと落ち着いた印象になる。色温度が暖色系なら温かい、寒色系なら涼しげ。こんな小さな違いが、デザインの印象を決めるのだと納得しました。色の話は難しく感じるかもしれませんが、身の回りの写真や服選び、部屋の模様替えに活かせる“道具”になるはずです。
次の記事: 化粧箱と外箱の違いを徹底解説!中身を守る箱の秘密と使い分けのコツ »





















