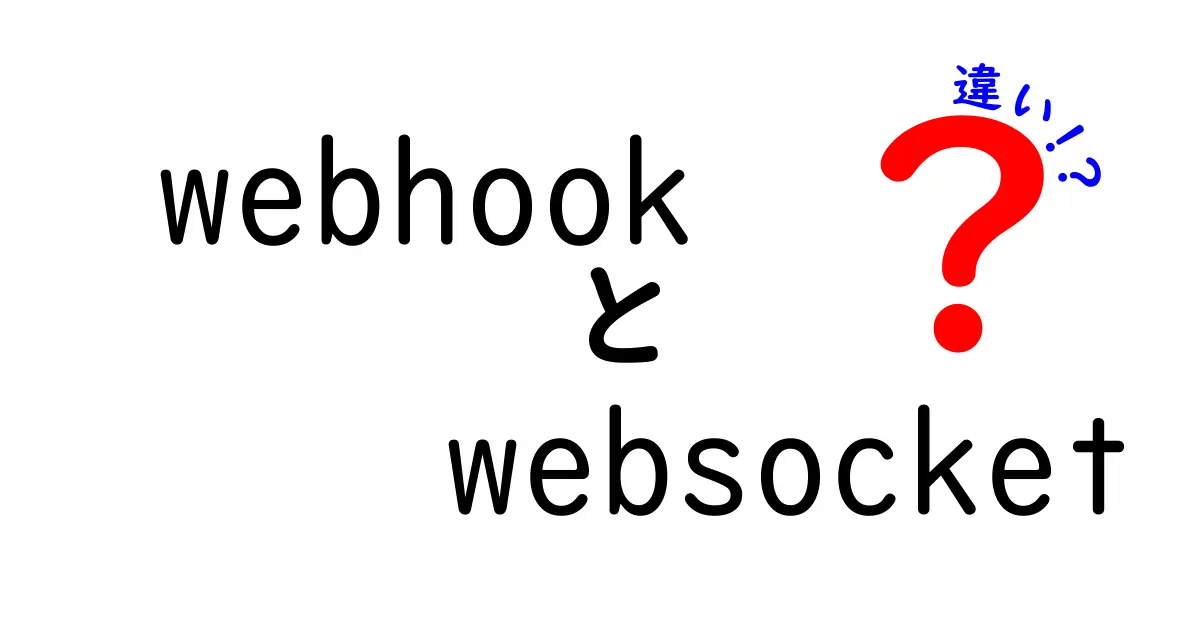

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
WebhookとWebSocketの違いを徹底解説 これを読めば使い分けが分かる!
この二つの技術 Webhookと WebSocket はウェブを動かすときの連携手段としてよく登場しますが、名前は似ていても実際の動き方や使われる場面が大きく異なります。まずWebhookはイベントが起きた瞬間に外部へデータを送る仕組みで、受け手は受信を待つ必要がなく、送信者がイベントを検知したときだけ情報を放出します。対してWebSocketはサーバーとクライアントが一度接続を作るとその接続を長く開いたまま、双方向に自由にデータをやり取りします。こうした違いは実際の運用コストやシステムの設計方針に大きく影響します。この記事では「何を通知したいのか」「どれくらいの頻度で通知するのか」「リアルタイム性の要求」「セキュリティと運用の難易度」を軸に、初心者にも分かる言葉で解説します。
まず結論を先に伝えると、イベント駆動の通知が中心ならWebhook、双方向のリアルタイム通信が必要ならWebSocketを選ぶのが基本です。もちろん実際には両方を併用したり、状況に応じて使い分ける場面も多くあります。理解のコツは「データの流れ方」と「接続の有無」です。Webhookは通知の入口を作る鍵、WebSocketは情報をリアルタイムで引き渡す窓口と考えると分かりやすいでしょう。
この先では、それぞれの仕組みの詳しい動き、現場での使い分けのコツ、そして実際の設計時に気をつけたいポイントを、実例とともに順を追って紹介します。読み進めるほど、どの場面にどの技術を組むべきかが自然と見えてくるはずです。セキュリティや運用コストの観点も忘れずに触れていきますので、予算や要件が固まっていない段階でも役立つ内容です。
なお本文中の用語は初学者にも伝わりやすいよう、可能な限り平易な言葉で説明します。実務で必要な細かな実装のディテールまでは立ち入らず、まずは「違いの感覚」を掴むことを目的としています。最後には比較表も用意しますので、実際の選択をメモと照らし合わせて考えると理解が深まるでしょう。
今日は放課後のオンライン対戦の話題からWebSocketの世界へ少し入ってみよう。友だち同士でリアルタイムの点数や状態を共有する場面、実はWebSocketが強い武器になる場面なんだ。最初は「常に開いている道があると便利そうだけど、そんなに多くの人が同時につなぐと何が起きるの?」という疑問から始まるかもしれない。ここでのカギは接続の保ち方と負荷の分散。接続が長く続くほどサーバーには常時のリソースが必要になるし、切断と再接続の処理を丁寧に設計しないと通信が不安定になる。だから僕たちはまず「どんな場面で使うのか」を整理して、WebhookとWebSocketの違いを日常の例えに置き換えてみる。WebSocketはリアルタイムの対話を前提に、Webhookはイベント通知の郵便配達のように「来たら受け取り、来ない期間は待つ」パターンだと考えると理解が早い。そうして選択の基準を作ると、実装時の迷いも減り、設計が楽になる。つまり、リアルタイム性が重要かどうか、双方向のやり取りが必要かどうか、この2つを手がかりに日々の技術選択をしていこうというのが結論さ。さらに詳しく知りたい人には実装のテクニックまで踏み込んだ記事も用意してあるので、興味のある人は読んでみてね。最後に、難しく聞こえる話を友だちと雑談するような気分で捉えると、勉強も楽しくなるはずさ。





















