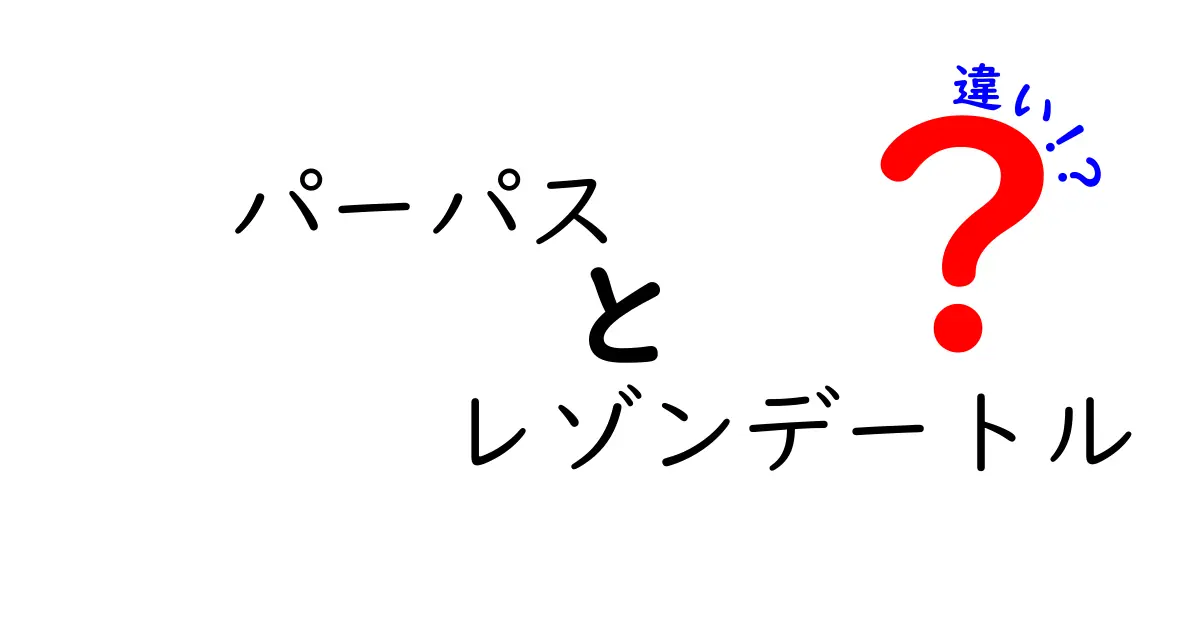

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
パーパスとレゾンデートルの違いを知ろう
現代の組織づくりや自己理解の場面でよく耳にするパーパスとレゾンデートル。この二つは似ているようで、使われ方やニュアンスに違いがあります。まずパーパスは“存在する目的”や“私たちが何のために行動するのか”という現実的で具体的な目的意識を指すことが多いです。企業が公表する場合、従業員のモチベーションを高め、顧客に対して共感を呼び起こすための指針として機能します。
次にレゾンデートルはフランス語由来の表現で、“存在の理由”や“存在意義の根拠”という哲学的・根本的な意味を強く含みます。個人や組織の“なぜこの世に存在するのか”という深い問いかけを表す場面で使われることが多く、抽象度の高い議論や長期的なブランドの正当性を語るときに登場します。これらは同じように“存在意義”を語る言葉ですが、現場での運用や読者の受け取り方には差が生まれやすい点に注意が必要です。本セクションでは、違いを分かりやすく整理し、日常の資料作りや授業の解説にどう落とし込むかを具体例とともに紹介します。
パーパスの意味と使い方
まずパーパスの基本は“目的”と“存在する理由”を結びつける考え方です。ビジネスの場では、会社が何を目指しているのか、社会にどんな貢献をしたいのかを示すガイドラインとして機能します。例えば、地元の食品企業が「地域の健康を支える安全な食を届ける」というパーパスを公表すると、製品開発の判断基準がその目的に沿う形で絞られます。さらに、採用募集や広告の文面にも現れ、従業員の行動や成果の評価にも影響を及ぼします。
またパーパスは日常生活にも影響します。家族のグループ活動で「みんなを笑顔にすることを目的に動く」というパーパスを共有すると、意見がぶつかったときにも合意形成がしやすくなります。マーケティングにおいては現実的で実行可能なパーパスを掲げることが重要で、理念だけで終わらせず、具体的な行動計画と結びつけることが信頼の源になります。ここでのコツは、文字だけの理想論にとどめず、日常の業務や学習の中で「今この瞬間にどう動くか」を示すことです。
レゾンデートルの意味と使い方
次にレゾンデートルを詳しく見ていきます。フランス語由来のこの言葉は“存在意義の根拠”を指し、ただの目的を超えた深い意味を持つ表現です。企業やブランドが自分たちの正当性を語る場面で使われ、長期的な信頼性を支える語として機能します。たとえば、環境問題に取り組む企業が“地球の未来を守る存在意義”を掲げ、製品設計や供給チェーンの選択にそれを反映させると、社会的評価が高まります。しかしレゾンデートルは抽象的になりがちなので、理解を深めるには具体的な行動との結びつけが必要です。
実務で有効にするには、哲学的な説明と日常の行動をつなぐ“実行可能なストーリー”を作ることがコツです。例えば、ある企業がレゾンデートルを語る際には、なぜそれが社会に価値を提供するのかを一貫したエピソードで示し、日常の業務でどう貢献するかを従業員に伝えると理解が深まります。加えて、従業員の参加を促すためのワークショップや事例紹介を取り入れると、レゾンデートルの理解が個人の行動につながりやすくなります。
実務での使い分けと比較
実務の場面ではパーパスとレゾンデートルをどう使い分けるかが重要です。現場の判断基準や従業員のモチベーションを高めるには、まずパーパスを中心に据え、日々の意思決定に反映させることが多いです。具体的には、プロジェクトの目的を明確化する際にパーパスを基準として示し、新規アイデアの採否や優先順位の決定にも影響を与えます。一方、ブランドや組織の長期的な正当性を説明する場面、あるいは大きな変革を語るときにはレゾンデートルの観点を使い、抽象的な正当性を実証可能なストーリーに落とし込みます。以下の表は、意味と使われ方の違いを整理したものです。
このように、現実の業務では両者を使い分けることで、現場の具体性と長期的な信頼性の両方を高めることができます。読み手の立場を想像して、難しい言葉を避けつつ、具体的な行動と結びつけた説明を心がけることが大切です。さらに、チーム内でこの2つの概念を統一して用語集を作成すると、全員が同じ理解を共有しやすくなります。
友達同士で雑談しているときのような口調で、パーパスって何だろう?と気になることがある。僕はパーパスを“その人や組織が何のためにここにいるのかを示す旗の役割”と考える。旗には色や形があり、人はそれを見て方向を決める。だからパーパスは日常の意思決定にも影響するはずだ。対してレゾンデートルは哲学的な問いに近く、存在意義の根拠を説明する時に使われる難しい言葉。だけど難しくても、それを自分や組織の具体的な行動に結びつける工夫が大切。私は、レゾンデートルを語るときには、必ず「どう社会に価値を届けるのか」という実例を添えるよう心がけている。





















