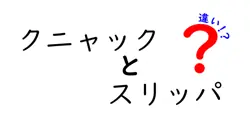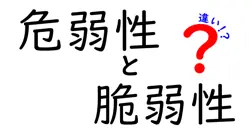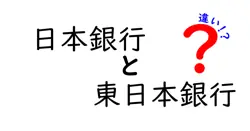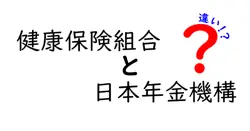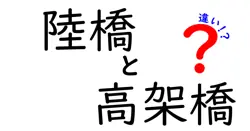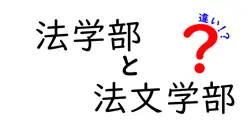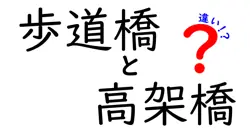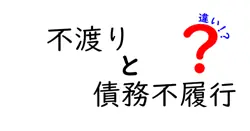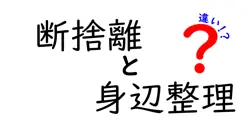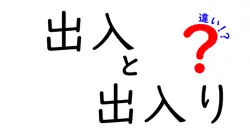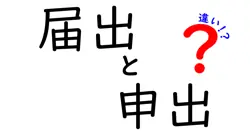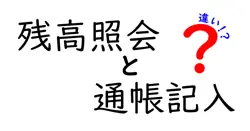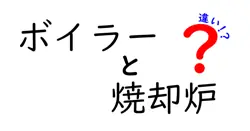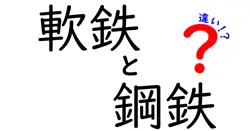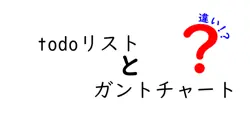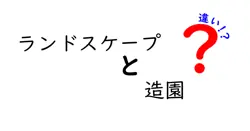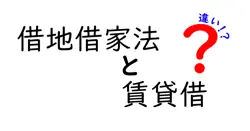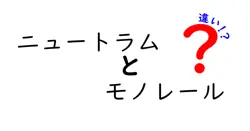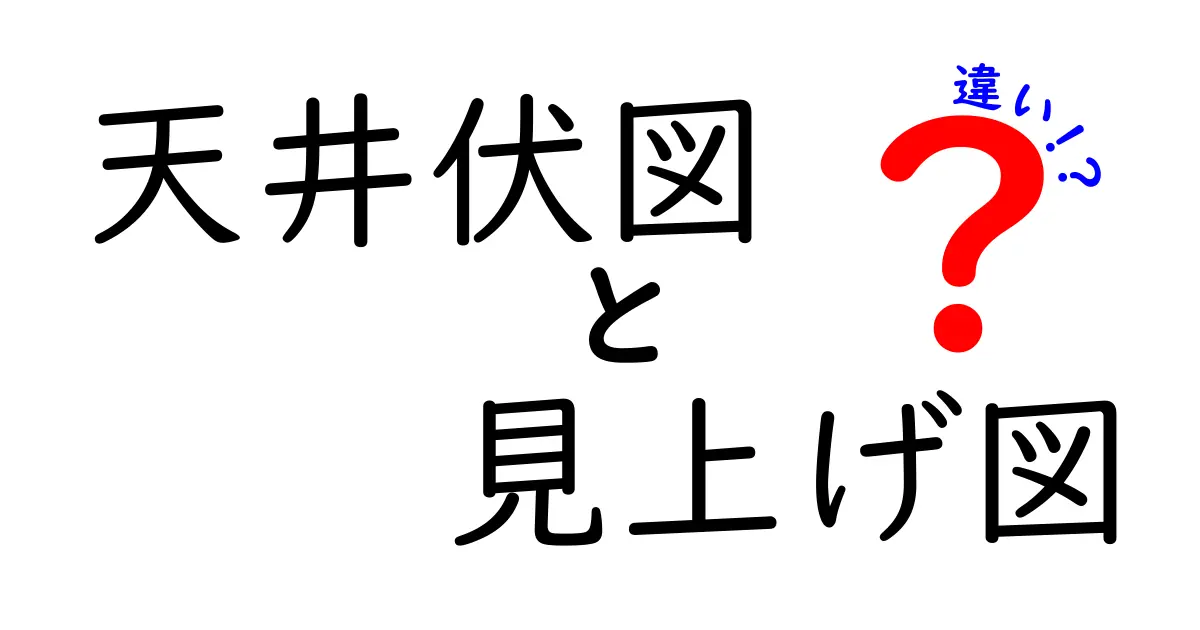
天井伏図とは何か?
天井伏図(てんじょうふせず)は、建物の設計や工事で使われる図面の一つです。
これは、建物の天井部分を真上から見た様子を描いたもので、天井の構造や仕上げ、照明や設備の配置がわかるようになっています。
天井伏図を見ることで、どこにどのような設備があるのか、どんな材質が使われているのかが一目で理解できます。
たとえば、照明器具の位置やエアコンの吹き出し口、換気口などの設備がどこにあるかを確認できるため、施工時に非常に役立ちます。
つまり、天井伏図は天井の設計図のようなもので、施工業者や設計者がスムーズに作業を進められるようにするための重要な図面です。
見上げ図とは何か?
一方、見上げ図(みあげず)は読んで字のごとく、実際に立って上方向を見上げたときの視点を表現した図面です。
天井伏図が真上からの俯瞰(ふかん)図であるのに対し、見上げ図は人が実際に天井や空間を見上げたときの視覚イメージを示した図面です。
この図は、天井の形状や装飾、照明の光の当たり方、空間の高さ感などをイメージしやすく描かれています。
設計者やクライアントが施設や部屋の雰囲気をつかむために活用されることが多く、実際の空間の感覚に近い見え方を伝えるのが特徴です。
見上げ図は完成後の見た目を想像しやすくするために使われる図面と言えます。
天井伏図と見上げ図の違いをまとめた表
| 項目 | 天井伏図 | 見上げ図 |
|---|---|---|
| 視点 | 真上から俯瞰 | 下から見上げる視点 |
| 目的 | 天井構造や設備の配置確認 | 完成イメージの提示 |
| 使う人 | 設計者・施工者 | 設計者・クライアント |
| 表現内容 | 構造・配置・寸法 | デザイン・空間の雰囲気 |
| 作成タイミング | 設計・施工段階 | プレゼンテーション段階 |
このように用途や見方が異なるため混同しやすいですが、両方とも建築の重要な図面です。
工事や設計の際には天井伏図を使い、完成イメージの共有や打ち合わせの時には見上げ図を活用すると理解が深まります。
ぜひ建築の図面を見る際に、どちらの図面なのかを意識してみてください。
そうすることで建物の構造やデザインの意図がより分かりやすくなるでしょう。
「天井伏図」は文字通り天井の伏せ図なので、設計や施工では“俯瞰的”な視点が基本です。でも、実際の建物内で人が感じる雰囲気は“見上げた視点”だから、そこをリアルに伝えたい時に「見上げ図」が使われます。意外に建築の世界では、この視点の違いが設計のコミュニケーションに大きく影響しているんですよ。ぜひ図面を見るときは視点の違いに注目してみてくださいね。
前の記事: « ジオラマと建築模型の違いとは?初心者にもわかるポイント徹底解説!