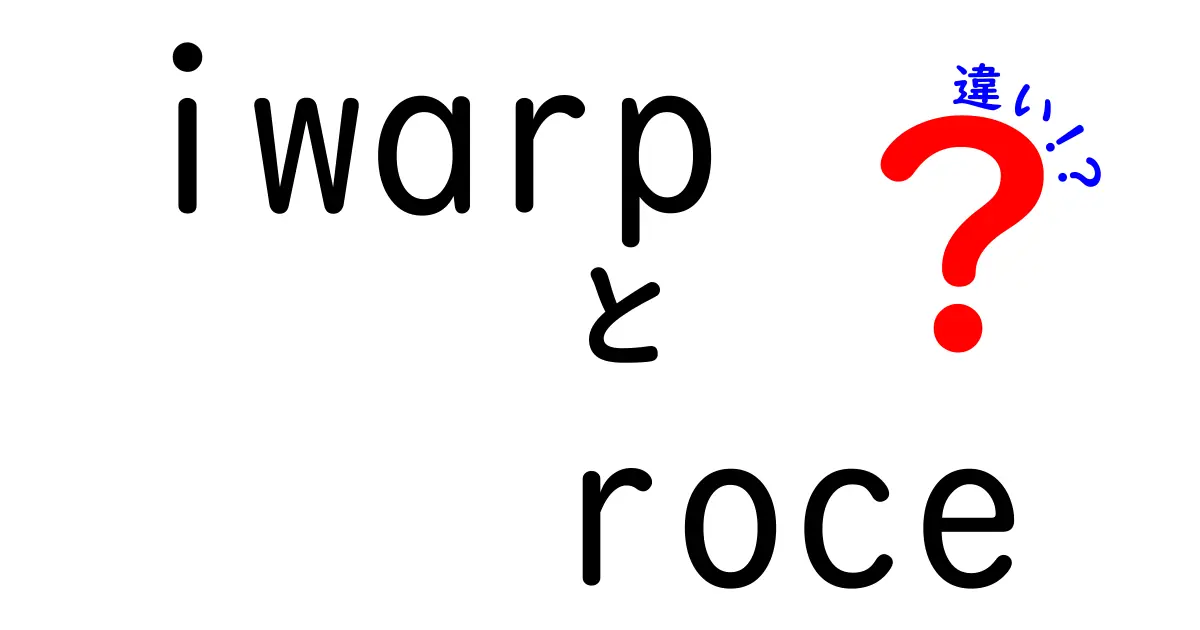

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
iWARPとRoCEの違いを理解するための基礎知識
iWARPとRoCEはデータセンターのネットワークで使われるテクノロジーです。どちらもRDMAと呼ばれる技術を使い、CPUの負担を減らして高速データ転送を実現します。iWARPはTCP/IP上で動作するRDMAの実装であり、既存のTCP/IPネットワークを活用しやすいのが特徴です。一方RoCEはエリアネットワークのDCB機能を前提に動作し、専用のlossless Ethernetを前提とした設計が多いです。これらの基本的な考え方の差を知ることが、実際の現場での選択に直結します。
以下ではそれぞれの仕組みの詳細と、どんな場面でどちらを選ぶべきかを整理します。
まず大切なのは、RDMA自体が「CPUの負担を減らして転送を効率化する技術」である点です。iWARPはTCP/IPの信頼性を活かして動作しますが、RoCEはEthernetの拡張機能を使って遅延を小さくすることを狙います。
この違いを知ると、現場のネットワーク設計やNIC/スイッチの選択肢がどのように変わるかが見えてきます。
1) 技術の根本的な違い
技術の根本的な違いとして最も重要なのは「どの層の通信をRDMAで最適化するか」という点です。iWARPはTCP/IPの上で動くRDMAであり、信頼性の高い転送をTCPの機構に任せつつRDMAのゼロコピーを実現します。これにより、既存のLAN環境と高い互換性を保ちながらRDMAを適用できるのが特徴です。対してRoCEはEthernetのDCB機能を前提とし、RDMAをEthernetのレイヤーで直接実現します。RoCEは特にデータセンター内の「遅延を極限まで抑える」目的で設計され、PFC(Priority Flow Control)などの機能を使って損失を抑えつつ高帯域を狙います。この差は、現場のネットワーク機器選択や設定に大きく影響します。
つまり、iWARPは“普段のネットワークをそのままRDMAで速くする”発想、RoCEは“伝送路を最適化して RDMA を最も速く動かす”発想と言えるでしょう。
この区別を理解しておくと、後の遅延やコストの判断材料がはっきりしてきます。
重要ポイント:iWARPはTCP/IP上の信頼性を活かすため現場の導入が比較的容易、RoCEはDCBの前提と高性能を両立させる選択肢として検討されることが多いです。
2) 遅延と帯域の現実的な比較
遅延の観点では、iWARPはTCPの輻輳制御や再送が発生する場面で若干の影響を受けやすい場合があります。TCPの挙動そのものが遅延要因になることがあるため、ネットワークの混雑時には遅延が増えることがあります。一方、RoCEはDCBを前提にして設計されており、PFCなどの損失回避機能を有効化することで 今日はRoCEとiWARPの話題について、僕と友だちの会話風に深掘りします。友人が「うちのデータセンター、RoCEにするべきかな?」と聞いてきたとき、僕はこう答えました。ROCEは確かに遅延を抑える力が強いけれど、DCB設定やスイッチの対応状況を前提に話さないと失敗します。一方でiWARPは“今あるEthernet基盤をそのまま活かせる”ので、新規導入のハードルは低め。ただし実際の性能はワークロード次第。結局は現場での検証が一番大切だよね。僕たちはまず小さな検証環境を作って、数値で判断することにした。話をしているうちに、技術の違いだけでなく運用の現実感が見えてきて、どちらを選ぶべきかの判断材料が見えてくる。
ITの人気記事
新着記事
ITの関連記事





















