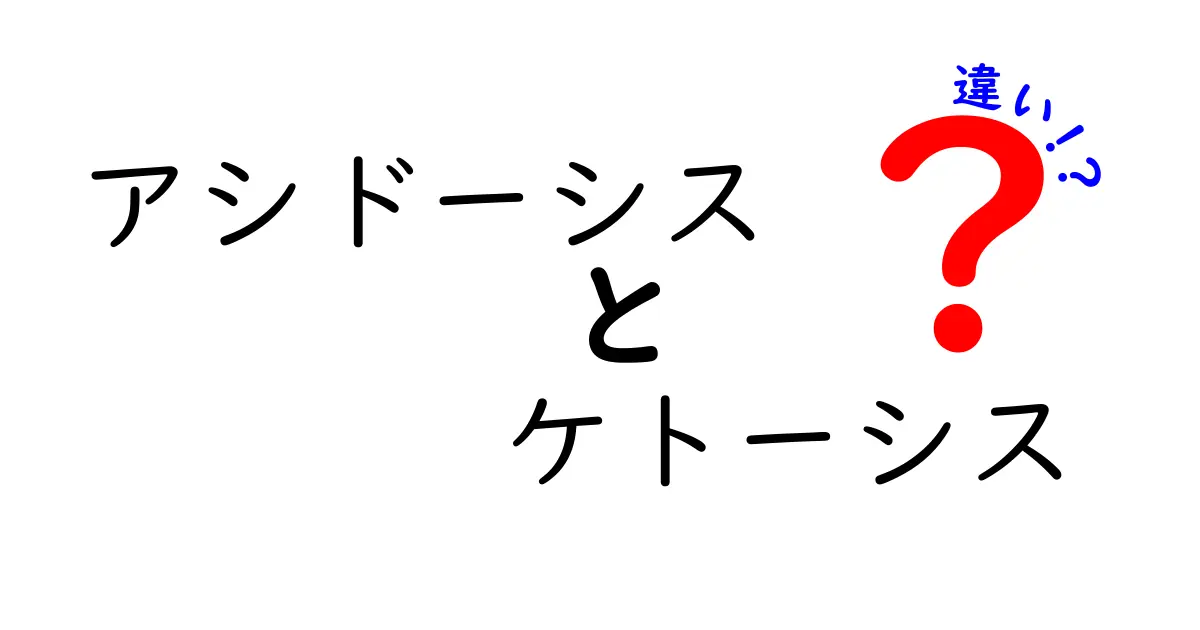

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アシドーシスとケトーシスの違いを理解するための入門ガイド
私たちの体は毎瞬、酸とアルカリのバランスを保っており、血液のpHは7.35から7.45の範囲が健康の目安です。この範囲を外れると体の機能がうまく動かなくなります。アシドーシスは血液が酸性寄りになる状態の総称で、原因は呼吸の問題、腎臓の働きの低下、体内で作られる酸の量が増えることなどです。一方、ケトーシスは脂肪をエネルギー源として使うとき体内にケトン体が増える状態のことを指します。ケトン体は通常は少ないのですが、飢餓状態や糖質の少ない食事、過度の運動、アルコールなどの影響で増えることがあります。
両者は別々の現象ですが、ときには関係してくることもあり、病院で診断される「ケトアシドーシス」という合併症も存在します。中学生にも理解できるように、ここでは「何が起きているのか」「どんな症状があるのか」「どう判断するのか」を順番に整理します。まずは基本のイメージをつかみましょう。
このガイドのねらいは、難しい専門用語を避けつつ、日常生活での注意点や考え方のコツを伝えることです。読み進むと、胃腸の不調や息苦しさ、頭痛といった体のサインがどのようにつながるのかが見えてきます。強調したいポイントは、pHは命を左右する「基礎指標」、ケトーシスは必ずしも悪いものではないが放置すると危険な場合がある、症状が長く続くときは専門家の診察を受けるべきという点です。理解を深めるためにも、次の章から具体的な状態と違いを丁寧に見ていきましょう。
ここまでの要点をまとめると、アシドーシスは「血液が酸性に傾く状態」、ケトーシスは「ケトン体が増える状態」という、似ているようで異なる二つの現象だということです。
この違いをしっかり押さえることが、健康管理の第一歩となります。
アシドーシスとは何か
アシドーシスとは、体の血液が酸性寄りになる状態のことです。正常な血液のpHは7.35から7.45ですが、これを下回ると体の反応がうまく働かなくなります。アシドーシスには大きく分けて二つのタイプがあります。呼吸性アシドーシスは二酸化炭素が血液中に増えすぎることで起こり、肺の働きが低下したり、過度の呼吸抑制が原因になることがあります。代謝性アシドーシスは体内で酸が過剰に作られるか、炭酸水素塩が不足すると起こります。糖尿病のコントロールが乱れたときや腎臓の機能が低下したとき、重症な感染症やショックの状態でも発生します。症状としては頭痛、めまい、呼吸が浅く不規則になる、倦怠感、意識レベルの低下などが挙げられます。治療には原因の除去と体内の酸塩基のバランスを戻すための医療的介入が必要です。大切なのは早めの診断と治療で、放置すると臓器障害に進む危険性が高まります。
ここで学ぶのは、アシドーシスは「酸性に傾く状態全般」を指す広い概念であり、原因やタイプによって対応が異なるという点です。自分の体で「息苦しい、頭が重い、眠気が強い」などのサインが続く場合は、すぐに医療機関を受診することが重要です。
ケトーシスとは何か
ケトーシスとは、脂肪をエネルギーとして使うときに肝臓で作られるケトン体が増える状態のことを指します。空腹時や糖質を控えた食事、長時間の激しい運動、あるいは糖尿病の悪化などで体が糖を十分に使えなくなると、脂肪が分解されてケトン体が生じます。代表的なケトン体にはアセトン、アセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸があります。ケトーシス自体は自然な代謝の変化であり、短期間であれば体に害は少ないことが多いです。しかし、適切な水分補給や電解質の補充がないと脱水を招き、体調を崩すことがあります。特に糖尿病の人は血糖とケトン体のバランスを崩しやすく、重症化するとケトアシドーシスと呼ばれる深刻な状態に進む可能性があります。ケトーシスとケトアシドーシスの違いは、ケトン体が増えるという現象が起きても、pHが必ずしも低下していない点にあります。もちろん、ケトン体が過剱に蓄積すると体が酸性化してしまい、ケトアシドーシスへ進むこともあり、糖尿病患者には特に注意が必要です。日常生活では、過度のダイエットや断食、過度の運動が原因でケトーシスに陥る可能性があるため、栄養バランスと水分・電解質の補給を意識しましょう。
そして、ケトーシスの理解で重要なのは「体のエネルギーの使い方が一時的に変わる」という点です。普段と違うエネルギー源の使い方をしているとき、体は代謝の調整を行い、結果として血液のpHに影響を与えることがあります。適切な知識を身につけ、無理をしない生活を心がけることが大切です。
表で見るアシドーシスとケトーシスの違い
この表は、アシドーシスとケトーシスの基本的な違いを一目で比べるためのものです。実際には患者さんの病状に応じて専門家が判断します。なお、両者は密接に関係することがあるため、症状が気になる場合は早めに受診してください。
健康な生活を送るためには、日々の食事、睡眠、適度な運動、水分補給をバランスよく保つことが大切です。特に糖質制限を長く続ける場合には、体がどう反応しているかを自分で観察する力を養い、違和感があれば専門家に相談する習慣をつけましょう。
ある日の放課後、友だちと保健の授業の話題で盛り上がった。『アシドーシスとケトーシスって、同じ酸性に関連してるのに別物だよね?』と僕。先生は静かに頷き、まずは定義から説明してくれた。アシドーシスは血液のpHが下がる状態、ケトーシスは脂肪をエネルギーにしたとき作られるケトン体が増える状態。『どちらも体の酸塩基バランスを崩す可能性があるんだけど、原因と程度が違うんだ』と先生。私たちはノートに書き込み、いま自分の生活でどんな場面があるかを考えた。





















