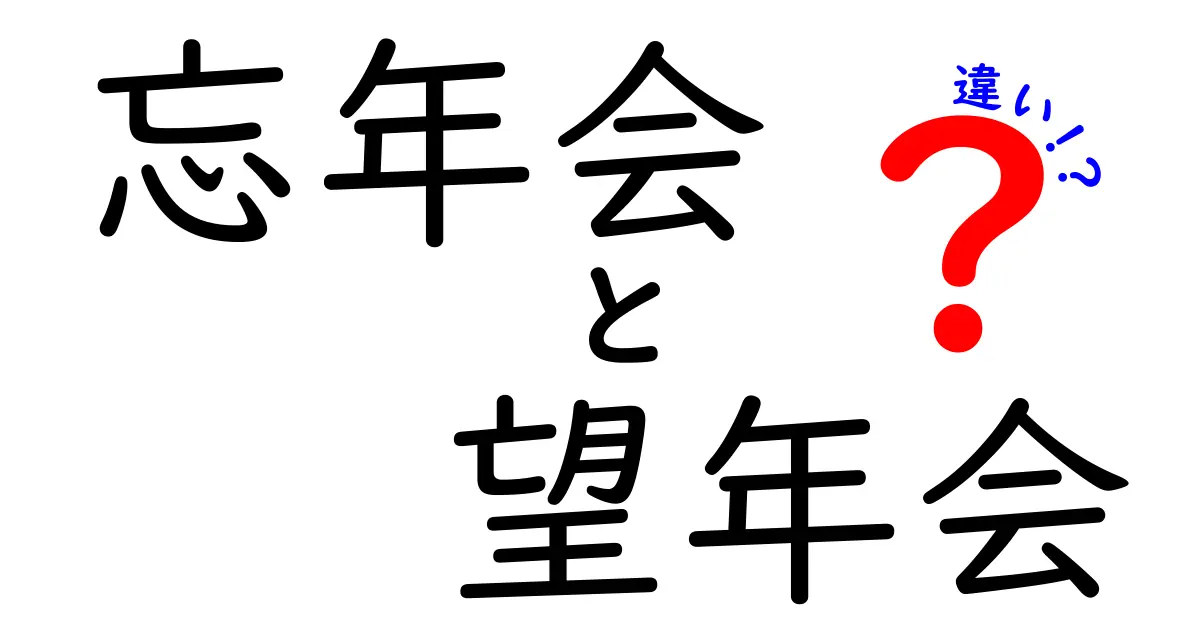

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:忘年会と望年会の違いを知ろう
現代の日本の職場やサークルでは年末に開かれる行事として忘年会が定番化しています。忘年会とは文字通り去年の出来事を忘れて新しい気持ちで来年を迎えるための集まりです。多くの場合、12月の終盤に行われ、飲食と歓談を軸に仲間たちの結束を深めます。雰囲気は賑やかでありながら、日頃の疲れを癒やす場としての役割も大きいです。
一方で 望年会 という言葉は一般的にはあまり使われませんが、意味としては来年へ向けた希望を語る会や来年の計画を話し合う場と解釈されることがあります。意味が重なることもありますが、実際には組織によって使われる場面や時期が異なることが多いです。
この記事では忘年会と望年会の違いを分かりやすく整理し、どちらを選ぶべきかの判断材料を提供します。
忘年会と望年会の違いを理解する第一歩として、両者の基本的な性格を押さえておきましょう。忘年会は去年の出来事を笑い話にしながら協力関係を強化することに重点があり、望年会は来年の目標設定や新しい年の幸先を祝う気分が中心となります。どちらも大切な社内のコミュニケーションイベントですが、目的が異なるため企画の組み方や参加者の反応も変わってきます。
この章の要点を押さえると、年末のイベントをただの会食として終わらせず、組織の風土に合わせて適切に活用できるようになります。年の区切り方を意識し、言葉の使い方に気をつけることで、場の雰囲気をより良く保てます。忘年会と望年会の違いを理解し、場の目的に合わせた準備をすることが大切です。
忘年会と望年会の違いを具体的に比較
まず時期の違いから見ていきましょう。忘年会は通常12月の終盤に行われ、1年の締めくくりとしての意味合いが強いです。来年へ切り替える準備というよりは、今年のことを締めくくる雰囲気が強く、飲み会としての要素が中心になることが多いです。反省よりも仲間との絆を深める場になるよう工夫されることが多いです。
望年会は地域や組織により時期が異なります。年末近くに開催されることもあれば、来年の始まりを祝うために1月など遅い時期に設定されることもあります。目的としては来年へ向けた意識の共有や新しい年の目標設定が中心です。来年の方針をみんなで相談し、具体的な行動計画へ落とし込む場として設計されることが多いです。
雰囲気の違いも重要です。忘年会は賑やかで冗談が飛び交い、上司と部下の関係性も緩やかになる場面が多いです。望年会は落ち着いた空気の中で真面目な話題が増えることがあり、プレッシャーを感じやすい人がいる場面もあります。どちらを選ぶかは組織の現状やメンバーの性格、年度末の業務状況を踏まえて判断すると良いでしょう。
次に企画の違いを見てみましょう。忘年会の企画はゲームやカラオケ、ビンゴなどの盛り上がり重視型が多いです。望年会は来年の抱負を共有するセッションや、グループディスカッション、目標設定のワークショップ形式が組み込まれることが多く、実務的な話題が増える傾向があります。こうした違いを理解しておくと、当日の準備や会場選び、進行の仕方を適切に選べます。
- 忘年会は話題がフランクでリラックスした雰囲気が多い
- 望年会は来年の目標や計画を話し合う場になることが多い
- どちらも基本は仲間意識の醸成だが、焦点となる話題が異なる
- 会場選びも雰囲気に合わせて変えると成功しやすい
実際の場の雰囲気と企画の具体例
忘年会の企画例としては、乾杯の後に軽い挨拶、ビンゴ大会、カラオケや余興、締めの挨拶と逃げ場のない楽しい雰囲気作りが挙げられます。笑いと連帯感を生み出す工夫が大切で、過度に個人攻撃的な発言や愚痴が長引かないよう空気を作るのも重要です。
望年会の企画は、来年の目標を共有するセッションが中心です。プレゼン形式での発表、グループディスカッション、具体的なアクションプランの作成、最後に全員で合意形成を図る時間を設けると効果的です。現実的で測定可能な目標を設定し、それを職場でどう実行するかを具体化します。
表の活用もおすすめです。下記は簡易的な比較表の例です。 項目 特徴 目的 忘年会は今年の締めくくりと絆、望年会は来年の目標共有と準備 時期 忘年会は主に12月、望年会は地域により12月か1月 ble>雰囲気 忘年会は賑やかで開放的、望年会は落ち着きがあり前向き
いろいろな組織で行われるイベントですが、あえて同じイベント名を使うよりも、目的に合わせて実際の名前を決めると混乱を避けられます。忘年会と望年会の違いを理解することで、年末年始の時間をより有意義に使え、組織の雰囲気も改善することができます。
ねえねえ、忘年会と望年会の話、今日の話題の本題って結局どう違うの?と思ってる人も多いかもしれないけど、実は場の目的が違うだけでやること自体は似てるんだよ。忘年会は去年の頑張りをみんなでねぎらい、時には失敗を笑い話にして来年へつなぐ“エネルギーチャージ”の場。だから盛り上がり重視の企画が多く、観客席とステージの距離が近い。望年会は来年の目標設定や計画づくりが中心。話題は実務的で、具体的なアクションへ落とし込む作業が入る。私の友人が所属している団体では、望年会のときに各自が来年の目標を1分程度で発表する時間を必ず設けていて、終わった後の雰囲気がぐっと前向きになるんだ。こうした差は、日常のコミュニケーションにも影響する。忘年会は「楽しく終えること」が目的のひとつ、望年会は「具体的な成果へつなぐこと」が目的。どちらを選ぶべきか迷ったときは、組織の直近の課題とメンバーのニーズを考えて決めると、場の効果を最大化しやすいよ。ちなみに、どちらも準備で大切なのは“場の空気を読み、誰もが参加しやすいルールを作ること”。





















