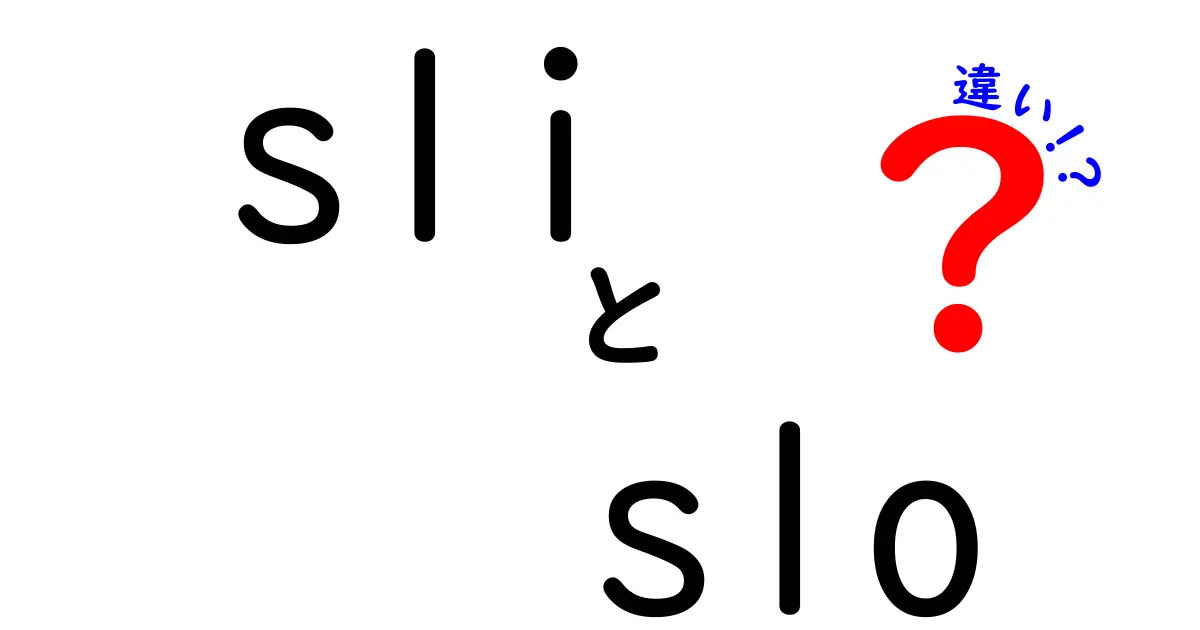

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:sliとsloの基礎を正しく理解する
現代のWebサービスやアプリは、利用者にとって「いつでも動くこと」が最も大事です。そのためには、まず自分たちが何を測るのかを決める必要があります。ここで登場するのが SLI(サービスレベル指標)と SLO(サービスレベル目標)です。SLIとSLOは、信頼性の設計と改善の核となる考え方で、現場の監視・運用・改善の指標系を作る土台になります。この記事では、初心者にも分かるように、SLIとSLOの違い・使い方・注意点を、実務の場面を想定して解説します。まずは両者の基本の定義から押さえ、その後、実務での具体的な運用方法やよくある誤解を解消していきます。読み進めるほど、なぜこの2つの概念が同時に重要なのかが見えてくるはずです。
この章では、まず大枠のイメージをつかむことを目標にします。SLIは「今、測っている値はどうか」という現状の品質を表す指標であり、SLOはその品質に対する「達成すべき目標」のことです。例を挙げれば、ウェブページの応答時間をSLIとして測定し、97パーセンタイルの応答時間が2秒以下になるようにSLOを設定する、という形です。現場ではこの二つを適切に設定し、監視とアラートを結びつけることで、ユーザー体験を安定させるための意思決定がしやすくなります。
この理解を元に、次のセクションではSLIとSLOそれぞれの正確な意味と役割を詳しく見ていきましょう。
SLIとは何か?
SLI(Service Level Indicator)は、サービスの品質を定量的に示す指標のことです。これが「何を測るのか」を示す指針となり、実務では「ユーザーが感じる体感品質」に直結する指標を選ぶことが重要です。典型的な例としては、可用性(一定期間中にサービスが利用可能だった割合)、応答時間(総リクエストのうち、何パーセントがどの時間内に完了したか)、エラーレート(リクエストのうちエラーとなった割合)などがあります。SLIを設計する際には、データの取得方法・測定の粒度・欠損値の扱いなど、計測の品質自体を検討する必要があります。測定開始時には、ユーザー体感と技術仕様の整合性を意識して、測定対象と計測頻度を決定します。
SLIを正しく設定すると、後のSLO設定やアラート設計が格段にスムーズになります。測定値はダッシュボードに表示され、日々の監視の基礎データとして機能します。ここで重要なのは「データが信頼できるかどうか」です。データの品質が低いと、SLOの評価自体がぶれてしまい、改善の判断が難しくなるからです。
また、SLIは「現状の品質を示す」指標であるため、時間とともに変化する可能性がある点も理解しておくべきです。閾値を決める際には、過去のデータを基にした現実的な値を設定し、長期的なトレンドを観察する姿勢が求められます。
SLOとは何か?
SLO(Service Level Objective)は、SLIを基に定める「品質の目標値」です。SLOは、どの程度の品質をどの期間で達成するべきかを示す約束ごとであり、組織の信頼性の「合意事項」として機能します。たとえば、あるWebアプリの可用性を99.9%と設定する場合、その期間は月次、日次、または週間など、組織が決めた時間粒度での達成を目指します。SLOは、開発チームと運用チームの間での共通言語として役立ち、遅延が生じたときには改善の優先度を決める基準にもなります。
SLOを設計する際には、現実的で測定可能な値を設定することが重要です。あまりにも厳しいSLOは日々の運用を圧迫し、緩すぎるとユーザー体験の質を担保できません。また、SLOは「時間の窓(ウィンドウ)」を設定する点が特徴で、例えば“月間での達成率”や“過去24時間の達成率”といった形で評価します。SLOを適切に運用することで、組織は品質の変動を可視化し、改善の優先順位を明確にすることができます。
SLIとSLOの違いを整理するポイント
SLIとSLOは似ていますが役割が異なります。SLIは「何を測るか」という測定対象の指標そのもの、SLOは「どの程度なら acceptable か」という目標値です。現場での活用例を挙げると、SLIは“レスポンス時間の95パーセンタイルが2.5秒以下か”という現状の指標、SLOは“この月の可用性を99.9%に達成する”という達成基準です。これらを組み合わせると、監視から改善までの流れがスムーズになります。注意点としては、SLIの測定値が信頼できるデータであること、SLOの閾値設定が現実的であること、そして閾値を越えたときの運用ルール(アラートの出し方・リソースの割り当て・改善の優先度など)を事前に決めておくことです。こうした設計を怠ると、単なる指標の羅列に終わり、実務での意思決定を阻害してしまいます。
結論として、SLIとSLOはセットで機能します。SLIが「今この瞬間の品質」を、SLOが「品質を維持するための約束」を示すことで、組織全体の信頼性を効率的に高めることが可能になるのです。
実務での活用のコツと注意点
実務でSLIとSLOを活用するには、現場のニーズと組織の能力に合わせた設計が必要です。まずは「ユーザー体感と直結する指標」を優先的に選び、測定の自動化を進めます。データ収集の自動化は、頻繁に発生するアラートの根拠を正確にするための基盤です。次に「SLOを現場の意思決定に結びつける仕組み」を作ること。SLO超過時の対応ルール、予算の再配分、リリースの判断基準などを事前に定義しておくと、緊急時にも動きやすくなります。
また、SLOを設定する際には“過去のデータから現実的な閾値を設定する”“定期的に見直す”といった運用習慣が重要です。KPIと混同しやすい点にも注意が必要で、SLOは顧客体験の品質を長期的に安定させるための「約束事」であり、短期の成果指標とは別に設計するのが理想的です。最後に、チーム間のコミュニケーションを円滑にするために、SLIとSLOの定義を文書化し、新規メンバーにも理解できるように共有しましょう。こうした実践を積むことで、信頼性の改善サイクルが継続的に回り始めます。
友達A: ねえ、SLIとSLOの違いって何者なの? 友達B: 簡単に言えば、SLIは今の品質を測る“指標”、SLOはそれを達成するための“目標”だよ。例えば、サイトの応答時間をSLIとして測るとする。97パーセンタイルが2秒以下ならいい、というのがSLOになる。つまりSLIが測定値、SLOがその測定値に対する約束ごと。現場ではこの2つをセットで使うことで、何を改善すべきかがはっきり見えるんだ。





















