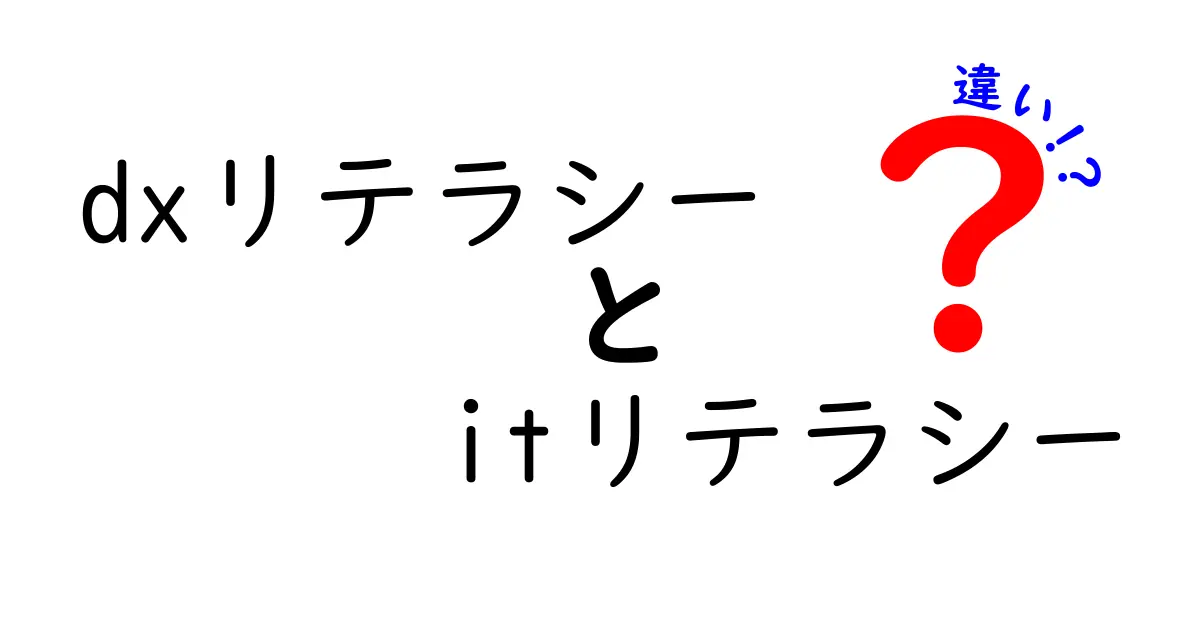

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基礎理解:DXリテラシーとITリテラシーとは何か
近年「DXリテラシー」という言葉をよく耳にしますが、同じ土俵でもう一つの言葉「ITリテラシー」とは何が違うのかを正しく理解することは、学校の授業だけでなく将来の仕事にも役立ちます。
この二つは似ているようで、対象と目的、必要とされる視点が異なります。
まずは基本を押さえ、次に実際の現場でどう使われるのかを考えていきましょう。
『難しく考えず、日常の体験から比較すること』がポイントです。
この章では、用語の定義と歴史、誰が使うべきか、どんな場面で使われるのかを、できるだけ具体例とともに説明します。
DXリテラシーの要素と日常での活かし方
DXリテラシーとは、デジタル技術を用いて組織や社会の仕組みを「変革(Digital Transformation)」する力のことです。
単に機械を使えるだけではなく、問題を見つけ、データから答えを導き、組織の仕組みを変えるための考え方を含みます。たとえば学校のクラブ活動をグループチャットとオンライン共有化で効率化したり、地域のイベント運営をデータ分析で来場者の動きを予測して改善したりすることが該当します。日常での活かし方は、まず現場の課題を「デジタルという道具でどう解決できるか」を考えることです。
次に、データの取り扱い方、セキュリティの基本、チームでの協働方法、そして変化を楽しむ心を育てることが大切です。
つまり、DXリテラシーは「新しい技術を使う力」だけでなく、「変化を起こす力」を含む広い視点のことを指します。
この視点を身につけるには、身の回りの課題を観察し、仮説を立て、試して検証するという、科学のような思考プロセスを練習するのが効果的です。
ITリテラシーの要素と学び方
ITリテラシーは、コンピュータやネットワーク、ソフトウェアを使いこなす基本的な力のことです。ここには「情報を正しく扱う力」「安全に使う意識」「トラブルを自分で解決する初歩的な技術」が含まれます。中学生にも身近なのは、PCやスマホでの設定、ソフトの使い方、情報の出所を見極める力などです。学ぶ順序としては、まず道具の操作を確実に身につけ、次に情報の信頼性を判断する力、最後に簡単な問題解決の手順を覚えると良いでしょう。
ITリテラシーは、個人の生活を豊かにするだけでなく、将来の就職活動や進学の際にも基本的な土台となります。
このリテラシーは、学校の授業だけでなく、自分の興味に合わせてやり方を変えられる柔軟性が重要です。
たとえば自分のスマホの設定を見直し、セキュリティを守る方法を学ぶことから始めると、自然と次のステップへ進みやすくなります。
実践編:自分に必要なスキルを見極めるためのチェックリスト
この章では、今の自分にとって DX と IT のどちらが急務かを判断するチェックリストを紹介します。まずは自分の近い課題を挙げ、次にそれを解決するためのデジタル手段を列挙します。具体的には日常の勤怠管理、学習ノートの整理、情報の検索の仕方、友人やクラスメートとの連携の取り方などを例にします。
次に、実際に何を学ぶべきかを「短期・中期・長期」の3つの視点で整理します。
さらに、チームで協力して課題を解決する経験を積むことも大切です。
最後に学習計画を作成し、週ごとに達成度を評価することで、着実にリテラシーを高められます。
このプロセスは、受験勉強や部活動の活動計画にも応用できます。
- 課題を見つける - 生活の中の困りごとをノートに書く
- データで裏付ける - どんなデータを集めればいいか考える
- 解決策を試す - 小さな実験を繰り返す
- 成果を共有 - 学んだことを他の人と説明する
放課後の教室。AくんとBさんがDXリテラシーについて雑談している。Aが『DXリテラシーって結局、デジタル技術で現場を変える力だよね』とつぶやくと、Bは『ITリテラシーが基礎、DXは応用の組み合わせを作る力だと思う』と返す。二人は学校行事の運営を題材に、データを集めて現場の課題を可視化し、仮説を立て、実際に少しずつ試す過程を話し合う。会話の中でデータを記録し、小さな成功を共有することの大切さを確認し、未来の学習へとつながる気づきを得た。





















