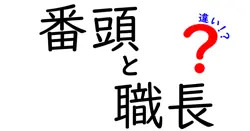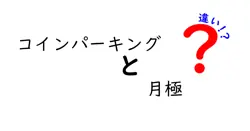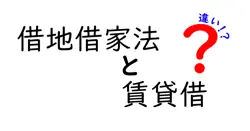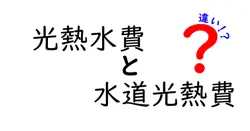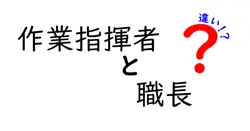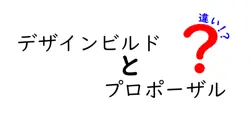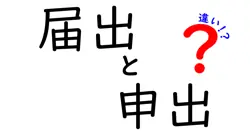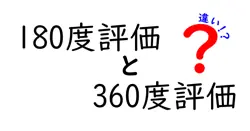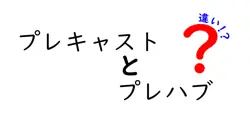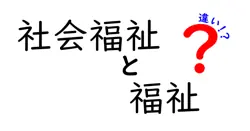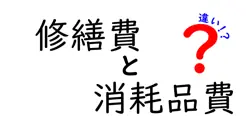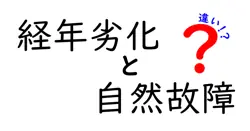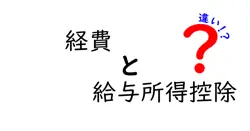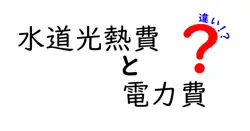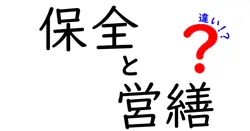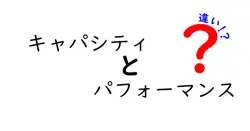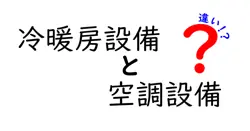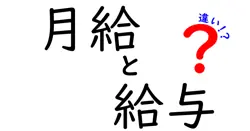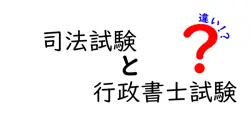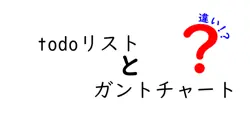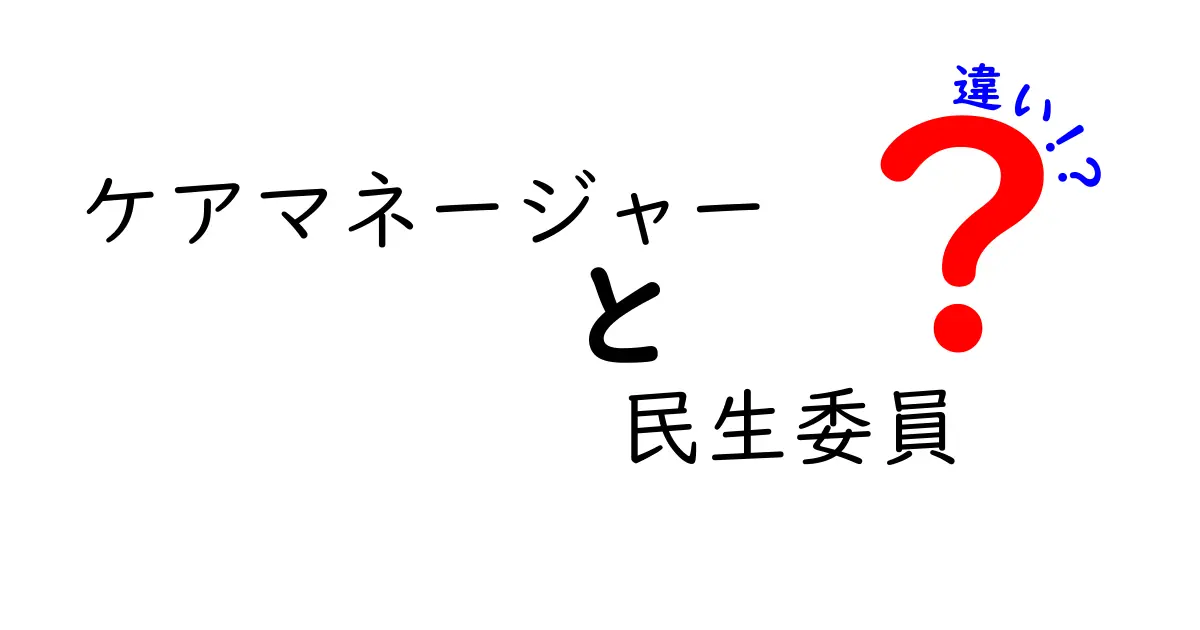
ケアマネージャーと民生委員の基本的な役割の違い
まずは、ケアマネージャーと民生委員の基本的な役割について理解しましょう。
ケアマネージャーは正式名称を「介護支援専門員」といい、介護が必要な人のためにケアプラン(介護サービス計画)を作成します。介護サービスがスムーズに受けられるよう、本人やその家族、サービス提供者と相談しながら介護の計画や調整を行う専門職です。
一方で、民生委員は地域の住民の生活支援や相談役として活動しています。地域の困りごとを聞き取り、社会福祉協議会や行政と連携しながらさまざまな生活課題の解決を手助けするボランティア的な役割を担っています。
つまり、ケアマネージャーは主に介護の専門職で、民生委員は地域住民の生活全般を支える存在という違いがあります。
仕事内容や資格面での違い
両者は仕事の内容や求められる資格にも大きな違いがあります。
ケアマネージャーの仕事は、介護サービス計画の作成だけでなく、介護が必要な方の状態を評価し、適切なサービスを選ぶことも含まれます。医療や介護の知識が深く求められる専門職なので、介護福祉士や看護師、社会福祉士などの資格を持ち、さらにケアマネージャーの資格試験に合格する必要があります。
これに対して、民生委員は地域のボランティア活動が中心で、特に資格要件はなく、地域の住民の信頼を得た人が選ばれます。役割は幅広く、住民の困りごとを聞いたり、行政の制度を案内したりすることが中心です。仕事は無給で、地域に密着したサポート役として活動しています。
このように、ケアマネージャーは専門職であり、有給の仕事であるのに対し、民生委員はボランティア的で資格不要、地域の生活支援が中心という大きな違いがあります。
活動場所や関係機関の違い
ケアマネージャーは主に介護保険制度の枠組みの中で病院、介護施設、訪問介護事業所など様々な場所で働いています。介護を受ける本人や家族と日常的にやり取りをしながら、ケアプランの進行状況の確認やサービス調整を行います。
一方、民生委員は地域ごとに自治体や社会福祉協議会の支援を受けながら、その地域の住民と密接に関わり、困りごとの早期発見や生活相談、見守り活動をしています。
ケアマネージャーが介護の専門サービスの利用に関わるのに対し、民生委員は生活全般の見守りと相談が主な役割で、生活困窮者や高齢者だけでなく地域住民全体を対象に活動しています。
以下の表により違いをまとめます。
| 項目 | ケアマネージャー | 民生委員 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 介護サービス計画の作成・調整 | 地域住民の生活支援・相談 |
| 必要資格 | 介護福祉士など実務経験+ケアマネ資格試験合格 | 特になし(地域から選出) |
| 雇用形態 | 有給の専門職 | 無給のボランティア |
| 活動場所 | 介護施設、病院、訪問先など | 地域全般、自治体・社会福祉協議会と連携 |
| 対象者 | 介護が必要な人や家族 | 地域住民全般 |
ケアマネージャーという言葉は、専門的な介護のサポート役としてよく知られていますが、実は資格を取るのがかなり大変です。介護福祉士や看護師、社会福祉士といった資格と実務経験がないと受験資格も得られず、試験も難しいのです。だからこそ、ケアマネージャーは信頼性が高い専門職として地域で重要視されています。仕事は大変でも、介護を必要とする人の人生に大きく寄り添える仕事です。