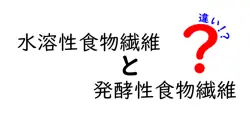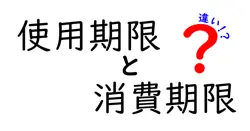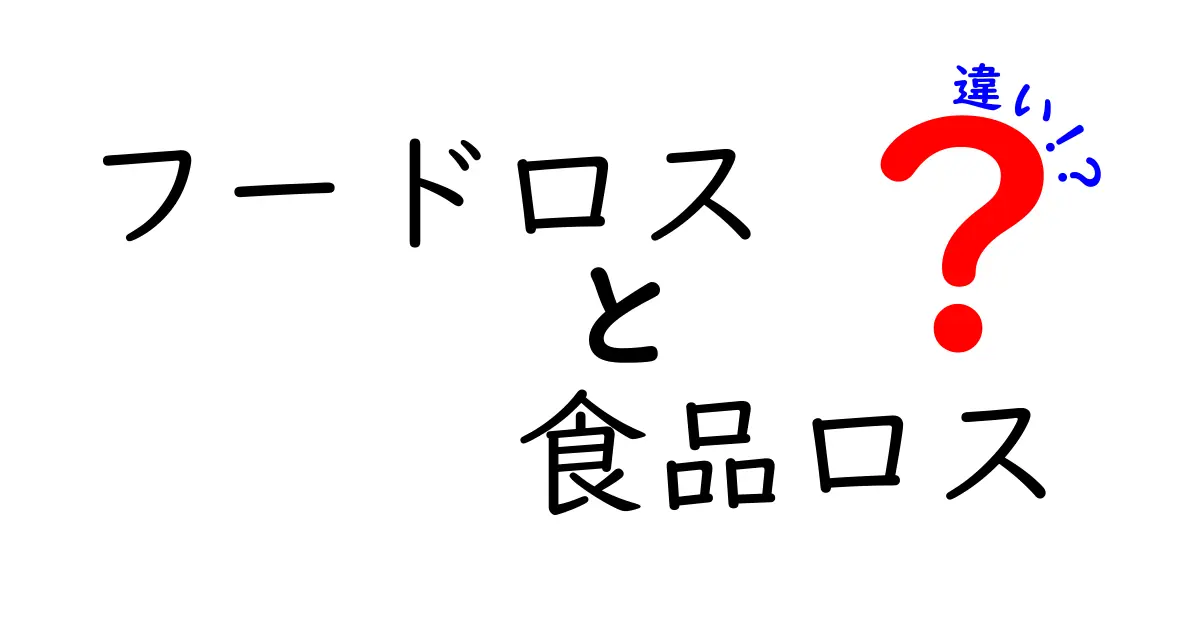

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
フードロスと食品ロスの基本的な違いと混同しやすい点
フードロスは英語のFood Lossを日本語に置き換えた言葉で、食べられる状態の食品が捨てられることを指します。つまり家庭での捨て物から農家の収穫過剰、製造ラインでの規格外品、輸送中の破損など、食べられる状態で廃棄される全ての場面を含むことが多いです。対して食品ロスは日本の行政や報道でよく使われる言葉で、食べられるかどうかに関係なく、食品が無駄になる全体の現象を指す広い意味の語です。ここで重要なのは、両者が同じ現象を指しているわけではなく、焦点が違うという点です。
この微妙な区別を理解すると、個人の行動だけでなく、企業の在庫管理、農業の計画、学校給食の仕入れ方など、社会全体の仕組みを見直すヒントが見えてきます。さらに、私たちが捨てずに済ませるための「ちょっとした工夫」がどれほど大きな影響を生むのかを想像してほしいのです。
例えば、賞味期限が近づいた食品を組み合わせて新しい料理に変える、規格外品を別の商品として再販する、家庭での買い物リストを作って過剰購入を防ぐ、これらの行動はすぐに結果につながります。これこそが身近な取り組みの力です。
日常の中での違いの見分け方と実践アイデア
家庭や学校、地域社会でどのように違いを見分け、何をすればよいかを具体的に考えていきます。まず見分け方としては、食品を廃棄する原因を「捨てるのが惜しい」「安全性の判断」「仕入れと在庫の管理」「価格の割引に対する反応」などの視点で分解します。
例として、同じキャベツが規格外で市場では売れず廃棄されるケースと、家庭で買いすぎて使い切れずに捨てるケースを比較します。前者は流通の仕組み、後者は個人の購買習慣の影響が大きいのです。ここで強調したいのは、「捨てる前に活用する選択肢」を常に探す姿勢が大切だという点です。
家庭での実践アイデアとしては、以下のような方法があります。
- 買い物前に食べきり計画を立てる
- 冷凍保存を活用して長く保存する
- 残り物を使ったレシピを増やす
- 規格外品や売れ残りを活用したSNS販売や共同購入
職場や学校での工夫としては、在庫と賞味期限の一覧化、献立の計画的な配分、余剰食材を共有する仕組みを作ることが挙げられます。教育の現場では子どもたちに「なぜ捨てるのがもったいないのか」を体感させるプログラムが役立ちます。これらの取り組みを続けると、消費者の意識が変わり、社会全体でのロスが少なくなるはずです。
この表を見れば、同じ現象でも視点によって強調点が変わることが分かります。私たちは日常の小さな選択で大きな影響を生み出せます。今後も 具体的な方法を日常に取り入れていくこと が課題です。
ねえ、ニュースでフードロスの話、なんだか難しそうに思えるよね。でも僕は最近、身近な工夫で大きく変わると感じ始めたんだ。買い物のときに「使い切れる量を選ぶ」こと、セール品を安易に買いすぎないこと、余った食材を別の料理に変えること。これだけで捨てる食品が減る。友達と一緒にやってみると楽しい気分にもなって、自然とエコな行動が習慣になる。結論は単純で、日々の選択が未来の食料ロスを決めるのだ。