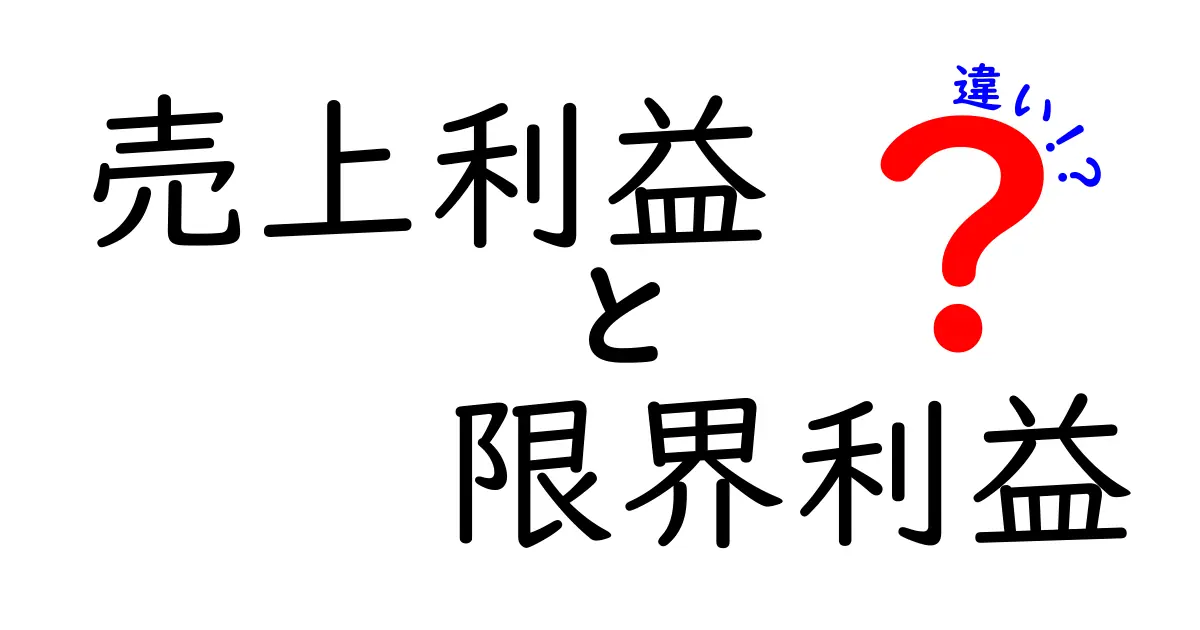

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
売上利益 限界利益 違いを徹底解説!中学生にも伝わるやさしい解説と実例
\みなさん、ビジネスの勉強をするときに「売上利益」と「限界利益」という言葉が出てきます。最初は難しく感じるかもしれませんが、実は身の回りの話題にも結びつく"利益の考え方"の違いを知ると、数字の意味がぐっと見えてきます。この記事では、売上利益と限界利益の違いを、できるだけやさしく、中学生でも分かる言い回しで解説します。売上利益は「売ることで得られる利益の総量」、限界利益は「追加で1つ商品を売るときに得られる利益の追加分」を指すと覚えてください。
実務ではこの二つを使い分けることで、価格設定や販売戦略、特別注文への対応などの判断が楽になります。
まずはお互いの意味を一つずつ固めてから、それぞれがどんな場面で役立つのかを見ていきましょう。
この先の説明では、身近な例を用いて具体的な数字を出します。難しい公式は最低限にして、イメージで理解できるように進めます。
さあ、売上利益と限界利益の違いを、簡単な言葉と図解で一緒に学んでいきましょう。
さらに、ビジネスの世界では「変動費」と「固定費」という区別も重要です。売上利益は材料費や直接人件費など、売上の量に連動して変わる費用を引いた後の利益を示すことが多いです。一方、限界利益は追加で1単位販売したときに変わる費用だけを引いた「追加の利益」です。これを理解すると、どうすればより効率的に利益を増やせるのか、という視点が見えてきます。
\売上利益とは何か?基本の考え方
\売上利益は、しばしば「売上高から売上原価を引いたもの」と説明されます。ここでいう売上高は、商品を売って得た総額のこと。売上原価はその商品を作るためにかかった直接的な費用です。たとえばパン屋さんが1枚100円のパンを100枚売ったとします。売上高は100円×100枚=1万円です。パンを作るのに必要な材料費や直接的な生産費用が合計で6千円かかったとすると、売上利益は1万円-6千円=4千円。この4千円が「売上利益」です。ここには、店舗の家賃や一般管理費など、売上に比例しない費用は含まれません。つまり、売上利益は"原価"に焦点を当てた利益の見方です。
この考え方は、商品の原価を下げる努力や、より安く仕入れる方法を考える際に役立ちます。
ただし、実務ではこの値だけを見てすべてを判断するわけではなく、固定費を別に考えることが大事です。
したがって、売上利益は「お店が何を売って、いくら原価を抑えられるか」という視点を持つときの基本指標として使われます。
この基本を押さえると、単に売上が増えたから良い、ではなく、どれだけの原価で商品の価値を作れるかを考える力がつきます。
さらに、複数商品の原価を比較することで、どの商品を増産・販売拡大の対象にするべきか、という判断にも役立ちます。
また、売上利益の数値だけでは判断できない場合もあります。例えば固定費が大きく影響して黒字化が難しい場合には、別の視点で見る必要があります。
このように売上利益は「原価と売上の関係をもとにした利益の目安」を示す重要な指標です。
限界利益とは何か?どう計算するのか
\限界利益は、追加で1単位販売したときの利益の増分を表します。英語で言うと contribution margin の考え方で、売上高から変動費を引いた額です。変動費には材料費、直接労務費、外部委託費など、その販売量に応じて増える費用が含まれます。たとえば、1個100円のお菓子を50個販売するとします。材料費が1個につき20円、包装費が5円、その他の変動費が5円とすると、1個あたりの変動費は30円、限界利益は100円-30円=70円です。50個売れば、合計の限界利益は70円×50個=3,500円になります。ここで重要なのは、限界利益は追加販売の判断材料になる点です。固定費(家賃、人件費のうち、売上の量に関係なく発生する費用)はこの加算分には含まれません。企業が特別な受注を受けるべきか、値上げで利益を確保できるかを判断するときに、限界利益はとても役立ちます。
また、限界利益を用いると「売上高をどれだけ増やせば固定費を賄い、黒字化できるか」のブレークイーブン分析が分かりやすくなります。
つまり、限界利益は「追加の販売がどれだけ会社の利益になるか」を直感的に示す指標です。
- \
- 定義:売上高から変動費を引いた額が限界利益です。 \
- 含む費用:材料費や直接労務費など、販売量に比例して増える費用が中心です。 \
- 使い方の場面:追加販売の判断、価格戦略、特別注文の可否判断に有効です。 \
- 固定費との関係:固定費は含まれず、別途ブレークイーブン分析などで活用されます。 \
以上を踏まえると、売上利益は原価の観点から「何を売るか」で利益を測る指標、限界利益は追加販売の判断材料として「いくら追加すれば黒字化に近づくか」を測る指標と覚えると、使い分けが自然に身についてきます。
\なお、現場ではこの二つの指標だけでなく、固定費の水準、資金繰り、需要の変動なども合わせて判断します。売上利益と限界利益を両方理解することで、より現実的で柔軟な意思決定ができるようになるのです。
\放課後、友だちと雑談していたときのこと。限界利益って、追加で1個売れたときのちょっとした“増え方”を示す指標だよね、という話題になりました。最初は難しく感じたけれど、私たちは当日、駄菓子屋の例を使って実演してみたんです。たとえば100円のお菓子を1個売ると、材料費が20円、包装費が5円、その他の変動費が5円なら、限界利益は70円。もしこのお菓子を追加で10個売ると、追加の利益は700円。こうやって“追加販売の価値”を見える化すると、店の向きを変えるヒントが見つかるんだよ。変動費が高い商品なら限界利益が小さく、安い材料で作る商品は大きくなりやすい。だから、単に売上を追うのではなく、追加販売の価値を考える視点が大事。
次の記事: 売上利益と粗利の違いを徹底解説!初心者にも分かる基礎と使い分け »





















