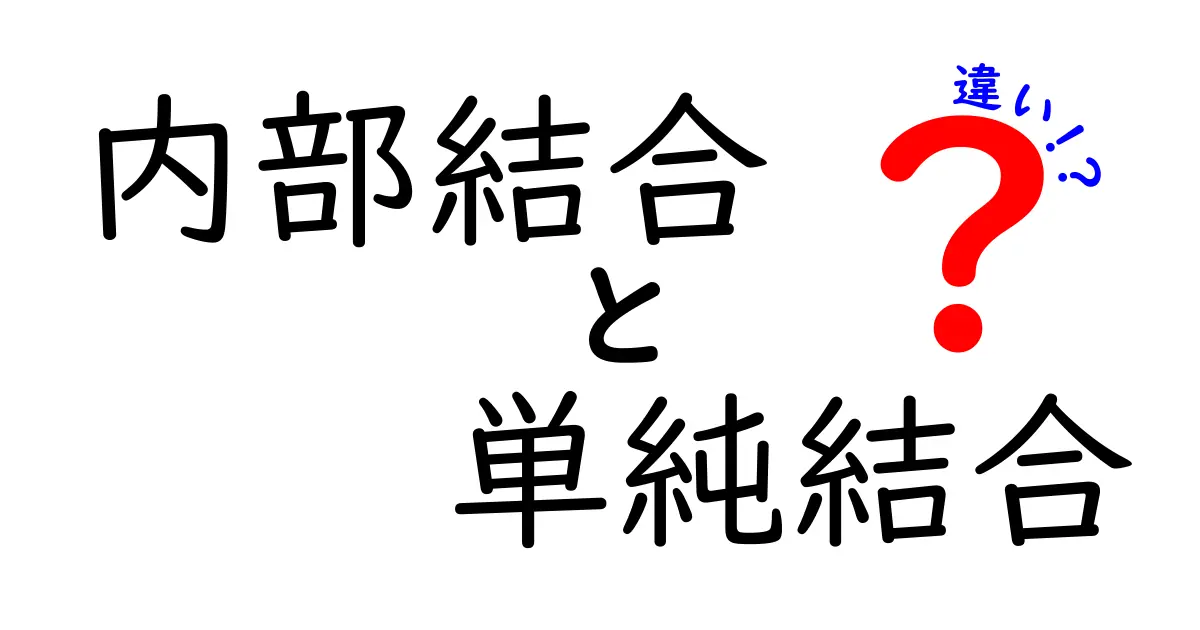

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
内部結合と単純結合の違いをわかりやすく解説
データベースの世界では、2つ以上の表をくっつけて情報を1つにまとめる作業を結合と呼びます。よく出てくる用語に内部結合と単純結合がありますが、これらは使われる場面で意味が少し変わります。まず、内部結合(Inner Join)とは、結合条件を満たす行だけを取り出す結び方です。たとえば、学生の表と成績の表があり、それぞれの表に共通の列としてstudent_idがあるとします。student_idが両方の表に存在する行だけが結果として残ります。つまり「両方に存在する情報だけを結ぶ」という性質です。次に単純結合という言葉は、日常の説明で「とりあえず結ぶ」という意味で使われることがあります。厳密にはテーブルの結合の種類を指す標準用語ではなく、話し方の中で“特定の結合の種類を意識せずに結ぶ”ことを表すことが多いです。結果として、単純結合と内部結合が混同される場面もあります。ここでは、初心者の人が混乱しないように、それぞれの基本を丁寧に整理します。
この違いを理解するコツは、まず「どのキーで結ぶのか」を決め、次に「取りたい情報の範囲はどこまでか」を決めることです。内部結合は共通キーが両方の表に現れる行だけを取り出す動きで、表Aと表Bの結び目がぴたりと合う部分だけを新しい表にします。単純結合については、文脈によって意味が変わる場合がありますが、日常会話では「結ぶこと自体」を指す場合が多く、場合によっては内部結合とほぼ同じ意味で使われることもあります。このように、同じ言葉でも使われる場面によって意味が変わる点に注意しておくと、後で混乱しにくくなります。
内部結合とは?しくみとポイント
内部結合は、2つの表を結ぶときに共通の鍵を基準にして、両方の表に「一致している行」だけを取り出す方法です。具体的には、表Aと表Bの各行を作業台のように照合して、結合条件が成立する場合にだけ新しい行を作ります。条件が複数ある場合でも、条件がすべて満たされる行だけが残ります。結果として、片方の表にしかないデータ(片側にしか無い情報)は消えてしまいます。これを現実の例で見てみると、学校の「生徒名簿(表A)」と「出席情報(表B)」を結ぶとき、生徒IDが一致する行だけが新しい一覧表に現れます。複数の出席情報が同じ生徒IDにぶら下がっていると、その生徒は複数の行として結果に現れることもあり、結合の仕方次第で重複が起きる点に注意が必要です。さらに、外部のデータが欠けている場合、内部結合はそのデータを含みません。つまり「結合に使うキーが両方にある場合だけ残す」という単純な原理です。
単純結合とは?具体的なイメージ
単純結合は日常の説明では「とりあえず結ぶ」という意味で使われることが多く、正式なSQL用語としては必ずしも決まった意味を持ちません。実務では、結合の種類を特に指定せず、共通キーで結ぶことを指す場合が多いです。その結果、内部結合と同じ動作になることもあります。たとえば、A表とB表を“同じID”で結ぶという話題なら、両方にIDがある行だけを取り出す、という点では内部結合と似ています。ただし、使う文脈やデータベースの仕様によって、左側の表にデータがない場合の扱い(NULLになるかなど)や、結合の許容範囲が変わることがあります。だから、単純結合という言葉を聞いたら、まずは“この場面での意味は何か”を確認するのが大切です。ここでは、混乱を避けるために「単純結合は結ぶことそのものを指すことが多い」が基本であり、必ずしも一つの結合タイプを意味しない、という理解を促します。
違いを表で整理する
ここまでの説明を表にまとめると、違いが見えやすくなります。まず、内部結合は「両方の表に共通する鍵がある行だけを拾う」という点が特徴です。次に、単純結合は話し言葉で使われることが多く、結ぶ対象や結果の範囲を特定しない場合が多いです。そのため、文脈次第で内部結合と同じ動作になることもあれば、異なる結合を前提にしていることもあります。次の表は、よくあるケースをシンプルに比較したものです。
表は次の通りです。
今日は友だちと雑談風に内部結合と単純結合の違いを深掘りしてみます。実は結合の考え方は、物事のつながり方を考える練習にも役立ちます。まず、同じ道具を使って同じゴールを目指すとき、道具Aと道具Bがきちんと『同じID』や『同じ名前』でつながると、作業はスムーズに進みます。ところが、AとBが完全に一致しないとき、結局はどの情報を残すべきか悩みます。内側だけを拾う内部結合は、こうした“一致するものだけを残す”という判断の良い例です。単純結合という言葉には“結ぶこと自体を指す”意味もあり、ケースによっては内部結合と同じ結果になることがあります。つまり言葉の使い方次第で、結び方の印象が変わるのです。私たちは用語に振り回されず、目的が何かを見失わないように、結び方のルールを自分の言葉で整理しておくといいですよ。





















