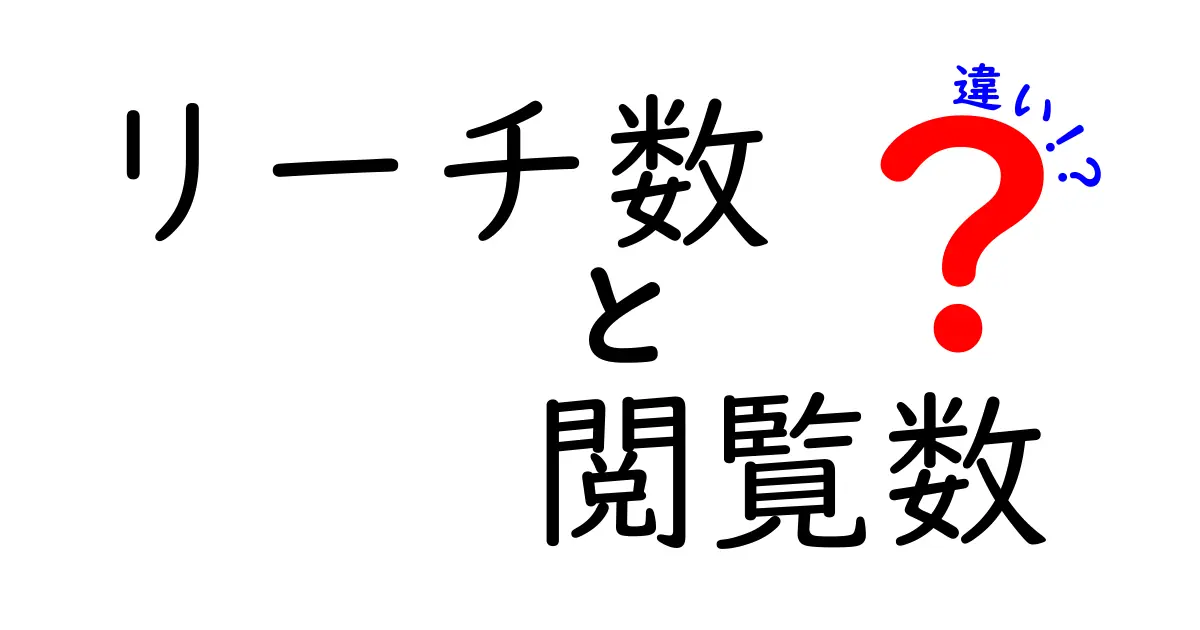

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
リーチ数と閲覧数の違いを知る基本
現代のデジタル社会では情報を発信する機会が増えていますが、ただ発信するだけでは十分ではありません。
どれだけの人に見てもらえたか、そして実際にどれだけの人が内容を読んだり見たりしたかを把握することが、効果的な発信につながります。
この2つの指標、リーチ数と閲覧数は似ているようで目的が異なります。
リーチ数は投稿を表示されたユニークな人数の目安であり、閲覧数は表示された回数の総量です。
この違いを正しく理解しておくと、施策の良し悪しを判断する基準が明確になり、改善の方向性が見えやすくなります。
以下では、それぞれの定義と実務での活用方法を、初心者にもわかるように丁寧に解説します。
リーチ数とは何か
リーチ数は投稿を表示されたユニークな人数のことを指します。
つまり同じ人が何度表示を見ても、リーチ数は1としてカウントされます。この性質のため、リーチは「どれだけ広く人の目に触れたか」という到達範囲の指標として用いられます。
実務では、キャンペーンがどれだけ新しい人に届いているかを測るための基本指標として重要です。たとえば広告を出した場合、リーチが大きいほど新規ユーザーへの到達が多いと判断でき、予算の配分やクリエイティブの見直しのヒントになります。
ただしリーチだけではエンゲージメントの強さは分かりません。リーチが大きくても閲覧数が低い場合は、投稿内容の魅力やタイミングに改善の余地があるというサインかもしれません。
閲覧数とは何か
閲覧数は表示回数の総計を指します。
同じ人が何度もその投稿を開けば、その都度カウントされます。閲覧数は「このコンテンツがどれだけの回数視聴・閲覧されたか」を表すため、内容の魅力や継続的な関心を測るのに適しています。
文章、動画、画像など形式を問わず、閲覧数が高いほど視聴者の関心を引く力が強いと考えられます。
しかし閲覧数が高くてもエンゲージメントが伴わない場合、視聴者の関心が一過性である可能性もあるため、他の指標と組み合わせて解釈することが大切です。
違いを日常の運用にどう活かすか
リーチ数と閲覧数をどう使い分けるかは、目的次第です。
新規層の獲得を重視するならリーチ数を追うべきです。広く届くほど新しい視聴者の母集団が増え、ブランド認知の向上につながる可能性が高くなります。
一方で、投稿の質や深さを評価したいときは閲覧数と合わせて滞在時間、クリック率、再生時間、完読率などの指標を見ます。
また期間を統一して比較することも重要です。月間のリーチと閲覧数を同じ条件で比較すると、キャンペーンの波及力と定着力の両方の傾向を読み取れます。
最後に重要なのは、リーチだけでなくエンゲージメント率を確認することです。リーチが多くても、反応が薄い場合はメッセージの伝わり方を見直す必要があります。
表でわかりやすく比較
この表はリーチと閲覧の違いを一目で比較するためのものです。
リーチは到達範囲の大きさを示す指標であり、閲覧数は関心の深さと視聴量を示します。
両者を合わせて解釈することで、施策の強みと弱みがはっきりします。実務では日付をそろえ、同じキャンペーン内で同時に両方の数値を追跡すると、波及と定着の両方の傾向を読み取れます。
以下の表を参考にして、あなたのデータ分析にも役立ててください。
ある日の放課後、友だちと雑談でリーチと閲覧の違いの話題になった。彼は『リーチは誰に届いたかの人数、閲覧は実際に読んだ人の回数だよね』とつぶやき、僕は頷いた。僕らの学校の文化祭の告知を例にとって考えると、リーチはポスターを見た生徒の数、閲覧数はその告知をオンラインで実際にクリックして内容を確認した回数に近い。リーチが大きいほど注目度は高いが、閲覧数が低いと「伝わっていない部分」もある。逆に閲覧数が多くてもリーチが小さい場合は、限られた層だけが深く見ている状況だ。こうした現象を理解すると、次の告知では見せ方を変えるきっかけになる。私たちは友達と『リーチと閲覧、両方を意識して発信する』という新しいルールを作り、実際のポスターとSNSの併用を試してみることにした。私はデータを日付ごとに記録し、どの戦略がリーチを伸ばし、どの戦略が閲覧数に効果を出すかをメモした。結果的には、見出しの工夫と誘導文の改善がリーチと閲覧の両方に寄与することを体感した。さらに大事なのは、数字は“生の物語”だと捉えること。データは人々の関心の変化を映す鏡であり、私たちの発信の方向性を教えてくれる。





















