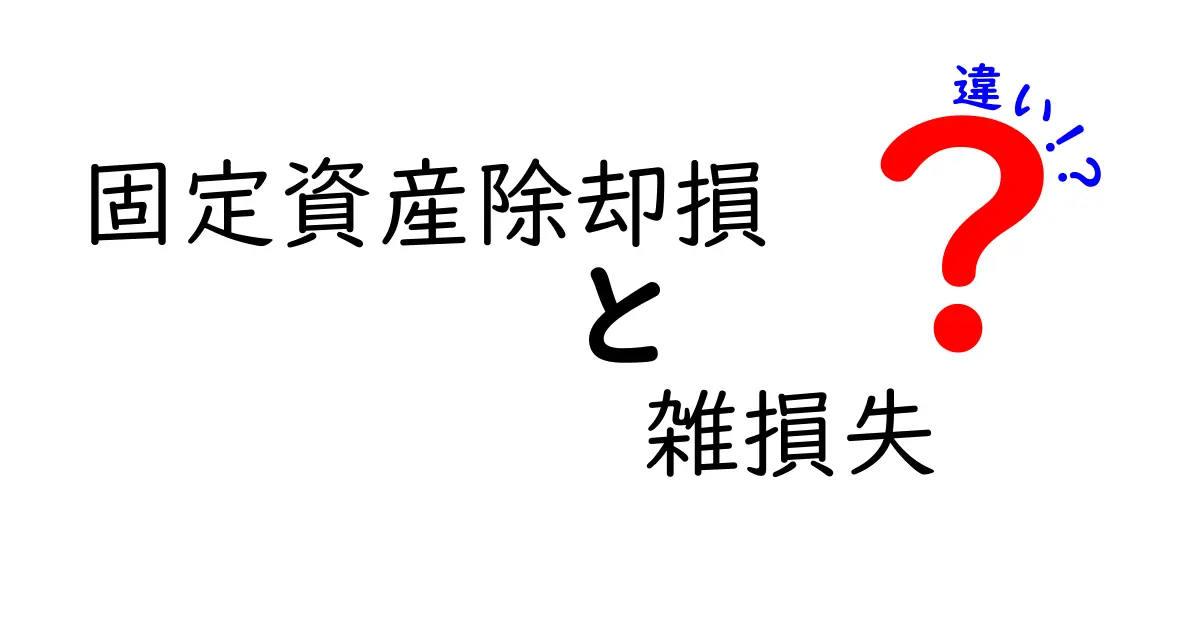

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
固定資産除却損とは何か?
固定資産除却損(こていしさんじょきゃくそん)とは、会社や事業で使う建物や機械、車などの固定資産を壊したり、取り壊したりした時に発生する損失のことです。
例えば、古くなった工場の機械を捨てた時に、その機械の価値が簿価(帳簿に記録されている価値)よりも減っていれば、その差が固定資産除却損として計上されます。
つまり、固定資産除却損は会社の資産の価値が下がった時の損失を計算するものとして使われます。
この損失は主に会計上の処理であり、税務上でも特に重要な扱いを受けることが多いため、正しく理解しておくことが大切です。
雑損失とは何か?
雑損失(ざっそんしつ)は、会社や個人が経営や日常生活の中で受ける、予測できない様々な損失のうち、特に他の分類に当てはまらない損失をまとめたものです。
例えば、火災や盗難による損害、風水害や偶然の事故による損失などが含まれます。
雑損失は、通常は貸借対照表の勘定科目以外の部分で取り扱われます。
事業以外の損失も含むことが多く、非常に幅広い項目です。
固定資産除却損と雑損失の違い
これら二つの損失は似ているようで、次のような違いがあります。
| 項目 | 固定資産除却損 | 雑損失 |
|---|---|---|
| 損失の対象 | 建物、機械、土地などの固定資産 | 建物以外の損失、災害や盗難、偶然の事故など |
| 発生の原因 | 固定資産の取り壊しや廃棄、価値の減少 | 災害、盗難、事故など予測できない様々な損失 |
| 会計の扱い | 固定資産の簿価減少を計上 | その他損失として計上 |
| 税務上の扱い | 一定の条件で損金算入が認められる | 損金算入の可否は原因により異なる |
要するに、固定資産除却損は資産の除却に限った損失であり、雑損失はそれ以外の様々な損失を含む広い分類です。
具体例で理解しよう
例えば、事業で使っていた機械を壊して処分したときは、その機械の簿価との違いが固定資産除却損になります。
一方で、工場が火事になって備品が燃えてしまった場合、その損失は雑損失として計上される可能性が高いです。
それぞれの損失の性質や原因をよく理解して、正しく会計処理をしましょう。
まとめ
固定資産除却損と雑損失は、損失の種類と対象が異なります。
・固定資産除却損は資産の取り壊しや廃棄による損失
・雑損失は固定資産以外の自然災害や事故などの損失
税務や会計で適正に処理するためには、この違いをよく理解し、適切に分類・計上することが重要です。
わかりにくい会計用語ですが、今回の記事が少しでも皆さんの理解に役立てれば嬉しいです。
固定資産除却損という言葉を聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は会社が使っている建物や機械を壊したり捨てたりするときの“損した分”を意味しています。これがなぜ損失になるのかというと、帳簿上の価値と実際に手放す時の価値が違うからです。面白いのは、ただ壊れたから損だけど、それは会計のルールでちゃんと記録しないといけない決まりになっていること。こうした細かいルールを知ることで、会社のお金の流れがもっと見えてきますよ。
次の記事: 控除と還付金の違いとは?税金の仕組みを簡単解説! »





















