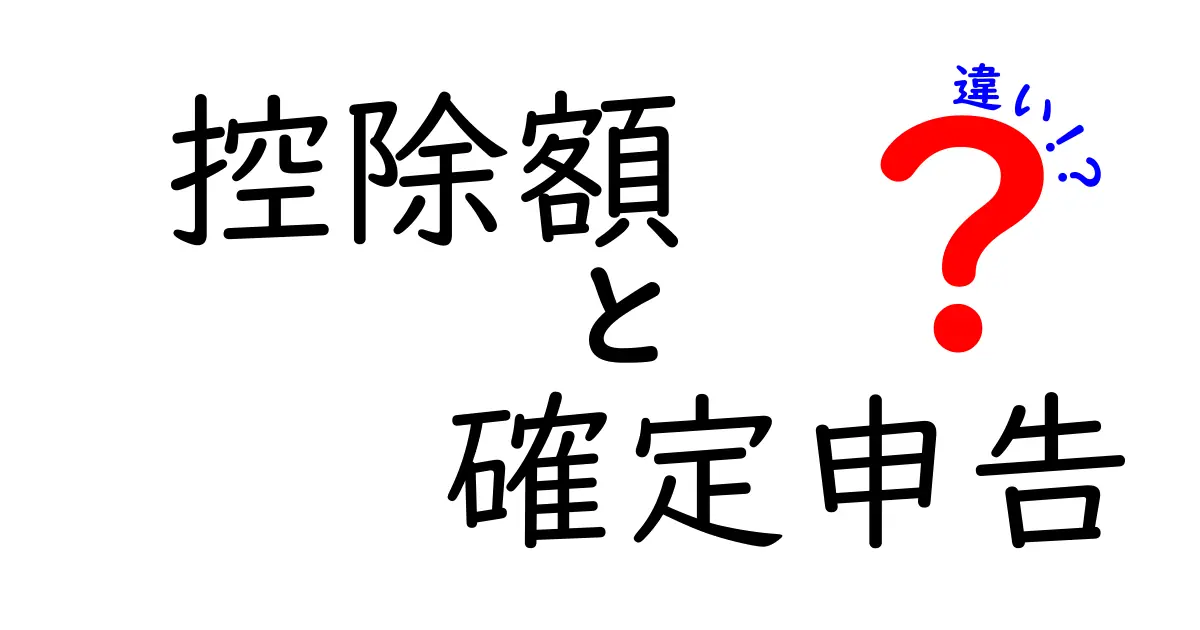

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
控除額と確定申告って何が違うの?基本を理解しよう
<税金の話になると、よく「控除額」と「確定申告」という言葉が出てきます。似ているようで実は全く違うものです。控除額は、払う税金を減らすための金額のことで、確定申告は、自分で1年間の収入や経費をまとめて税金を計算する手続きのことを指します。
簡単に言うと、控除額は「税金を少なくするためのルール」、確定申告は「その計算を自分で税務署に報告する作業」と覚えておくとわかりやすいでしょう。
この違いを正しく理解しないと、税金が多く取られたり、申告し忘れてトラブルになることもあります。そこで今回は、控除額と確定申告の違いを中学生でもわかるように詳しく解説します。
控除額とは?税金を減らすための仕組みを詳しく説明
<控除額とは、所得税や住民税を計算するときに、税金の対象になる収入から差し引ける金額のことです。つまり、控除があるおかげで、税金を払う金額が少なくなります。
控除にはいくつか種類があり、主なものは以下の通りです。
- <
- 基礎控除:全員に適用される最低限の控除額 <
- 配偶者控除:配偶者がいる場合にもらえる控除 <
- 扶養控除:子どもや両親など扶養家族がいる場合の控除 <
- 医療費控除:1年間の医療費が一定額を超えた場合に申請できる控除 <
- 社会保険料控除:支払った健康保険料や年金の控除 <
例えば年収が300万円でも、基礎控除や社会保険料控除が引かれて課税所得が200万円になる、つまり税金は200万円に対してかかる仕組みです。
控除は税金の計算をする上でとても重要で、知っておくことで税金の負担を減らすことができます。<
確定申告とは?自分で税金を計算して申告する手続き
<一方、確定申告は、自分の1年間の所得や控除額をまとめて税務署に申告し、税金を正確に計算してもらう手続きです。確定申告をすることで、余分に払った税金が戻ってくる場合もありますし、逆に不足分を払うことにもなります。
確定申告が必要な人は、主に次のようなケースです。
- <
- 自営業やフリーランスの人 <
- 給与以外に収入がある人 <
- 複数の会社から給与をもらっている人 <
- 医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人 <
給与所得者でも年末調整で処理しきれない控除がある場合は確定申告が必要です。
確定申告には「申告期間」があり、毎年2月中旬から3月中旬までに行います。この期間を過ぎると延滞税がかかることもあるので注意が必要です。<
控除額と確定申告の違いをわかりやすく表で比較
<まとめ:控除額と確定申告のポイントを押さえよう
<控除額は税金を計算するときに差し引ける金額のことで、税負担を軽くするためのものです。確定申告は、その控除額や収入などを税務署に自分で報告する手続きで、特に自営業者や副収入がある人に必要です。
どちらも税金に関わる大切な知識なので、無理に覚える必要はありませんが、仕組みをしっかり理解しておくと、税金を正しく納めたり戻ってきたりするのに役立ちます。
特に医療費控除や住宅ローン控除など、知っているとお得な控除もたくさんあるので、確定申告の時期が近づいたらぜひしっかり準備しましょう。
控除額の中でも「医療費控除」は意外と知られていませんが、とても役立つ控除です。たとえば、1年間で病院にかかる費用が一定額以上かかった場合、その超えた分を税金から引ける制度です。風邪で何度も病院に行ったり、薬をたくさん買ったりした年はチャンス!ただし、申告しないと控除は受けられないので、病院の領収書は確定申告まで大切に取っておくのがポイントです。
次の記事: 基礎控除と所得控除額の違いをわかりやすく解説!税金がどう変わる? »





















