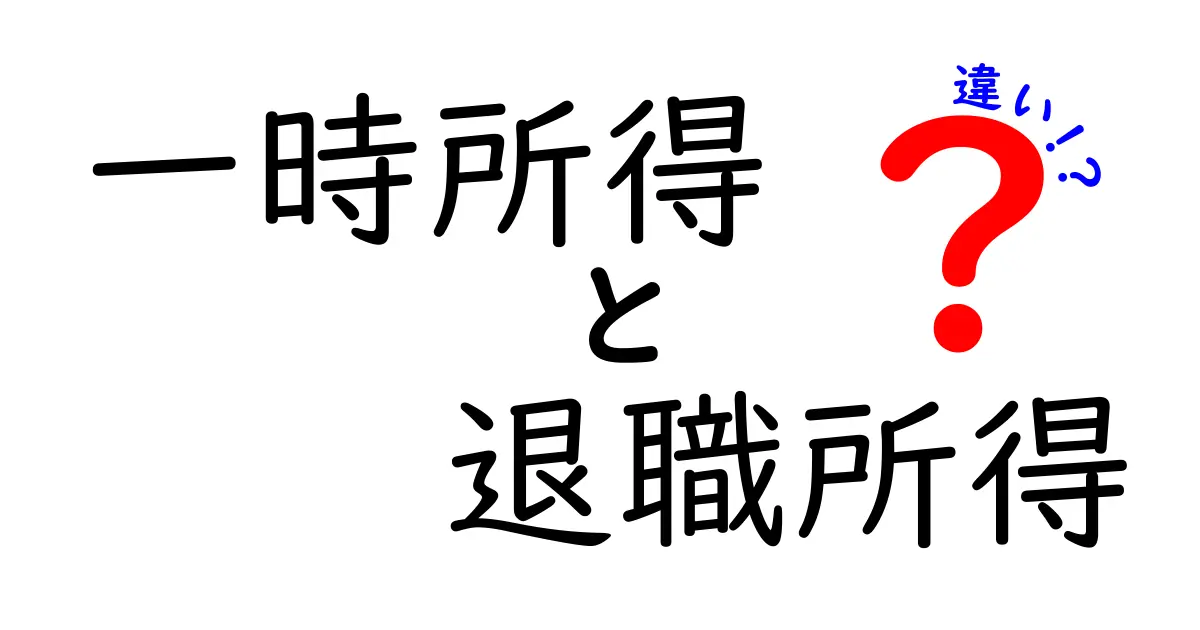

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
一時所得と退職所得とは何か?
税金を考えるうえで、「一時所得」と「退職所得」はよく出てくる言葉です。しかし、この2つは似ているようで実は全く違うものです。中学生のみなさんでもわかるように、一時所得は突然に得た一時的なお金、退職所得は会社を辞める時にもらうお金と覚えておきましょう。
一時所得は宝くじの当選金や懸賞金、保険の満期金など、普段の働き以外で一度だけ得られる収入のことを言います。
一方、退職所得は会社を退職するときに受け取る退職金や功労金などで、労働の対価として支払われるまとまったお金のことです。
この2つはどちらも税金の課税対象ですが、扱い方が異なるため混乱しないように違いをはっきり理解することが大切です。
一時所得と退職所得の税金の計算方法の違い
一時所得も退職所得も所得税の対象ですが、税金の計算方法が違います。
- 一時所得の計算方法:『収入金額-(必要経費+50万円の特別控除)』で計算されます。つまり、得たお金からかかった費用と50万円を差し引いた残りが課税対象です。
- 退職所得の計算方法:『(収入金額-必要経費)÷2-勤続年数×40万円』となります。ここで特に注目すべきは勤続年数×40万円の控除と、収入の半分だけが課税対象になることです。
税務署は退職金に対して長く勤めたことへの報奨という意味合いを強く持っています。だからこそ所得税が軽くなる計算がされているのです。
以下の表で整理します。
一時所得と退職所得での節税ポイント
この2つの違いを知っておくと、節税につながることがあります。
一時所得の場合、50万円の特別控除があるため、少額なら税金がかからないこともあります。特に保険の満期金などを受け取るときは、50万円以下なら申告不要になる場合が多いです。
退職所得の場合は勤続年数が増えるごとに40万円ずつ控除額が増えるため、長く働くほど税金が軽くなります。会社を辞める時に受け取る退職金はこの優遇があることをしっかり理解しておきましょう。
また、どちらの所得も確定申告のタイミングで正しく申告することが重要です。税金のプロである税理士に相談するのも安心です。
これで、「一時所得」と「退職所得」の違いと節税ポイントがよく分かったと思います。知識を持って賢くお金を管理しましょう!
「一時所得」のなかでも特に面白いのが、保険の満期金です。これは例えば、一定期間保険に入っていたら受け取れる一時金ですが、このお金は税金がかかるかどうか心配になりますよね。実は、50万円の特別控除があり、満期金から必要経費を引いて、その差額が50万円以下なら税金がかかりません。つまり、保険を上手に利用すると、ちょっとしたお金の受け取りで税金を節約できるというわけです。この仕組みは意外と知られていないので知っておくと得です。
前の記事: « 無申告と申告漏れの違いを徹底解説!知らないと損する税金の基本





















