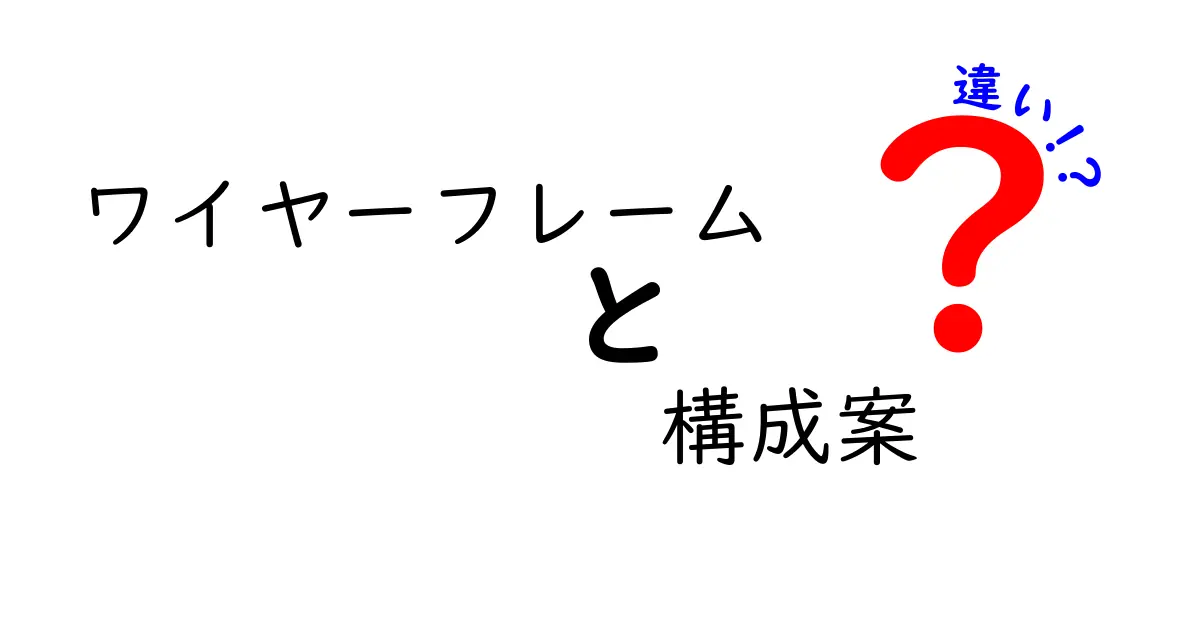

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ワイヤーフレームと構成案の違いを正しく理解する
ワイヤーフレームとは、Webページやアプリの画面の“骨組み”を示す設計図のようなものです。実際の色やフォント、写真などのデザイン要素は置かず、どこに何が配置されるか、どの機能がどこにあるかを視覚的に並べます。この段階では「情報の順序」「操作の導線」「主要機能の有無」といった点を中心に検討します。低忠実度のものが多く、手書きのスケッチや簡易なデジタル図として作成されることもあります。ワイヤーフレームの最大の利点は、初期段階での共通理解を作れる点と、UIデザイナーとエンジニアが同じ言葉で話せる点です。これにより、実際のデザインへスムーズにつなげられます。
また、変更がしやすいので、検討の回数を増やしやすく、コストを抑えつつ基本設計を固めるのに役立ちます。
この段階での失敗は後で大きな修正につながりやすいので、要素同士の関係性、優先度、相互作用を明確にしておくことが重要です。
ワイヤーフレームの特徴と目的
ワイヤーフレームの主な特徴は、見た目の美しさよりも構造に焦点を当てる点です。画面上の部品の位置、サイズ感、配置関係を示し、情報の階層と操作の導線を把握します。目的は、情報を「どう伝えるか」を決めることと、関係者の認識をそろえることです。実務では、紙、ホワイトボード、PowerPoint、Figma、Sketch、Balsamiq など、さまざまな道具を使いますが、いずれも設計の共有を最優先に置き、後工程のデザイン作業をスムーズにします。ワイヤーフレームを通じて、クライアントの要望が技術的に実現可能かどうか、開発のリスクはどこにあるかを早めに見極めることができます。
さらに、複雑な対話や新機能の追加があっても、最初にレイアウトを決めておけば、後からの変更が比較的容易です。
この段階での判断は、プロジェクト全体の進行に大きな影響を与えます。
構成案の特徴と目的
構成案は、サイトやアプリ全体の情報設計・ナビゲーション設計の設計書です。ここでは情報の階層、ページ間の関係、検索・ブロー制度などの全体像を整理します。目的は、ユーザーが目的の情報にたどり着くまでの“道筋”を明確化し、検索エンジンや社内の開発者にも理解しやすい形にすることです。実務では、情報のカテゴリ分け、メニュー構造、パンくずリスト、検索機能の挙動、ページの役割を文書化します。構成案は、情報アーキテクチャを作る作業であり、UIデザインの前提条件を整える役割を担います。これにより、デザインと実装の整合性が高まり、将来の拡張にも耐えやすくなります。情報の正確さと再利用性を高めるためのこの作業は、長い目で見ればコスト削減にもつながります。
情報設計が不十分だと、後の変更が難しく、ナビゲーションの混乱や検索の非効率につながります。そうならないように、構成案ではカテゴリの整理、ページ間の関係性、検索機能の仕様を丁寧に決めていくことが大切です。
違いを踏まえた使い分けと実務のポイント
ワイヤーフレームと構成案は、目的とタイミングが違います。前者は画面の骨組み・導線、後者は情報の整理と全体の構造です。実務では、両方を併用することでリスクを減らせます。以下のポイントを押さえると良いです。
- 初期段階の共通理解を作るために、まずはワイヤーフレームで画面の配置を決める。
- 続いて構成案で情報の階層とナビゲーションを整え、全体像を共有する。
- 成果物を段階的に分け、関係者が同じ言葉で話せるようにする。
- ツールは用途に合わせて選び、変更履歴を残せる体制を作る。
- リスク管理と変更管理を事前に計画しておく。
以下は要点をまとめた比較表です。この表を見れば、どの作業を先に行うべきかがすぐ分かります。
こんにちは。今日はワイヤーフレームと構成案の違いを、雑談風に深掘りしてみます。私たちはどうしてこの二つを別物として考えるのか、現場の実務でどう使い分けるのかを、友達とカフェで話している場面を想像して読んでください。まず、ワイヤーフレームは“画面の骨格”です。ボタンがどこに来るか、見出しが何階層になるか、リンクのつながりはどうなるか—そんな“見た目より機能の配置”を決めます。対して構成案は“サイト全体の地図”で、どのページで何を見せるか、どんな順番で情報を並べるかを整理します。つまり、ワイヤーフレームが個々の画面設計なら、構成案は全体の情報設計です。実務では、まずワイヤーフレームで画面の使い勝手を仮決定し、そのあと構成案で情報の階層と導線を整えるのが鉄板です。これを同時に進められると、クライアントの要望と技術的な現実のズレを早く埋められます。知っておくと便利なのは、両者は互いを補完する存在だということ。ワイヤーフレームだけでは「見た目だけの設計」になりがちですが、構成案を足すと「何を優先すべきか」「どの順番で見せるべきか」が明確になります。私の経験では、雑談の中でこの二つを同時に整理すると、誰もが同じイメージを共有しやすく、会議の時間を大幅に短縮できました。だから、次のプロジェクトでは、最初の会議でワイヤーフレームと構成案の両方をサポートする“共通の地図”を作ることをおすすめします。
次の記事: クリック率と読解を変える! h1タグとh2タグの違いを徹底解説 »





















