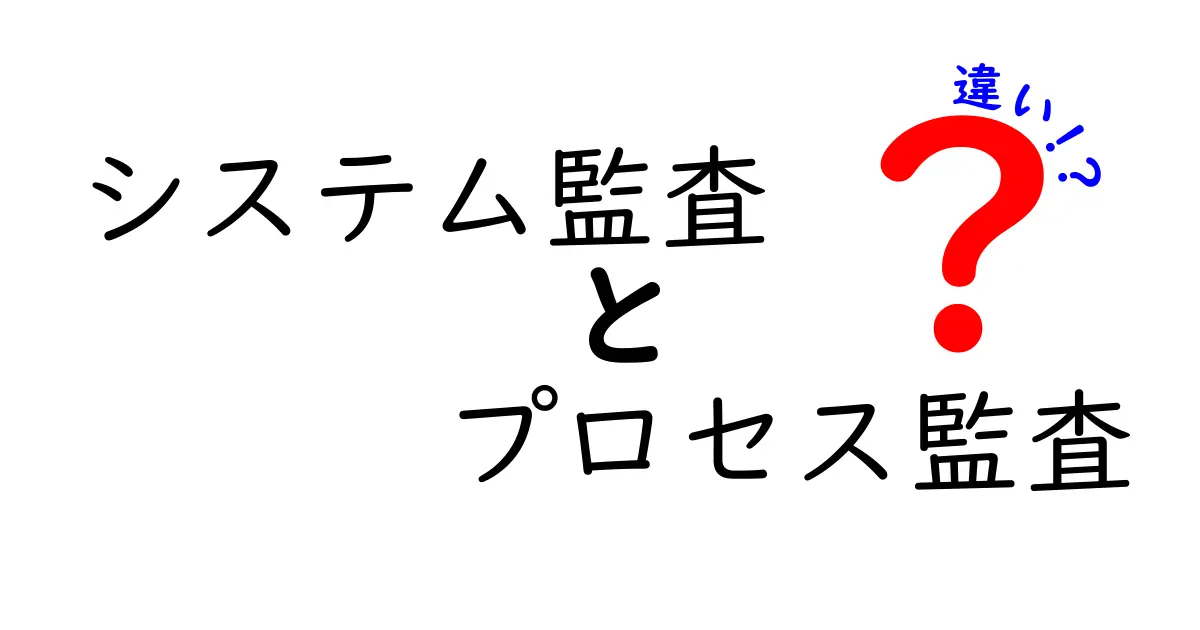

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
システム監査とプロセス監査の違いをわかりやすく解説
「システム監査」と「プロセス監査」は、どちらも組織の情報を守るための監査ですが、目的と焦点が違います。システム監査は情報システム全体の設計・運用・統制の適切性を横断的に評価し、ITガバナンスの整合性、セキュリティ対策の有効性、データの取扱いの適法性、バックアップと災害復旧の準備状況、法令遵守の遵守状況などを見ます。これに対しプロセス監査は特定の業務プロセス、例えば受注から出荷、請求、顧客対応といった一連の流れや、変更管理、脆弱性対応、インシデント対応、サービス提供の現場実務の実行状況を詳しく検証します。つまり、システム監査は全体像の健全性を評価し、プロセス監査は日々の業務の手順と実務の質を検証する役割を担います。これらは互いに重なる部分も多いですが、監査計画を立てるときにはまずどの観点を優先するかを決めることが重要です。
例えば大規模な組織では、情報資産の守りを固めるシステム監査と、部門ごとの手続きの遵守と改善を追うプロセス監査の両方を同時に進めることで、リスクの見落としを減らすことができます。最後に、両者を適切に組み合わせるための基本的な考え方として、証拠収集の計画、評価基準の共有、監査報告の読み手を意識した表現の工夫が挙げられます。これらを意識することが、現場の混乱を避けつつ有益な改善を生む第一歩になります。
定義と焦点の違い
システム監査は「情報システム全体の信頼性と安全性を高めるための設計と運用の妥当性を検証する」という定義が基本です。ITガバナンス、セキュリティ統制、データ保護、災害対策、法令遵守の状況を横断的に把握し、組織のリスク許容度と整合しているかを判断します。対象はハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、運用手順、監視体制など広い範囲に及びます。証拠としては設定値の比較、ログ分析、テスト実施、現場観察などを組み合わせ、評価はリスクの高さと改善の優先度を示します。
一方のプロセス監査は「特定の業務プロセスの実務運用が定められた手順に従い、目的を達成するために有効か」を検証します。対象は業務の流れそのもの、規程・手順・役割分担・記録の整合性・透明性、記録の追跡可能性です。評価は手順の再現性、責任分担の明確さ、潜在的なリスクの識別と緩和、そして改善点の具体性に重点を置きます。これらの違いを把握することで、監査の焦点を適切に設定し、実務上の混乱を防ぐことができます。
適用範囲と対象
システム監査は組織全体のIT資産と統制の健全性を対象にし、情報システムがビジネス戦略に沿って機能しているかを評価します。システム構成、アクセス権限の管理、データの整合性、バックアップと復旧、監視と検知の仕組みがよくチェック項目として挙がります。これに対してプロセス監査は特定の業務プロセスに限定され、変更管理、ソフトウェアの開発プロセス、問題管理、インシデント対応、サービスデリバリの現場運用などを深掘りします。現場の手順書、作業日誌、担当者の意思決定の痕跡、顧客対応の記録などを横断的に確認し、適合性と有効性を測定します。つまり、範囲の広さと狭さが異なる二つの視点を同時に見ていくのが基本です。
実務での検証項目と手順
実務では、監査計画を作成する際に、対象領域を特定し、証拠の収集計画を立てます。システム監査では、設定値の検証、アクセス権の見直し、セキュリティイベントの傾向分析、バックアップの実テスト、復旧手順の実行テスト、法令遵守のチェックリストの適用などを行います。証拠としては設定ファイル、ログ、構成管理資料、監視レポート、外部監査の報告などを組み合わせ、客観的な評価基準に照らして判断します。
プロセス監査では、手順書と実際の作業の乖離を見つけることが重要です。変更管理の履歴、開発時の品質保証の記録、変更の承認プロセス、インシデント対応の再現性、作業者の役割と責任の割り当て、業務KPIの達成状況などを検証します。現場の聞き取りと観察も重要な証拠となり、データと事実の一致を重視します。
表での比較と実務のヒント
以下の表は、両者の観点を比較したものです。
この比較を用いれば、監査計画の優先順位づけや、報告書の構成をわかりやすく整理できます。実務では、監査の結果を受けて、組織のポリシー見直し、手順書の改訂、教育・訓練の実施、リスク対応の計画作成など、具体的な改善アクションへと落とし込むことが大切です。また、現場の声を聴くこと、異なる部門間の合意形成を促すこと、監査結果をKPIに落とし込むことなど、実務の使い勝手を良くする工夫も必要です。そうして初めて、監査が現場に受け入れられ、継続的な改善サイクルを回せるようになります。
ある日、友だちとゲームの話をしていたら『システム監査とプロセス監査って何が違うの?』と聞かれた。私は雑談の流れで、監査は建物のセキュリティをチェックするように、システム全体の安全性と統制を見極める作業と、個々の業務プロセスが適切に設計・運用されているかを検証する作業とに分かれる、という話をしました。実務では、証拠の収集方法、関係者へのヒアリングのコツ、手順と実際の運用のズレを記録する工夫を組み合わせていくことが大事です。二つの視点を同時に使うと、リスクも改善点も見つけやすく、結果として組織の安全性と効率が同時にアップします。





















