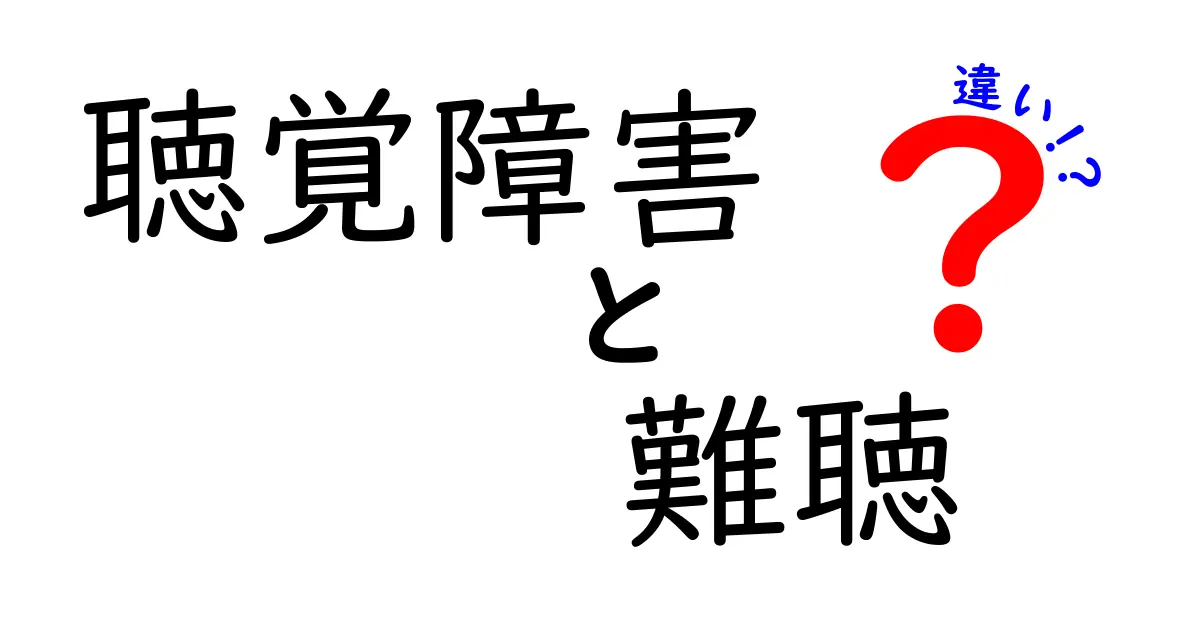

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:聴覚障害と難聴の基本を正しく理解する
聴覚は私たちの情報収集の大事な道具です。小さな音でも気づけるかどうかが生活の質を大きく左右します。聴覚障害は耳の構造や聴覚情報の処理に関わる障害を指す広い概念です。聴力検査の結果だけでなく、言語の発達・音声の認識・会話の理解といった実生活の影響まで含みます。対して難聴は聴力の低下を示す状態そのものを指し、軽度から重度、超重度など程度が分かれます。医療の場面では、聴力はデジベル聴取閾値で評価され、例えば軽度難聴はおよそ26〜40 dB HL、重度は71 dB HL以上とされます。日常生活では、聴覚障害をもつ人は音の大きさだけでなく、背景ノイズ・話者の発話速度・話し方の視覚情報(口元・表情)に左右されやすいのが特徴です。教育・福祉の場での視点は、単に聴力の数値だけでなく、情報アクセスの確保・コミュニケーション手段の提供をセットで考えることです。
この違いを理解することは、友人関係・学校生活・職場での適切なサポートを選ぶ第一歩になります。
ポイント整理:聴覚障害は広い概念、難聴は聴力低下の状態、支援は個人のニーズに合わせて選ぶ、という基本を押さえましょう。
この節では基本的な用語の違いを押さえ、日常生活と制度の両方の視点から理解を深めます。後続の節では、実生活の場面での違いを具体的に示し、表や事例を使って解説します。
聴覚障害と難聴の違いを実生活の場面で見る
この節では、日常の場面での違いを具体例とともに見ていきます。難聴は個人の聴力の状態を指すため、同じ難聴でも生活スタイルや支援の必要性は人それぞれです。強いノイズ環境では話の聞き取りが難しくなる一方で、静かな教室では話の内容を理解しやすい場合もあります。教育の現場では、字幕付きの講義、手話通訳、補聴器、音声強調設備など、さまざまな方法で情報アクセスを確保します。ここからは具体的な支援の差を表に示します。
この表はあくまで目安です。個人差が大きく、同じ「難聴」の人でも感じ方や必要な支援は異なります。情報アクセスの権利は誰もが等しくあるべきで、学校や職場、地域社会は、それぞれのニーズに合わせた環境づくりを進める責任があります。
この表を通じて、同じ「難聴」と呼ばれる場合でも、個人ごとに状況が大きく異なることを理解しましょう。教室や職場での情報アクセスを確保するには、相手の聴こえ方を知る努力と、必要な支援を提案する柔軟性が重要です。
難聴についての小ネタ:難聴は単に“音が聞こえない”という状態だけではなく、音の聞こえ方や情報の取り方が人それぞれ違う、という点が本当に面白いところです。ある友だちは補聴器で音の輪郭がはっきりして授業の会話を取りやすくなったと言います。一方、別の友だちは静かな場所での話し方や、口の動きを見て理解する工夫を続けています。難聴という状態を、支援技術と周囲の理解でどう日常に取り込むかが、コミュニケーションを自然に保つコツです。
次の記事: ろう者と聴覚障害の違いを徹底解説:誤解を解く基本と実例 »





















