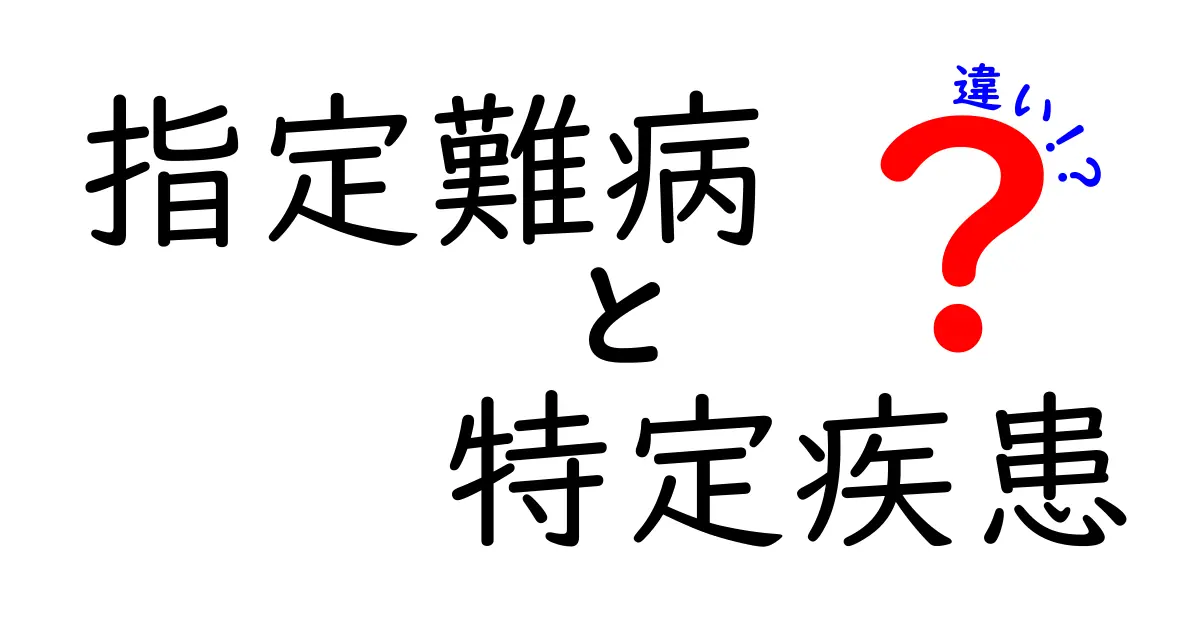

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
指定難病と特定疾患って何?
皆さんは「指定難病」と「特定疾患」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも難しい病気を指す言葉ですが、実は少し違いがあります。
まず、指定難病とは、厚生労働省が定めた特に難しく原因や治療法がまだ十分分かっていない病気のことです。これらの病気は専門的な治療が必要で、患者さんは治療費の助成を受けることができます。
一方、特定疾患も同じように難しい病気のことですが、こちらは指定難病の中でも特に国が指定して医療費の助成制度がある病気のことを指します。指定難病のうち、医療費助成の対象となるものを特定疾患と言うことも多いです。
簡単に言うと、指定難病は広い意味の難病のことで、特定疾患はその中でも医療費助成などに関わる病気のことです。
制度上の違いとポイント
制度面での違いを詳しく見ていきましょう。指定難病と特定疾患は見た目は似ていますが、申請や助成の枠組みが違います。
指定難病は2015年に難病法が施行されて以降、国が定めた病気のリストに基づき、患者の負担を減らすための制度です。指定難病の患者さんは医療費助成の対象となり、一定の自己負担額で治療が受けられます。
一方で、特定疾患という呼び方はそれ以前の制度である「特定疾患治療研究事業」から来ています。この制度は1982年から存在し、特に治療が難しい病気を指定して一定の医療費助成を行っていました。
つまり、昔の制度が特定疾患で、現在は指定難病という形に統一されたというイメージです。しかし、今でも「特定疾患」という言葉は制度名や書類で使われることがあり、混乱しやすいポイントでもあります。
下の表で違いをまとめてみました。
どうやって支援を受けるの?
指定難病の認定を受けることで、健康保険の自己負担額が軽くなり、医療費助成が受けられます。
制度利用のためには医師からの診断書や主治医意見書の提出が必要で、都道府県などの自治体が審査を行います。
申請が受理され指定難病患者として認められると、「医療受給者証」が交付されます。これにより医療費の助成がスタートし、患者さんの負担が大幅に軽減されます。
医療費の負担を減らすだけでなく、難病患者への理解を社会全体で深める役割もあります。
特定疾患という言葉が残る場合でも、現在は指定難病制度の枠組みで助成や支援が行われていることを覚えておきましょう。
まとめると、指定難病は現在の制度名で、特定疾患は以前の制度名から来た言葉です。制度が変わった歴史を知ることで、患者さんも混乱せずに助成を申請しやすくなります。
「特定疾患」という言葉は一見難しそうですが、実は昔の制度の名残なんですよ。1982年から始まった特定疾患治療研究事業の名前がそのまま使われ続けていることが多いです。今では2015年から「指定難病」という新しい制度に統合されましたが、書類などではまだ特定疾患という言葉を見かけることもあります。これが混乱のもとですが、覚えておくと行政手続きがスムーズにできるかもしれませんね。昔の名前が今も残る日本の制度の面白い一面と言えますね。
前の記事: « 医の倫理と医療倫理の違いとは?わかりやすく解説!
次の記事: 手術療法と根治療法の違いとは?わかりやすく徹底解説! »





















