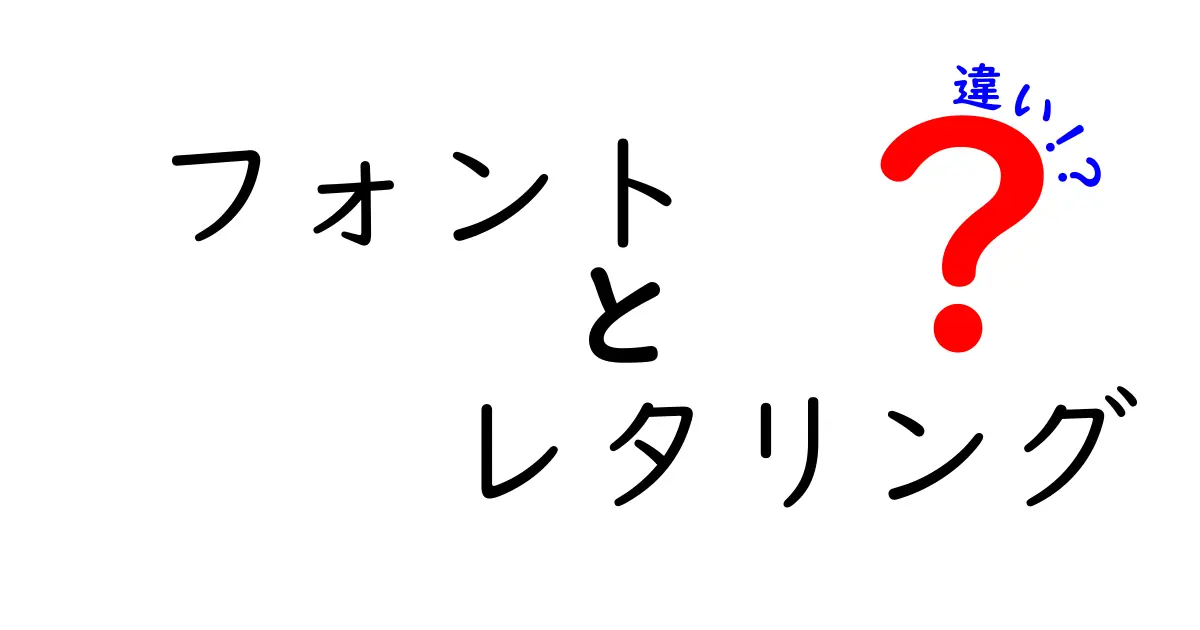

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
フォントとレタリングの違いを理解するための基本ガイド
文字の世界には「フォント」と「レタリング」という二つの言葉があります。似ているようで、役割がちがうため混同されやすいです。まず大事なのは、フォントはデジタルの世界の道具、レタリングは紙や画面に実際に描く技術と考えることです。
フォントはコンピュータの中に入っている「型の集合」で、太さ・傾き・間隔・字間などの情報が一つのファイルに詰まっています。あなたが文字を入力すると、ソフトはそのフォントの定義通りに文字を画面に表示します。
この仕組みのおかげで、同じフォントを使えばどんな文章でも同じ見た目になります。これはとても大きなメリットで、デザインの安定感を生み出します。
しかしフォントは万能ではなく、デジタルの決まりの中でしか表現できません。つまり、フォントは「型の標準化された表現」であり、個性を一から作ることは難しい場面もあります。
ここで覚えておくべきポイントは、フォントは“文字の形を決める道具”であり、文章全体のリズムや雰囲気はフォントの選び方で大きく変わるということです。
フォントとは何か?
フォントはデータとして存在し、コンピュータの中で「この字はこの形、太さ、間隔」という情報を持つファイルです。
たとえばArialやNoto Sansなどがそれです。
フォントを選ぶと、同じ文字であっても見た目が一変します。
フォントにはサンセリフ系、セリフ系、装飾系などの種類があり、それぞれ読みやすさや雰囲気が異なります。
覚えておきたいのは、フォントは一般的に「サイズの調整や互換性」をしやすく、ウェブや印刷物など、さまざまな場面で安定した見た目を提供してくれる点です。
フォントは文字の形のデータであり、デザインの土台となる要素です。
レタリングとは何か?
対照的にレタリングは、文字を実際に書くように描く作業です。
手で描くこともあれば、デジタルツールを使って自分だけの文字を作ることもあります。
レタリングは“個性”を強く表現できるのが魅力で、ロゴやタイトル、ブランドの看板など、世界に一つだけの文字を作るのにぴったりです。
手作業の温かみや、曲線の流れ、角の角度など、細かいニュアンスまで調整できます。
ただしレタリングは再現性が低く、同じ文字を再現するには同じ技術と時間が必要です。
実務で役立つ使い分けと表現のコツ
日常の授業プリントや学校のイベント告知でも、フォントとレタリングを上手に使い分けることで伝わり方が変わります。
以下のポイントを覚えておくと、デザインの失敗を減らせます。
まず、読みやすさを第一にする場面ではフォントを選びます。
見出しや強調したい部分には力強いフォントを使ってメリハリをつけ、本文には読みやすいフォントを選ぶと良いでしょう。
次に、ブランドやイベントの「個性」を出したいときはレタリングの出番です。
ロゴやタイトルなど、他にはない文字を作ることで印象が残りやすくなります。
最後に、表現の一貫性を保つために、同じ場面では同じフォントを使い、別の場面には別のフォントを使い分けるルールを作るとスムーズです。
ここまでの話をまとめると、フォントは「大量の文字を安定して表示する道具」、レタリングは「一つ一つの文字を丁寧に作っていく表現の技術」です。
学校のニュースレターを作るとき、フォントは見出しの太さをそろえ、本文は読みやすく整えます。
一方で、看板やロゴなどの特別な場面では、レタリングを使って個性を出します。
このバランスを意識するだけで、伝えたい内容がずっと伝わりやすくなります。
今後デザインの課題に直面したときは、まず「この場面はフォントでよいか、それともレタリングが必要か」を自問してみてください。
表を使った違いの整理
以下の表は、フォントとレタリングの基本的な違いを一目で比較するためのものです。
実務での選択の目安として活用してください。
この前、フォントとレタリングの話題で友達と長話をしました。フォントがデジタルの世界でどう動くか、レタリングが手作業でどんな温かさを生むか、実例を交えて雑談風に深掘りしました。フォントは文字の形と空白の配置の「設計図」で、誰が使っても同じ見た目になる安定感をくれます。一方、レタリングは筆運びや線の強弱を自分だけの癖として表現でき、看板やタイトルの「個性」を作る力があります。





















