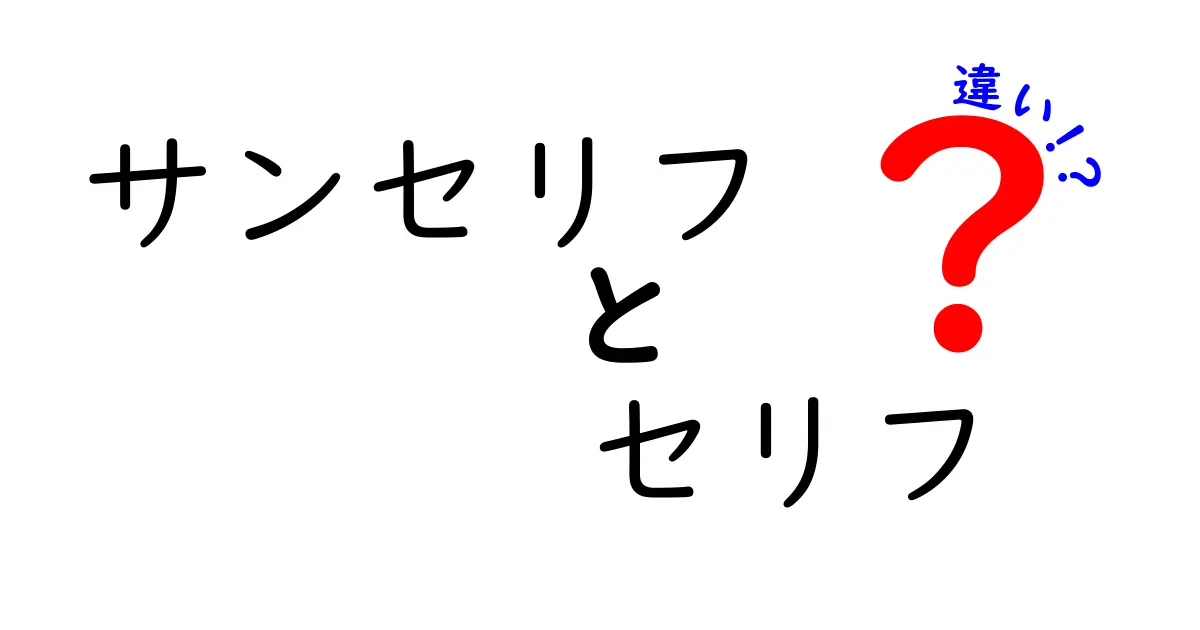

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
セリフとサンセリフの基本を押さえる
サンセリフとセリフはフォントの分類の基本です。セリフ、英語でserif、は文字の末端に小さな横線や装飾がつくタイプで、日本語では『セリフ体』と呼ばれることが多いです。反対にサンセリフは、末端の装飾がない『サンセリフ体』と呼ばれ、英語話者の間でも一般的な表現です。歴史的には活字印刷の時代にセリフ体が中心となり、長い文章の連続性を視覚的に支える役割を果たしてきました。しかしデジタルの時代が来ると、スクリーンでの読みやすさを優先する場面が増え、サンセリフ体が標準的な選択肢として広まっていきました。
なぜ読みやすさが変わるのかというと、セリフ体は文字の末端の小さな装飾が視線の運動を小さく抑え、段落ごとの行間を感じやすくする効果があるからです。長文を印刷物で読む場合、物理的な紙の質感やインクの色によっても影響を受けます。一方でサンセリフ体は装飾がない分、画面の解像度が低いと文字のエッジがかすれやすく、特に小さなサイズでは読みづらさを感じやすくなることがあります。現代のウェブデザインでは多くのサイトが本文に sans-serif を使い、見出しや強調する部分に serif を使うケースも見られますが、これはブランドの雰囲気や目的によって決まります。
以下の表を見て特徴を比べてみましょう
結論としては、完璧な正解はありません。読み手の環境、目的、ブランドのイメージによって最適な組み合わせを選ぶのがコツです。特にウェブでは、本文を sans-serif、重要なキャッチコピーや強調したい部分に serif を使うと、視線の動きと印象の両方をコントロールしやすくなります。フォント選びはデザインの初期段階で決めると後の作業が楽になるので、デザイン案を複数作って比較してみてください。
デザインと読みやすさの観点からの違い
デザインは見た目だけでなく雰囲気やブランドの声を作り出す重要な要素です。セリフとサンセリフはその雰囲気を最初の一瞬で決定づける力を持っています。セリフ体は伝統的でクラシックな印象を与え、信頼感や文学的なニュアンスを演出します。サンセリフは現代的でクリーン、デジタルの世界に合う直感的な印象を作ります。デザイン設計の初期段階では、この印象をチームで共有し、ブランドの目的に合わせて適切な組み合わせを決めることが大事です。
ウェブデザインの実務では、本文には sans-serif を使い、見出しや注目点には serif を使うなど、役割分担を明確にするのが定石として広まっています。こうすることで、長い本文の流れは読みやすく保ちながら、重要な語句やキャッチコピーには力強さと個性を付けることができます。フォントサイズ、行間、段落の余白なども、セリフとサンセリフの組み合わせに合わせて微調整します。
また、端末や解像度の違いを考慮することも忘れてはいけません。スマートフォンのように画面が小さいデバイスでは、サンセリフの方が小さな文字でもくっきりと見えやすい場合が多いです。一方で大きなスクリーンや紙の印刷物では、セリフが視線のリズムを作り出し、読書体験を滑らかにします。これらの点を踏まえ、デザイン案を複数作って実際の端末で確認することが成功のコツです。
実務での使い分けとコツ
実務的なコツとしては、まず本文は sans-serif を選ぶのが無難です。サイズは最低16px程度、行間は1.5倍程度を目安にします。見出しには serif か sans-serif のどちらを使うかはブランドの方向性次第ですが、読みやすさと統一感を優先すると良いでしょう。もしブランドが伝統的・格式高い印象を求めるなら見出しにも serif を取り入れ、モダンでフレッシュな雰囲気なら見出しも sans-serif に統一するといった判断が有効です。
実際の運用では、以下の点をチェックリストとして使うと失敗を防げます。第一にカラーバランスと背景のコントラスト、第二に本文の文字サイズと行間、第三に段落間の余白の統一、第四に重要な語句の強調方法(太字や色)を決めておくこと。第五に掲載するテキストの長さに応じて最適なフォント選択を複数案用意して比較することです。
最後に、デザインの一環として実サンプルを作ると理解が深まります。例えば同じ文章を serif と sans-serif で並べた比較ページを作り、読みやすさ、印象、ブランドの一貫性を自分の目で確かめるのが最も確かな方法です。
歴史と現代のウェブの現場
セリフ体の歴史は印刷機の時代にまでさかのぼります。活字が揃いにくかった時代、文字の終端に小さな装飾をつけることで文字同士の区別をつけ、読みやすさを高める工夫として生まれました。Times New Roman や明朝体はこの伝統を引き継いだ代表例です。対してサンセリフは19世紀後半から普及し、現代のデジタルや広告の世界で主役級の地位を得ています。
現代のウェブ現場では、読みやすさと表示速度、アクセシビリティが重視されるようになり、サンセリフの使用が圧倒的に増えました。Google のデザイン指針や多くの大手サイトの実践を見ると、本文に sans-serif を使い、適切なサイズと行間を確保する方が、スマホ時代には適しているという結論に落ち着くことが多いです。とはいえ、ブランドの個性を出すために見出しだけ serif を使うケースも多く、デザインの「組み合わせの美学」が評価されます。
このようにセリフとサンセリフは、それぞれの歴史と現代の要請を背景に共存しています。結局のところ、場面と目的と読者の環境を想定して、最適な組み合わせを選ぶことがベストな解決策です。技術が進む中でもフォントの選択はクリエイティブの核心であり、デザイナーと開発者が協力して初期設計を固めることが成功の鍵となります。
放課後のデザイン話で友だちとサンセリフとセリフの違いを深掘りしました。私はスマホの案内画面ではサンセリフが読みやすさのカギになると主張したのに対し、友だちは物語風の長文やクラシックな雰囲気を出す場面ではセリフ体が適していると反論しました。結局、結論はシンプル。読者層と媒体の特性を想定して使い分けるのが最善です。私は例として、ニュースアプリの本文は sans-serif、読み物の本文は serif を使うケースを挙げ、フォントの組み合わせが情報の伝わり方に影響することを体感しました。





















