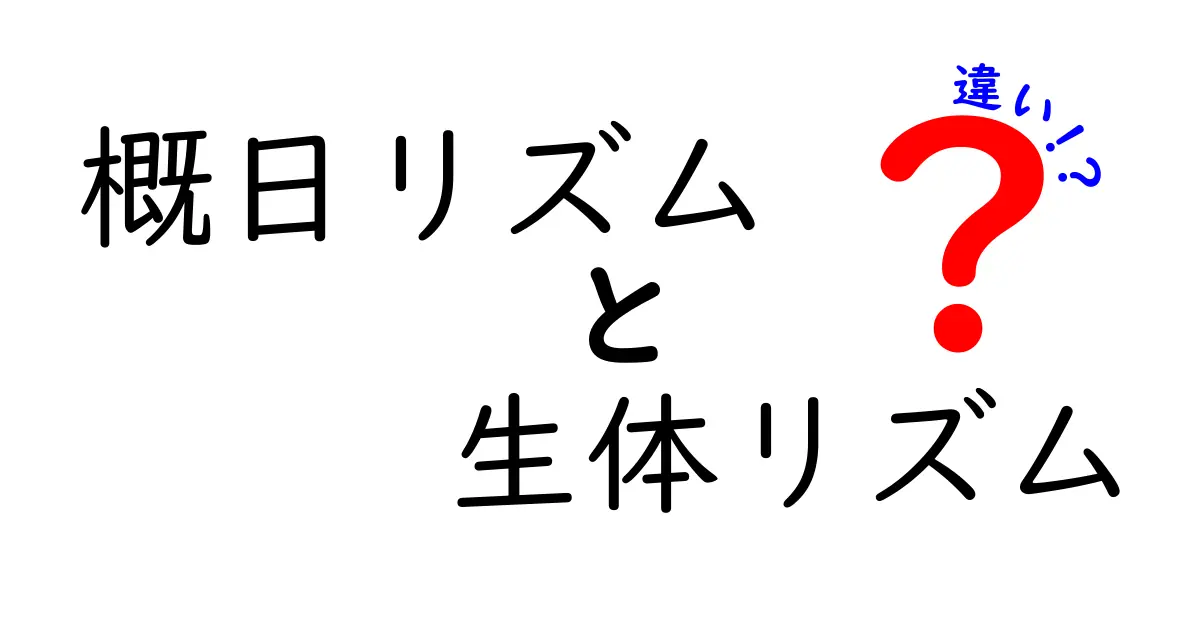

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
概日リズムと生体リズムの違いを理解するための基盤
人間の体には眠くなる時間や体温が高くなるタイミングなど、毎日同じように繰り返されるリズムがあります。このうち概日リズムと生体リズムはとても関係が深い言葉ですが、意味が混ざりやすいところです。概日リズムはおおよそ24時間の周期で体の機能を整える内なる時計のことを指します。これを司るのが脳の視床下部にある視交叉上核で、日光を感知することでリズムが整います。外の光の変化が時計に信号を送り、眠る時間や覚醒のタイミングを教えてくれます。つまり概日リズムは私たちの「体内の時計」で、外の世界の昼夜サイクルと連動して動きます。次に生体リズムという広い概念があります。
生体リズムは概日リズムを含む、体の中で起こる時間の法則の総称です。24時間より長い周期の睡眠サイクルや、数日〜数週間の周期で体の状態が変わる現象も含みます。だから生体リズムには睡眠だけでなく食欲、ホルモンの分泌、体温の変化、体の回復のタイミングなど、私たちの生活のさまざまな側面が関係しています。こうして考えると、概日リズムは生体リズムという大きな輪の中のひとつの輪っかであり、「24時間という周期を内側から作り出す仕組み」があると理解できます。
日常生活に現れる違いとは
実生活での影響を見てみると、朝起きる時間に体温が上がり眠気が現れ、同じ時間に眠ろうとする動機が高まることが多いです。概日リズムの乱れは時差ボケや夜勤、スマホの強い光などで起こりやすく、眠気と覚醒のタイミングがズレると日中の集中力が落ちたり気分が不安定になったりします。夜型の生活を強いられると全身のリズムがかく乱されることがあるため、規則正しい睡眠時間を守ることが大切です。日中は適度な日光を浴び、朝の光で時計を整え、夜は画面の明るさを控えることで内なる時計を安定させやすくなります。学校や部活動、家族の生活リズムと合わせる工夫をすると、睡眠の質が高まり体の回復も早くなります。
科学的な観点から見る違い
科学的には概日リズムは遺伝子の働きと外部の光によって調整されます。時計遺伝子と呼ばれるPERやCRYといった遺伝子が日々のリズムを作り、CLOCKやBMAL1といった別の遺伝子がその活動を組み合わせて24時間の周期を作り出します。これらの遺伝子の働きは睡眠だけでなくホルモン分泌、体温、代謝など全身の機能にも連動します。夜になるとメラトニンというホルモンが分泌され眠気を促し、朝には減少して目が覚めやすくなります。人間の体はこのリズムを守るために内なる時計を持っていますが、外部からの影響でリセットされることがあります。適切な光を浴びることは朝の光を浴びて時計を進め、夜には強い光を避けるという基本が重要です。ここで重要なのは、睡眠の質を高めることが日中のパフォーマンスを上げる鍵になるという点です。
表で整理して理解を深めよう
ここまでで概日リズムと生体リズムの違いの要点はつかめたと思います。表は要点を並べて比較しやすい形ですが、実際には体の中でこれらの仕組みがどう連携しているかを理解することが大切です。概日リズムは約24時間の周期を内側から推進する時計の役割を果たしますが、生体リズムはそのほかの長さの周期を含む総称です。日常生活への影響として眠気のタイミング、睡眠の質、ホルモンの分泌、体温の変化などが挙げられます。表を利用する際は自分の生活リズムを観察して記録すると、内なる時計の癖を知る手がかりになります。次の表はその理解を助けるまとめです。項目 意味 日常への影響 概日リズム 約24時間の内なる時計 内在性と外部情報の両方で調整 眠気のタイミング、体温、ホルモンの分泌など 生体リズム 生体の長さのリズムの総称 睡眠以外の周期、食欲、代謝、回復
ある日、友だちと夜更かしの話をしていて気づいたのは、概日リズムって実は私たちの体の時間割みたいなものだということ。日光を浴びると時計が動き出し、朝日を浴びないと眠気のタイミングがずれてくる。私の実験として朝の光を意識的に浴びる日と浴びない日を比べてみると、授業中の眠気や集中力が違って感じられた。つまり光を取り入れる小さな工夫が内なる時計を整え、学校生活の質を高める手助けになる。難しい研究用語よりも、日常の習慣を少し変えるだけで体のリズムを正しく働かせることができるのです。朝光を浴び、夜はスマホの光を控える、これだけでかなりリズムは整います。規則正しい生活を続けていくうちに、体の疲れにくさや気分の安定感が増していくはずですよ。
前の記事: « 正の強化と負の強化の違いを徹底理解!中学生にもわかる行動学の基本





















