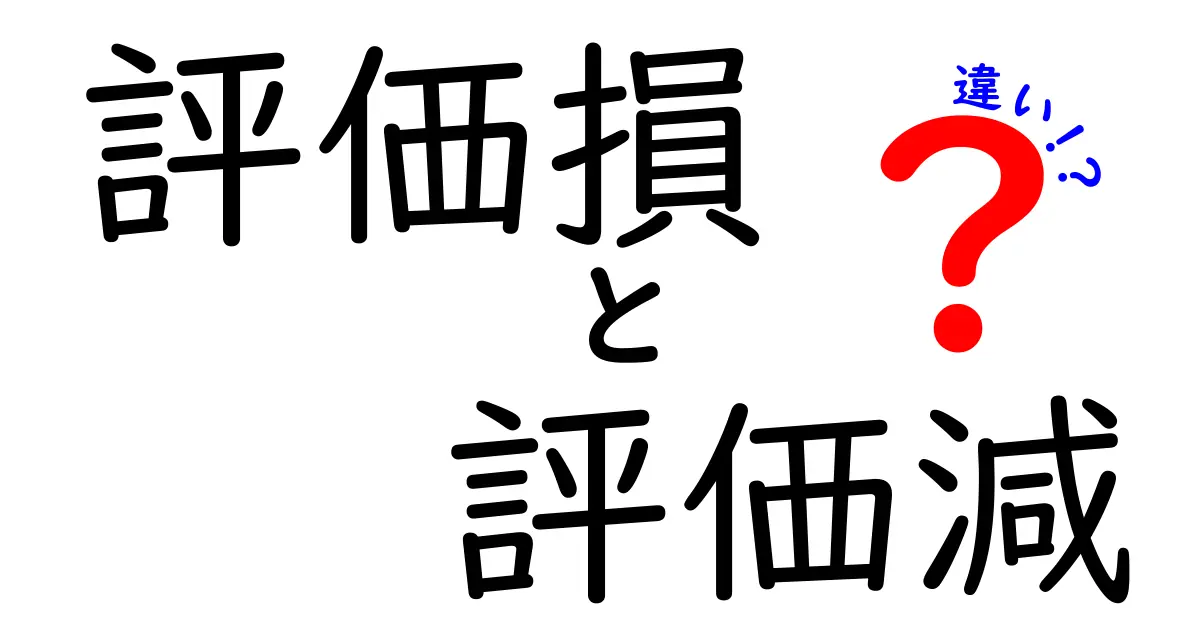

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
評価損と評価減の基本的な意味とは?
会計や投資の世界でよく耳にする「評価損」と「評価減」は、どちらも資産の価値が下がったことを表す言葉ですが、意味や使い方には違いがあります。
まず、評価損とは、企業や投資家が保有する資産の価値が購入時よりも下がったために発生する損失を指します。これは、会計上の計算で資産の価値を見直した結果、実際の市場価格や現在の価値が購入価格よりも低くなった状態のことです。
一方、評価減は、資産の帳簿価格(簿価)を減額することを意味し、具体的には貸借対照表(バランスシート)に記載される資産の価値を下げる会計処理のことです。
つまり、評価損は価値の下落によって発生する損失のことで、評価減はその損失を会計上どのように反映するかという処理の違いを示します。
評価損と評価減の違いを詳しく説明!仕組みと使い方のポイント
評価損と評価減の違いを理解するためには、会計処理の流れを知ることが大切です。
まず、資産の価値が下がっているかどうかを評価します。例えば、株式や商品、固定資産などの価値が市場価格の低下などにより減少した場合、評価損として計上されます。これは会社の利益にマイナスの影響を与えます。
次に、その評価損を帳簿にどう反映させるかが評価減です。評価減が行われると、帳簿の資産価値が減り、貸借対照表の資産の部の金額が少なくなります。これが意味するのは、資産の実態価値により近い数字を示そうとする会計の仕組みです。
大切なのは、評価損は価値の下落による損失の実態、評価減はその実態を会計帳簿に反映する処理だということです。
また、評価減は法律や会計基準に基づいて行われ、必ずしも評価損が全額評価減になるわけではありません。例えば、将来の回復可能性(リカバリー)があればその分は評価減しないこともあります。
評価損と評価減の違いを表で比較!
| 項目 | 評価損 | 評価減 |
|---|---|---|
| 意味 | 資産価値の下落による損失 | 帳簿上の資産価値を減額する会計処理 |
| 発生のタイミング | 資産の市場価値が下がった時点 | 評価損を認識した後に処理 |
| 会計上の影響 | 損益計算書に損失として計上 | 貸借対照表の資産額が減少 |
| 目的 | 価値の実際の下落を反映 | 帳簿価格と実態の一致を図る |
| 法律・基準 | 会計基準に基づき認識 | 会計基準・法律に従い調整 |
この表からもわかるように、評価損は損失の内容自体を示し、評価減は損失を帳簿にどう反映するか一歩踏み込んだ処理だと理解できます。
特に企業の財務状況を分析する際には、この違いを正しく理解していることが重要です。
評価損と評価減の活用シーンと注意点
実務では、投資や保有資産の管理において評価損と評価減は頻繁に使われます。
たとえば、不動産や株式などの金融資産がある場合、時価が購入時の価格を下回れば評価損が発生します。その後、会計で合理的な期間と方法で評価減を行い、正しい資産価値を帳簿に反映します。
注意点としては、評価損が発生してもすぐに評価減するわけではなく、価値の回復の可能性や将来の利益見通しを考慮する必要があることです。安易に評価減を行うと、企業の財務状態が過度に悪化して見えることがあります。
また、税務上も評価減が認められるかどうかは基準が異なる場合がありますので、専門家の意見を参考にすることが大切です。
このように、評価損と評価減の違いを正しく理解し、その発生と処理の流れを押さえることで、財務内容の正確な把握や投資判断に役立てることができます。
評価損と評価減、言葉は似ていますが会計での役割は少し違うんですよ。評価損は資産の価値が下がってしまった“実際の損失”のこと。一方、評価減はその損失を帳簿にどう反映させるかという“会計処理”なんです。つまり、評価損がないと評価減もありません。会計って実際の数字だけじゃなく、信頼できる数字に近づける作業があるんですね。こうした仕組みが会社の財務の透明性を保っているんです。中学生でも覚えておくと将来役立ちますよ!





















