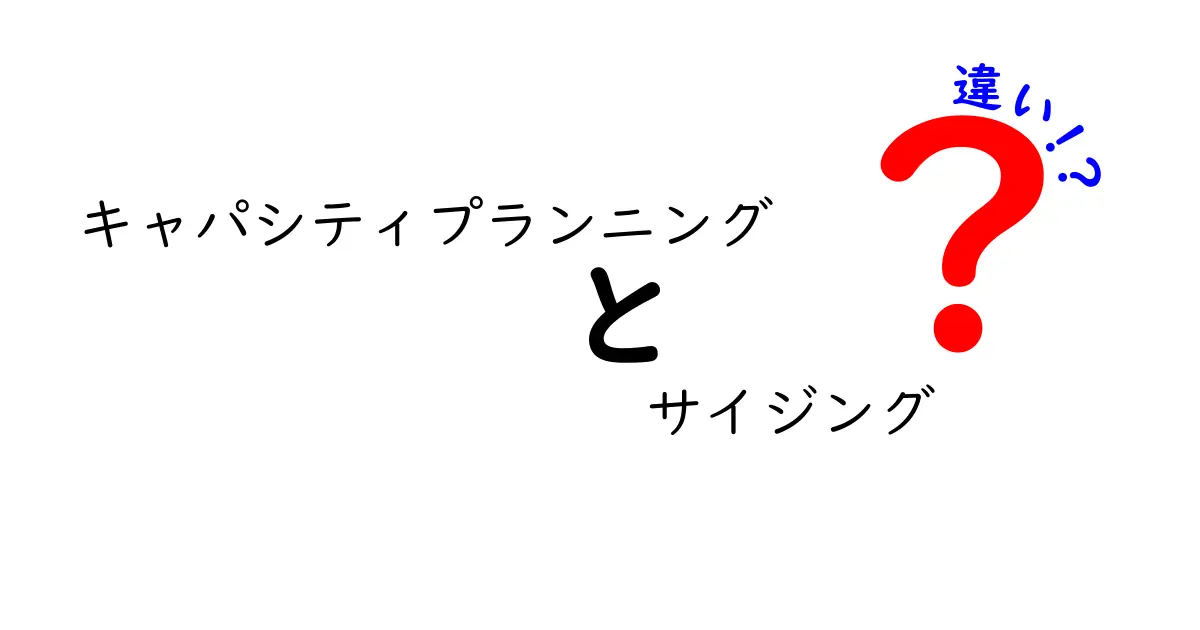

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
キャパシティプランニングとは何か?
まず、キャパシティプランニングとは、将来のシステムやサービスが問題なく動くように必要な資源や能力をあらかじめ見積もり、計画することを言います。例えば、ウェブサイトの訪問者が増えたときに、サーバーがパンクしないようにあらかじめ準備をしておくイメージです。
この計画では、現在の使用状況や将来の予想トラフィックを元に、CPUやメモリ、ストレージの容量、ネットワーク帯域などを分析して、最適な資源量を決めます。
つまり、未来を見越して、適切な量の設備を準備することがキャパシティプランニングの役割です。これによって、無駄なコストを抑えつつ、サービスが安定して稼働し続けられます。
サイジングとは何か?
一方、サイジングとは、特定のシステムや機器の導入・構築時に必要な性能や容量を決める作業のことを指します。たとえば、新しいサーバーを買うときに「どのくらいのCPUパワーやメモリ容量、ストレージ容量が必要か」を決める作業がサイジングです。
サイジングは、現在の要件や直近の利用状況に基づいて行われることが多いですが、場合によっては将来の拡張を見込みながら決めることもあります。
キャパシティプランニングの結果を利用してサイジングを行うことも多いため、両者は関連性がありますが、サイジングはあくまで装置やシステム単位での具体的なサイズ決定が中心です。
キャパシティプランニングとサイジングの主な違い
ここで、両者の違いを表でまとめてみましょう。項目 キャパシティプランニング サイジング 目的 将来の需要に対して最適な資源計画を立てる システムや装置の具体的な性能・容量を決定する 対象範囲 サービス全体やシステム全体 個別システムや機器単位 期間 中長期的(数か月~数年) 短期的、導入時点中心 主な手法 使用データ分析、需要予測、リソース計画 仕様決定、性能評価、要件設定 重要性 リスク管理やコスト管理に重要 適切なシステム構築に不可欠
このように、キャパシティプランニングは長期的な視野での準備、サイジングは具体的な装置の設計といった違いがあります。
まとめ
まとめると、キャパシティプランニングは将来の需要を見越して最適な資源を計画するプロセスで、サイジングはその計画や現在の要件をもとに具体的なシステムや装置の性能や容量を決める行動です。
両方ともITシステムやネットワークの安定運用に欠かせない作業ですが、役割や視点が異なるため、それぞれの意味を理解して使い分けることが大切です。
これからシステム設計やサービス運用に関わる方は、キャパシティプランニングとサイジングの基本を押さえて効率的で安定したシステム構築を目指しましょう。
サイジングって、ただ単に"サイズ決め"って意味に思いがちだけど、実はシステムの性能や容量を正確に見積もるすごく重要な作業なんだよね。例えばサーバーのサイジングを間違えると、必要なパワーが足りなくて処理が遅くなったり、逆にオーバースペックで無駄なコストがかかったりしてしまう。だから、丁寧な調査や分析が必須なんだ。キャパシティプランニングの結果を基に決める場面も多いから、両方の理解が大切だね。





















