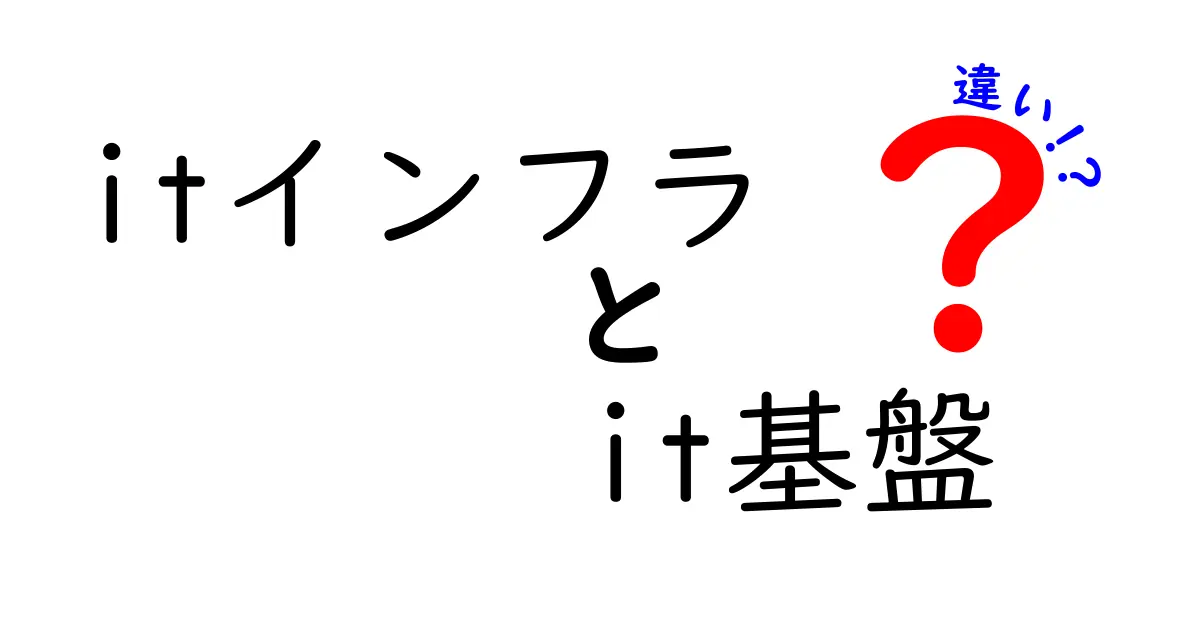

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ITインフラとIT基盤とは何か?
ITインフラとIT基盤は、似た言葉で混同しやすいですが、それぞれ意味が少し違います。
ITインフラは、パソコンやサーバー、ネットワークケーブルや電源設備など、企業がITを使うための物理的な設備や技術全般を指します。
一方、IT基盤は、ソフトウェアやクラウドサービス、運用ルールやシステムの仕組みを含めた、ITインフラを使ってサービスを提供するための土台全体を意味します。
つまり、ITインフラは主にハードウェアや物理的な設備を表し、IT基盤はより広い意味でソフトも含む、ITを支える全体の仕組みを表しているのです。
ITインフラとIT基盤の違いを具体的に理解しよう
では、具体的にどんな部分が違うのか見ていきましょう。
ITインフラは、パソコン、サーバー、ルーター、スイッチ、データセンター、電源装置、ネットワークケーブルなどの物理的な要素が中心です。
例えば、会社のネットワークがつながるための設備や、データを保存するサーバーがそれにあたります。
IT基盤は、それらのITインフラ上で動くOS、ミドルウェア、クラウド環境、セキュリティ対策、運用管理手順やサービス管理システムなどを含みます。
IT基盤は、ITインフラを生かしてビジネスアプリやサービスを安定して提供できるようにするための仕組み全体と考えましょう。
下記の表でまとめてみます。
| 項目 | ITインフラ | IT基盤 |
|---|---|---|
| 意味 | 物理的な設備や技術の総称 | インフラを含むITの仕組み全体 |
| 主な構成要素 | パソコン、サーバー、ネットワーク機器、電源など | OS・ミドルウェア、クラウド環境、セキュリティ、運用管理 |
| 役割 | IT環境の土台を提供 | ITサービスを安定して運用する仕組み |
| 視点 | 主にハードウェア中心 | ハードもソフトも含む全体像 |
ITインフラの中でも「サーバー」は特に重要な存在です。
例えばスマホでゲームをするとき、そのゲームのデータはどこかに保存されているのですが、それは自分のスマホではなく "サーバー" と呼ばれる専用のコンピューターにあります。このサーバーがないと、ゲームは動きません。
また、サーバーには種類があり、大きさや性能も様々。用途によって選ぶのがポイントです。
だから、ITインフラの理解にはまずサーバーの役割を知ることが近道なんです。
次の記事: フレームワークと開発言語の違いとは?初心者でもわかる基本解説 »





















