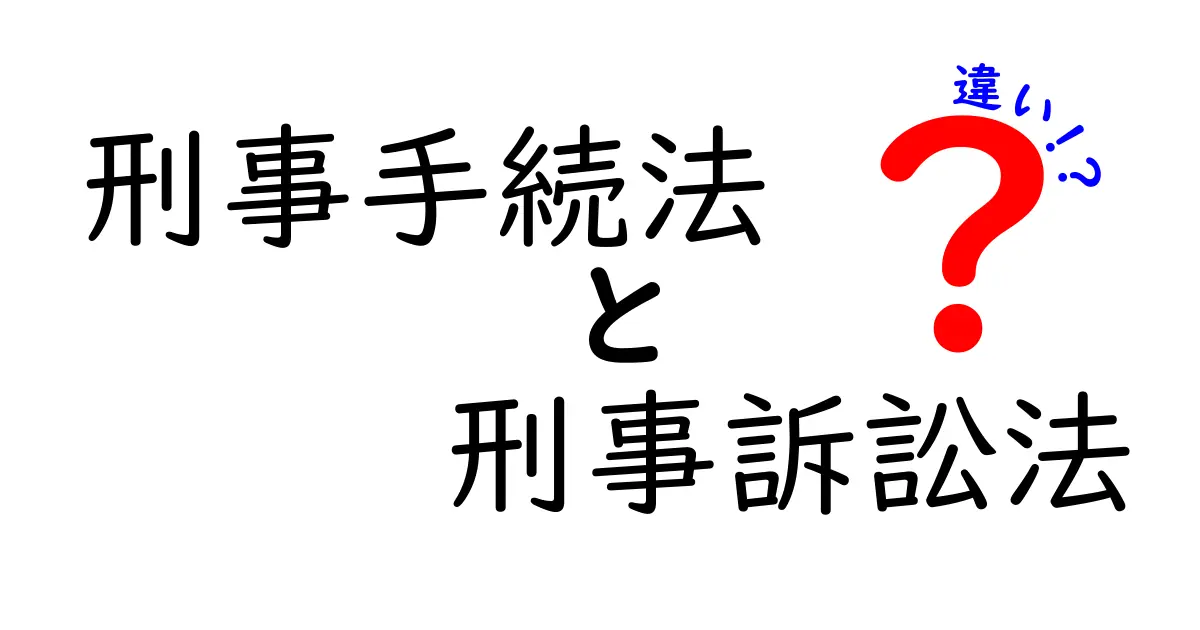

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
刑事手続法と刑事訴訟法とは何か?
まず、刑事手続法と刑事訴訟法は、犯罪があった時にどのように事件を処理するかを決めた法律ですが、実は扱う範囲や役割に違いがあります。
簡単に言うと、刑事手続法は、警察や検察、裁判所が事件を調べたり裁き方のルールを定めた新しい法律です。
一方、刑事訴訟法は、それまで使われてきた、被告人の権利を守りつつ処理の流れを決めている法律です。
刑事手続法は2020年代になってできた法律で、刑事訴訟法を補うための内容も多いです。
これらは日本の刑事司法の仕組みを左右し、私たちの生活にとても関係しています。
このように、どちらも犯罪事件に関する法律ですが、それぞれ特徴があるので詳しく見ていきましょう。
刑事手続法と刑事訴訟法の主な違いとは?
刑事訴訟法は、裁判で事件を決める時の基本的なルールを定めています。
たとえば、捜査の方法、裁判の進め方、証拠の扱い、被告人の権利などが詳しく書かれています。
一方、刑事手続法は、犯罪の捜査から裁判までの手続き全体の流れをスムーズかつ公平に進めるための新しい法律です。
たとえば、被疑者の取調べにおける録音や可視化の義務なども含まれ、透明性と人権保護を強化しています。
具体的な違いは次の表をご覧ください。
このように、刑事訴訟法は昔からずっと基本を支えているのに対して、刑事手続法はより現代社会に合わせて作られた法律といえます。
両者は相互に補完し合いながら、犯罪捜査や裁判の正義を守っているのです。
なぜ刑事手続法が新しく作られたのか?その背景と重要性
刑事訴訟法は100年以上前にでき、その後も改正されてきましたが、時代の変化により捜査のやり方が大きく変わりました。
たとえば、スマホやインターネットの普及で証拠の種類が増え、取調べの可視化など新しいルールも必要になったのです。
そこで、刑事手続法が新設され、警察や検察の捜査手続きの透明化や被疑者・被告人の人権保護の強化が図られました。
今までは取調べの録音は任意でしたが、刑事手続法では録音や映像記録が義務付けられ、不適切な取り調べを防ぐ効果が期待されています。
また、令状の発行や押収・捜索のルールも明確化され、捜査の適正さを確保しています。
このように、刑事手続法は現代の社会情勢や技術の発展に対応した新しい刑事司法の仕組みとして非常に重要なのです。
法律の世界で「手続法」と「訴訟法」という言葉を聞くと、なんだか似ていて分かりづらいですよね。でも刑事手続法は、警察や検察が事件を扱う最初の段階から裁判まで、全体の流れをスムーズにするための法律なんです。特に取調べの様子を録音・録画するルールができて、昔より透明性がぐんと上がりました。こうした新しいルールができた背景には、過去の冤罪事件の反省や時代の変化があります。だから単なる法律用語じゃなくて、「正しい手続きで被疑者の人権を守ろう!」という強い思いが込められているんですね。法律って堅苦しく感じるけど、こうした裏話を知ると面白いですよ。
前の記事: « 公布と施行の違いって何?法律ができるまでの仕組みをやさしく解説!





















