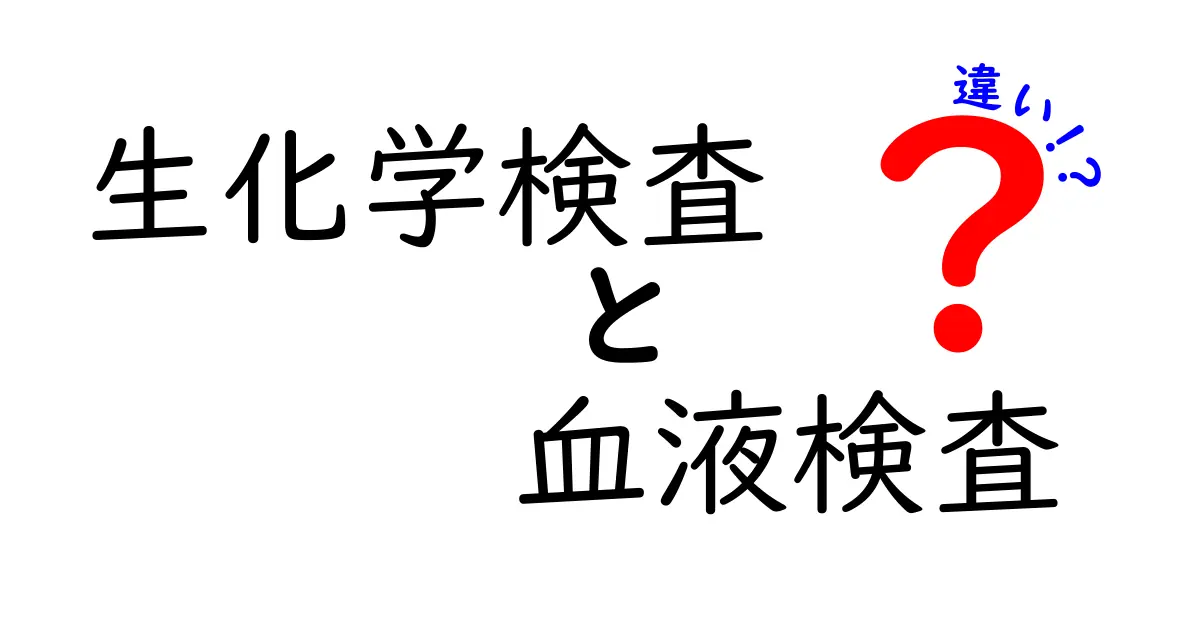

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
生化学検査と血液検査の基本の違いを理解しよう
まずは生化学検査と血液検査の基本的な違いについて説明します。血液検査は体の状態を調べるための検査の一種で、血液を使って行われます。一方、生化学検査は血液の中の成分の化学的な性質や量を詳しく調べる検査のことを指します。つまり、生化学検査は血液検査の中の一部として考えることもできるのですが、実はもっと広い範囲で血液以外の体液も対象になることもあるんです。
血液検査は主に血液全体を調べるもので、血球(赤血球、白血球、血小板)の数や形、ヘモグロビンの量など、血液の基本的な情報を調べます。生化学検査は血液に含まれる糖や脂質、酵素、ホルモンなどの成分を分析して、肝臓や腎臓の働き、代謝の状態、栄養のバランスなど体の様々な機能の状態を調べるのに役立ちます。
このように、どちらも体の健康状態を知る重要な検査ですが、調べる内容や目的が少し違います。生化学検査はより細かく血液の中の物質を測る検査という位置づけになります。
血液検査と生化学検査の具体的な検査内容と特徴
次に、それぞれの検査の内容についてもう少し詳しく見ていきましょう。
血液検査では、主に以下のような検査項目が含まれます。
- 赤血球(RBC)数:酸素を運ぶ役割を持つ細胞の数を調べます。
- 白血球(WBC)数:免疫に関わる細胞で、感染症の有無などを判断します。
- 血小板(PLT)数:血液の凝固に重要な細胞です。
- ヘモグロビン量:酸素を運搬する赤血球の成分の濃さを調べます。
生化学検査では、血液中の溶けている成分を調べます。例えば、
- 血糖値:血液中のブドウ糖の濃度。糖尿病の診断に使われます。
- 肝機能検査:AST、ALTという酵素の量を測り、肝臓の状態を調べます。
- 腎機能検査:クレアチニンという物質の量で腎臓の機能を確認します。
- 脂質検査:コレステロールや中性脂肪の量を調べ、心臓病のリスクを判定します。
このように血液検査は主に細胞の数や種類を調べるもので、生化学検査は血液中の化学物質の量や性質を調べる検査です。
血液検査と生化学検査の違いがわかりやすい表でまとめ
ここまでの内容をわかりやすく表にまとめました。検査種類 対象 調べる内容 目的 血液検査 血液中の血球類(赤血球、白血球、血小板) 細胞の数・種類・形態(例:赤血球数、ヘモグロビン量) 貧血、感染症、出血傾向の診断 生化学検査 血液中の化学成分(糖、脂質、酵素など) 成分の量・性質(例:血糖値、肝酵素、クレアチニン) 肝臓や腎臓の機能評価、代謝異常の発見
まとめ:生化学検査と血液検査はどう使い分けられる?
これまでの説明で、生化学検査と血液検査には明確な違いがあることがわかりました。血液検査は体の血液細胞の状態を見て、貧血や感染などを発見するのに役立ちます。
一方、生化学検査は血液内の化学成分を調べることで、肝臓や腎臓の働き、代謝の状態などを詳しく知ることができます。健康診断や病気の診断で、両方の検査を組み合わせて行うことが多いのは、それぞれが異なる重要な情報を提供するからです。
専門的には生化学検査は血液検査の一部として含まれますが、日常的な使い方では目的や検査内容の違いから区別して理解すると良いでしょう。
この違いを知っていると、病院で検査の説明を受けた時にもイメージがつきやすく、不安も減るはずです。
健康管理のために検査の意味を理解することは大切ですね。
生化学検査の中で特に面白いのが肝機能検査です。肝臓は体の中で解毒や栄養の代謝を行う重要な臓器ですが、ASTやALTと呼ばれる酵素の値を測ることで肝臓のダメージを知ることができます。例えば風邪が長引いたり黄疸が出た時、この値が異常になることがあります。普段はなかなか聞きなれない言葉かもしれませんが、健康診断の結果で見ることが多いので覚えておくと役に立ちますよ。





















