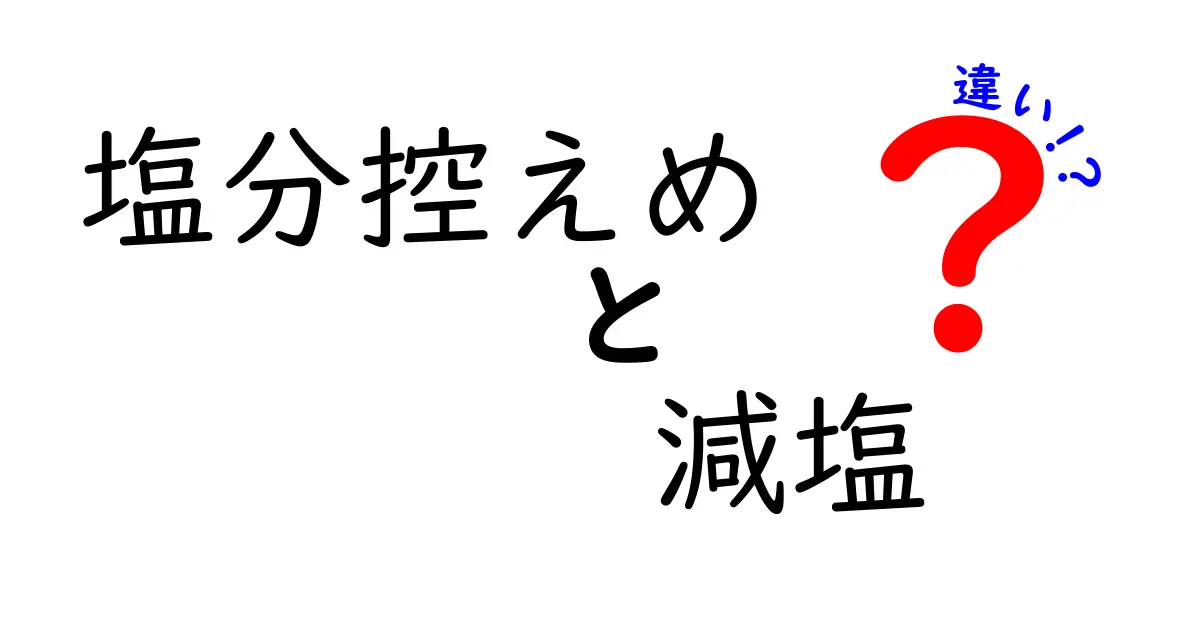

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:『塩分控えめ』と『減塩』ってどう違うの?
みなさんはスーパーやコンビニで食品を買うとき、『塩分控えめ』や『減塩』という表示をよく見かけますよね。
どちらも健康に良さそうなイメージですが、実はこれらの言葉には少しだけ意味の違いがあります。
今回は『塩分控えめ』と『減塩』の違いについて、中学生でもわかりやすいように丁寧に解説します。
健康的に食事を楽しみたい方はぜひ参考にしてください。
『塩分控えめ』とは何か?
『塩分控えめ』とは、通常の食品に比べて塩分の量をおさえていることを表します。
消費者に向けて、「この商品は通常より塩分を控えているので健康に気を使いたい方におすすめですよ」という意味で使われることが多いです。
ただし、法律で明確な基準が決められているわけではなく、メーカーが自主的にこの表現を使っている場合も多いです。
つまり、『塩分控えめ』はやや曖昧で、どれくらい塩分が減っているかは商品によって違うことがあります。
『減塩』の意味と基準
それに対して『減塩』という言葉は、よりはっきりとした意味があります。
日本の食品表示基準では、『減塩』や『塩分カット』と表示する場合、通常の食品に比べて塩分が25%以上減っていることが必要です。
したがって、『減塩』表示のほうが科学的に計算されていて、どれくらい塩分が減っているかが明確になっています。
健康のためには、『減塩』と表示された商品を選ぶほうが安心できるでしょう。
『塩分控えめ』『減塩』の違いまとめ表
| ポイント | 塩分控えめ | 減塩 |
|---|---|---|
| 基準 | 明確な基準なし(メーカー任せ) | 通常品より25%以上減少 |
| 健康効果 | 目安程度 | 科学的に証明されている |
| 表示の信頼性 | 商品ごとにばらつきあり | 一定の基準で保証されている |
なぜ塩分を控える・減らすことが大切なの?
塩分は私たちの体にとって必要な栄養素の一つですが、過剰に摂ると血圧が上がりやすくなり、高血圧や心臓病・脳卒中などのリスクが高まると言われています。
世界保健機関(WHO)も1日の塩分摂取目標を5グラム未満にすることを推奨しています。
そのため、少しでも塩分を控えたり減らしたりすることが、長い目で見ると健康を守るうえでとても大切なのです。
実際に商品を選ぶときのポイント
塩分を控えたり減らしたりしている商品を選ぶときは、
- 『減塩』と表示されているかどうか
- 実際の塩分量の数値(パッケージの栄養成分表示を確認)
- 味のバランスや満足感も考慮
を意識するとよいでしょう。
たとえば、『塩分控えめ』であってもどれくらい減っているか分からないことがあります。
できれば減塩基準に沿った商品を選ぶのがおすすめです。
しかし、味が薄すぎて続けられないと意味がないので、無理しすぎない範囲で習慣にするのがコツです。
まとめ
『塩分控えめ』と『減塩』は似た意味ですが、
『減塩』は塩分が25%以上減っていると法律で定められ、信頼性があるのに対し、
『塩分控えめ』は基準が明確でなく、商品によってまちまちです。
塩分をへらすことで、高血圧や生活習慣病の予防につながるため、
健康を考えながら商品を選ぶときには『減塩』表示や実際の塩分量に注目しましょう。
無理なく続けることが最大のポイントです。
この記事が皆さんの健康的な食品選びに役立てば幸いです。
『減塩』が25%以上塩分を減らした商品に表示されることはよく知られていますが、意外と『塩分控えめ』の基準が曖昧だということは知らない人も多いですよね。実は、『塩分控えめ』はメーカーが自由に使っていい言葉で、どれくらい減っているかは商品によって違います。だから買うときは、成分表示をしっかり見て、甘すぎず自分の味覚に合ったものを選ぶことが大切なんです。健康にいいからと言って味が合わないと続かないですからね。こんなちょっとした違いも押さえておくと賢くお買い物ができますよ!
前の記事: « 熱射病と熱疲労の違いとは?見分け方や予防法をわかりやすく解説!





















