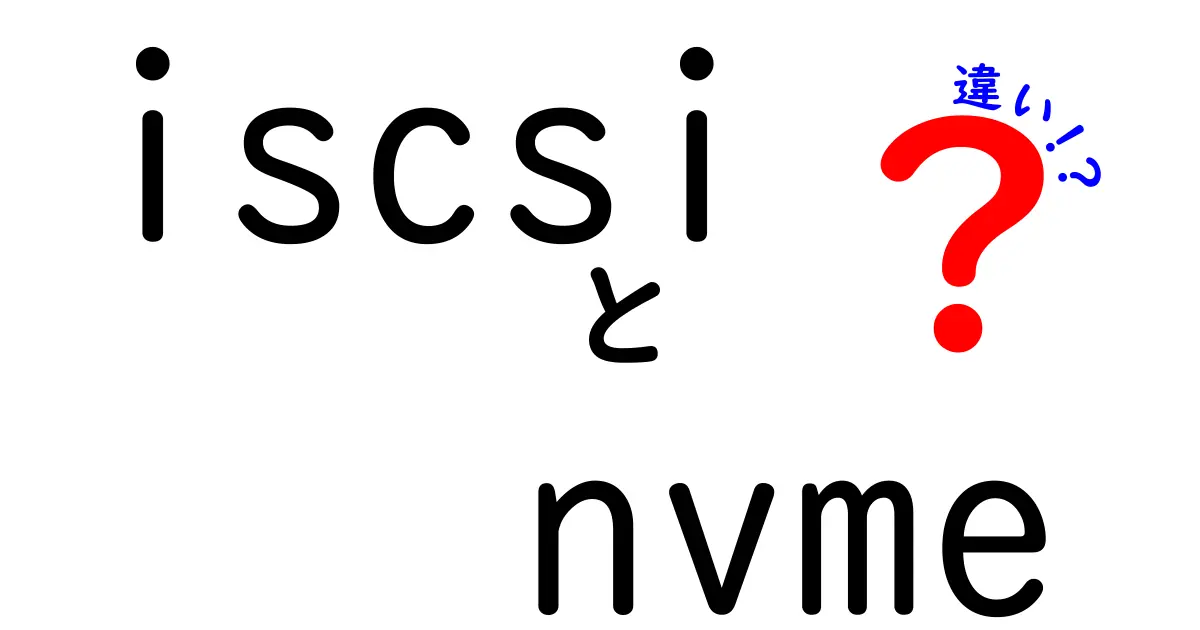

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
iSCSIとNVMeとは何か?
まずは、iSCSI(アイエスシスアイ)とNVMe(エヌブイエムイー)が何なのかを理解しましょう。
iSCSIは「Internet Small Computer System Interface」の略で、ネットワークを使ってストレージ(データを保存する装置)にアクセスする仕組みです。簡単に言うと、遠くにあるハードディスクなどのストレージを自分のコンピュータの一部のように使える技術です。
一方、NVMeは「Non-Volatile Memory Express」の略で、パソコンやサーバーで使う高速なSSD(ソリッドステートドライブ)にアクセスするための通信プロトコルです。特にパソコン内部でのやり取りを速くするために作られていて、データの読み書きをとても速く行えます。
両者ともストレージに関わる技術ですが、用途や使われる場所が異なるのです。
利用シーンと接続方法の違い
iSCSIはネットワーク越しにストレージを使うための技術です。例えば会社のサーバーから離れた場所にあるハードディスクをネットワーク経由で扱いたい場合に使われます。つまり、LANやインターネットのように遠くの機器と接続することを前提としています。
一方、NVMeは主にコンピュータ内部の高速な記憶装置(SSD)に直接アクセスするためのプロトコルです。データセンターのサーバーでも、ストレージが直接マザーボードに接続された形で使われます。
このため、iSCSIはネットワーク接続向け、NVMeは内部接続向けと考えるとわかりやすいです。
速度と性能の比較
速度の面を見ると、NVMeはとても高速です。PCI Express(PCIe)と呼ばれる高速な接続を使い、SSDの性能を最大限に引き出せます。そのため、大容量のデータも素早く読み書きできます。
一方、iSCSIはネットワークの速度に依存するため、速度はネットワーク環境に大きく左右されます。一般的な社内ネットワークやインターネット越しでは、NVMeに比べて速度が遅くなることが多いです。
以下の表で簡単にまとめました。
実はNVMeは最近のパソコンやサーバーで急速に普及している技術で、高速なSSDの性能を最大限に活かすために開発されました。名前の『Non-Volatile Memory Express』は、「消えない記憶領域」と「高速表現」を意味していて、まさにデータを失わずにとても速く読み書きできる仕組みをイメージしてください。これにより、ゲームや動画編集、データ解析など、たくさんのデータを扱う作業が快適になりました。iSCSIとは違い、主にコンピュータ内部で活躍する技術なので、家の中でパソコンの部品同士がスムーズに会話しているようなイメージですよ。
次の記事: 屋側配線と屋外配線の違いとは?初心者にもわかるポイント解説! »





















